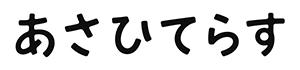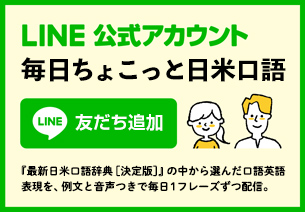1. 迷路散歩宣言
人間には、それをやっている間、他のすべてのことを忘れられる何か、つまり心の逃避先が必要である。子ども時代の私にとって、それはSFやファンタジー小説を読むことであり、もうひとつが迷路だった。
好きが高じて自分でも迷路を描くようになり、描いている間は夢中になって、嫌なことを忘れることができた。そのうち、授業中、ノートの片隅や配られたプリントの裏なんかに、いや、ノートの片隅でなくノートいっぱいに、プリントの裏ではなく表にも、うねうね描き倒すようになって、学校に通いながら、みるみる描き方が上達した。
迷路なんてものは子ども時代に限った趣味かといえば、そんなことはない。大人になっても描き続け、ついには迷路の本まで出版した。ちっとも売れなかったけども、迷路作家と自称できるようになったのは、ちょっとした自慢である。
ただし自称しているだけで、とくに仕事は来ないので、最近はあまり描いていない。もちろん頼まれればいくらでも描く所存であるが、頼まれないので、最近は迷路な町を探して散歩することで気を吐いている。
今では迷路を描くより、迷路な路地を歩くほうが面白い。
私はわりと方向感覚がよく、あまり道に迷わないのが自慢だった。最近はだいぶ衰えて、たまに迷うようになったが、それでも普通の人よりは迷わないほうだと思う。そのため、一般に迷路っぽいとされている町でも、たいして迷わない。仮に一瞬迷ったとしても、少し周囲を探り歩けば把握できてしまう。ありがたい能力と言えるが、これが私は昔からとても残念に思っていた。
もっと迷いたい!
迷うことによって、世界の見え方が変わってくる瞬間がいいのだ。家の近所であっても、ひとたび迷えば、世界はよそよそしいものとなり、いったいここはどこなんだ、と異世界感に浸ることができる。異世界感というのが大袈裟ならば、旅情と言い換えてもいい。
子どもの頃は、突然自分が誰かもわからなくなり、知らない街にポツンと置き去りにされたら面白いと思っていた。記憶喪失になって行方不明になった人が、何年か後に突如記憶が戻って家に帰ってきたという話を何かで読んで、甘美な快感のようなものを覚えた。
そんなことを人に話すと、「それって認知症でしょ。ほうっておいてもそのうち実現しますよ」と冷ややかにつっこまれ、一気に熱が冷めかけたが、そうではないと思い直した。認知症と違うのは、自分の名前も居場所もわからなくなっても頭脳は明晰であることで、記憶は欠落しても判断力は衰えていないことがこの冒険のポイントである。
わからなくなった自分と場所を、明晰な頭で謎解きしていくのが面白そうに思えたのである。

失踪願望みたいなものがあったかもしれない。
「失踪」とか「蒸発」という言葉に魅力を感じる。実際にはいろいろ大変だろうし、人知れず事故に遭うとか、夜逃げみたいに失踪しなければならない状況に陥るのは避けたいけれども、そういう切迫した失踪でなければ、それは昨今のラノベなんかで人気がある異世界転生に近いものではないか。
そんな性格だから、日常で散歩するときも、知らない道知らない道へと歩いて行くし、仕事でどこかへ出かけた折りには、近くにいい迷路の町がないか調べ、あれば寄ってみたりしている。旅先で「迷路」「迷宮」「迷子」などのネット検索をかけて、出てきた土地に行ってみるのである。
調べてみると、迷路っぽさを自ら標榜したり、標榜しなくても迷路と噂されたりする町は各地にあった。行けば、たしかにこれは迷路だと思う場所もあった一方で、それほどでもない土地もあり、あちこち行き慣れてくるうちに、だんだん、少々の迷路では満足できなくなってきた。
たとえば、東京にも迷路っぽいと言われる街区がたくさんあるものの、行ってみると、範囲が狭くてすぐに歩き終わってしまったりして、なかなか眼鏡にかなう迷路に出会わないのだ。
眼鏡にかなう迷路がどういうのかというと、まず絶対条件として歩いているうちに方向がわからなくなることと、できれば帰り道もわからなくなれば、もっといい。あとできれば道は狭いほうがいいし、高低差があったり、これは本当に道なのかどうかわからないすき間があったり、ところどころ意外な景観や不思議な景色が現れたら、完璧である。
つまるところ、異世界感や旅情が喚起される迷路が、私の眼鏡にかなう迷路ということになる。旅情の喚起のされかたは人それぞれなので、具体的にどういうのか、結局説明になっていない気もするけれど、ああ、私はこんなところにいる、と自分の存在の心もとなさと、それでも確かに存在している力強さを同時に感じ、世界がクリアになって身に迫ってくるリアリティ、と言ったらいいのかもしれない。

まあ、理屈はどうでもいい。
コロナ禍で旅行ができなくなった時、苦肉の策として近所の散歩を始めた。もう10年以上住んでいる家のまわりに、一度も歩いたことのない道がいくつもあることを知り、片っ端から探検した。家の近くにこんなにも知らない道があったのかという驚きとともに、もっと探検したい欲がむらむらと湧きあがってきて、とにかく行ったことのない道、知らない道を見つけてはどんどん自分の勢力地図を広げていった。
そのうち近所にはもう未知の道がなくなり、バスや駅で少し遠くの町へ出かけては、知らない道を歩き回るようになった。
今では自分の歩いた道をGPSを使って記録し、そのすべてを地図に落としこんで、盛大な散歩マップをつくるに至っている。それによると、もはや自宅から半径3キロ以内に歩いていない道はほぼなく、今では電車に乗って30分から1時間行った先の駅から歩きだしたりしている。そうでもしないと知らない道がないのである。散歩ごときに交通費がかかってしょうがないが、これはもう性分だからとあきらめている。
そうまでして続ける散歩には結構な効能がある。
肉体の健康にもいいだろうし、気持ちが滅入ったときや、明日がくるのが全然楽しみじゃないと思ったときなど、散歩ひとつで気が晴れることも少なくない。
できれば自然のなかの道か、もしくは迷路のような道を歩くのが、とくに私の精神にいいようだ。迷路の散歩は、私にとって束の間、現実の辛さや面倒くささを忘れることができる清涼剤なのだ。

そんなわけでこれから迷路を歩く話をしようと思う。
旅行や散歩のついでに訪ねた話だから、深い考察などはない。その土地が迷路になった経緯とか、そこに暮らす人々の日常とか、そういう本格的な話ではなくて、知識も知恵も深まらず、力が抜けるようなふにゃふにゃなエッセイになる予定である。どこかへ逃げたくなったときに読んでほしい。