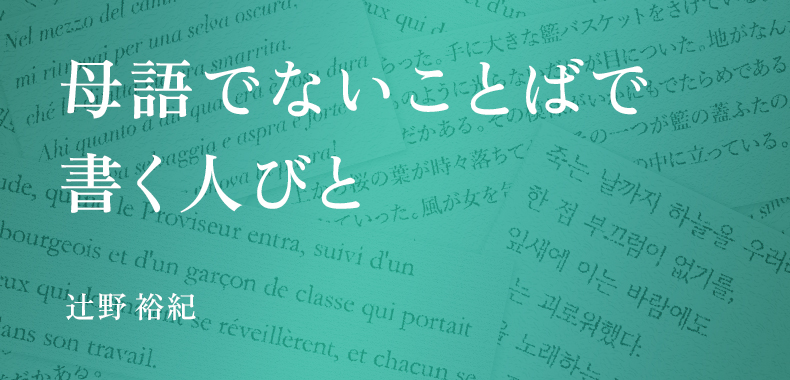第1回:「非母語という希望:言語論と文学の交差路へ」
「母語は、〈臨界期〉と呼ばれる時期を過ぎれば、取り換えがきかない」
私は、韓国語を専門とする言語研究者であり、言語教育者でもある。学部時代は、フランス語を専攻しつつ他の言語群とも多く戯れ、また、大学院博士課程在学中には、ソウルの大学で専任講師として日本語や日本語学を講じたりもした。かくして言語の森を一定期間、
私が生まれたとき、日本語は既に十全なる形で存在していた。しかし、私の意志で日本語を母語として選んだわけではない。この点で、母語は〈選択不能な
翻って、母語ではない、他者の言語=非母語は、原理的には自由に選び取ることが可能である。選択不能だった母語に対して、選択可能な非母語はある種の希望と言ってよい。
私のフランス語の恩師であり、私の言語観、分けても〈他者の言語〉への構えに至大なる影響を与えてくださった、仏文学者にしてフランス語表現作家の水林章氏は、自伝的著作 Une langue venue d’ailleurs(Gallimard, 2011)の中で、『自死の日本史』などで知られるモーリス・パンゲ氏に「君のフランス語は5歳のころから話しているフランス語だ」と絶賛されたエピソードを披露している(p.18)。実際には、普通の大学生と同様に、18歳で初めてフランス語と接触したにもかかわらずである。モーリス・パンゲ氏のこのことばは、非母語に心酔し、母語話者を
私は、こうした、母語でない言語で執筆する書き手たちに予て興味を持ってきた。文学的な関心はもとより、一介の言語教師、一介の言語学習者として、語弊を恐れずに言えば、「究極の言語学習者」のようにも見える越境作家たちの生や言語への構えに接近することで、言語教育=言語学習に対する何らかの示唆を得ることができるのではないか。また、言語道具観が
もちろん、母語とは何かという根源的な問題もある。例えば、〈出自〉や〈移動〉などによって幼き頃から多言語にさらされてきた者たちにとって、母語とは、国家名や民族名が付された「なんとか語」ではなく、複数の相互浸透的なことばたちから構成される、容易に名づけえぬ存在である。例えば、温又柔氏の小説『真ん中の子どもたち』(集英社、2017年)の「こうした子どもたちの「母語」は複数の言語から成っていると思う」(p.152)という箇所は注目に価する。「こうした子どもたち」というのは、台湾における「台湾出身者と外国籍所有者の間にうまれた」ダブルの子たち=〈新台湾之子〉のことであり、彼女ら、彼らにとっての母語とは、単一の言語から組成された均質なものでは決してないのである。また、いわゆる〈多言語社会〉に住む者たちにとっても、「母語はこれ」と指目しえないケースは多い。そうした論件についても、連載の中でいつか触れることがあろう。母語/非母語という牧歌的な二分法に疑義を
本連載は、言語論的思考と文学の世界の交差路である。毎回、ひとりの越境作家を取り上げ、その人生や作品などを紹介しつつ、ことばを学ぶことや書くこと、そして、ことばと共に生きることなどについて考えていきたいと思う。
なお、紹介する作家の選定については、特に明確な方針に基づいてはおらず、私の偏った読書傾向が反映された、恣意的なものである。越境文学を体系的に