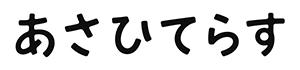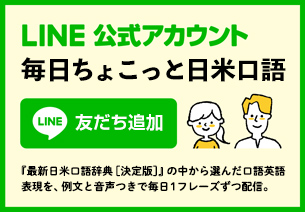自分が花みたい
今泉美佳さんから最初に連絡をもらったとき、短い文面のなかに衝撃的なひとことがありました。それは、自分の体について「壊れる」という言葉が使われていたこと。そこには「四歳からの難病」と闘っていて、「皮膚と関節が壊れ続けて」いる、と書かれていました。
「壊れる」は、一般的には椅子やパソコンなど、モノに対して使われる動詞です。百歩譲って他動詞の「壊す」であれば、「お腹を壊す」のように「調子が悪くなる」という意味で体に対して使われることもあります。けれども、「壊れる」という自動詞には、もう「私」の介入する余地はありません。金属疲労や劣化など長年の負荷が蓄積した結果、そのモノの内部的な構造に不具合が生じ、もとの機能を万全に発揮できなくなる。「壊れる」には「自壊していく」というニュアンスがあります。もちろん「壊死」などの医学用語はあります。けれども、「壊れる」という動詞の形は、医学用語よりもはるかに生々しい実感を持っているように感じられました。
自分の体について「壊れる」という動詞を使わざるを得ないとはどういうことなんだろう。それはどんな症状なのか? しかも「壊れ続ける」とは……? それがメールから受けた私の美佳さんに対する第一印象でした。モノに対して使う動詞を自分の体に対して使うということは、よっぽど体に対して距離を感じているのか? 体を「自分のもの」とは思えず、「自分とは関係なく勝手に生成変化していくもの」のようにとらえているのではないか? そんな印象を持っていました。
実際にお会いしてみて、その印象は半分は正しく、半分は間違っていました。正しかったのは、体をどこか「勝手に生成変化していくもの」ととらえていること。つまり、壊れていく体に対して、先回りしてそれが起こらないように制御しようとする介入的な意志を、美佳さんからはあまり感じなかったのです。痛みも強く、明らかに大変な症状なのですが、美佳さんにはどこか「体は体、私は私」と割り切れないものを割り切るような距離感がある。体との関わりは、もっぱら体の変化に対して、あとからそれについていくようなケア的な関係に集中していました。
間違っていたのは、だからといって、美佳さんと体との関係が疎遠ではないということでした。インタビュー時から数えて二年前に膝に人工関節を入れ、四〇年近くで初めて痛みのない生活を経験。「ああ、これが生きるってことなの?」と、痛みのない自分にびっくりしたといいます。同時に、あれもやりたい、これもやりたいという欲望がどんどん自分の中から生まれてきた。美佳さんは、体の中に生まれる感覚に対して非常に敏感です。体は体で勝手にやっていてどうしようもないけれど、その生成変化が発しているメッセージがある。それを美佳さんはつかもうとしています。そして、話の内容と不釣り合いなほど、美佳さんの表情や語り方は明るく生き生きしています。
手の届かないところにある生成変化に対して、それが意味するものを問いかけるという仕方でつきあうということ。誤解を恐れずにいえば、それは自然や世界に対して宗教がとる態度に似ています。実際、美佳さんも、「神様が、なんていうと変ですが」と断りながら、「いただいた試練」や「生かされている理由」といった言葉を使います。特定の宗教を想定したものではありませんが、左脳派を自認する美佳さんのパートナーの崇さんも、「そういうビリーフというものを、経験から立ち上げて、人間としてかなり完成に近い」と語ります。[1]
出来事の原因をもとめて因果関係の網目をたどるのではなく、それが意味するものを問いかけるというやり方で、ままならない相手を自分なりに解釈しようとする。前者が科学的身体観であるとすれば、後者は宗教的身体観です。美佳さんがこの意味での宗教的身体観にたどりついた背景には、どのような経験の蓄積があったのか。じっくり紐解いてみたいと思います。
腐っていく体
先述のとおり、美佳さんは幼いころから難病に苦しんできました。
最初の「壊れ」は手の皮膚からでした。
三、四歳の頃、手の皮膚が化膿してきて、ガーゼを当てていました。ところが、それがやがて足、お尻、肘、とよくぶつかる場所に広がっていった。化膿とは、傷口が細菌に感染して炎症を起こし、赤く腫れ、膿が出てくる状態です。皮膚が化膿すると、肉がダイレクトに空気に触れている状態になる。組織が欠損すると、「肉芽」と呼ばれるぽこっとした盛り上がりができます。するとその肉芽のまわりが緑黒っぽい色になり、周囲にも広がっていく。
美佳さんはその状況を「腐る」と表現します。「腐る」という言葉は通常は死と強く結びついているので、自分の体のうえに腐敗の進行を見るというのは、非常にショッキングな出来事です。それでもこの言葉を美佳さんに選ばせたのは、その見た目の印象に加え、症状が体をどんどん侵していく、その勢いを実感していたからでしょう。「腐っていくのが本当にあっという間で、下手すると骨が見えてきちゃうんです」。その際、化膿していく皮膚が発する匂いも、まさに腐敗臭そのものでした。
生きた体の上で進行する腐敗。当然、子供が経験するにはあまりに過酷な痛みが伴います。肉が空気に触れているので、患部が常にヒリヒリヒリヒリしていたといいます。保育園の昼寝に使う布団が、美佳さんの分だけ真っ赤になっていた。ものすごい勢いで体を侵食してくるわけのわからない症状、そしてみんなとの違いに、美佳さんはフリーズしたようになっていました。「たぶんお友だちが何か言っていたと思うんですが、私の中ではもう入らなくなっていました」。痛みから解放されるのは、お風呂に入っているときでした。患部が水に触れて潤っているあいだは痛くなかったのです。
小学校に入ってからは、腐っていく体を自分でケアすることが生活の一部になっていました。小学校二年生のときに母親が他界し、父親も仕事が忙しくいつもは頼れない状況だったのです。お風呂を出た瞬間から渇いて痛くなるので、消毒して、軟膏をぬって、ガーゼを当てて、テープで止める。この作業を、全身の患部に対してやっていました。おかげで小学生の頃の写真は、全身がガーゼだらけ。トイレも当時は和式で、おしっこをするとガーゼが濡れて、滲みて変えなくちゃいけなくなる。小さな子供が抱えるにはあまりに過酷な労苦です。
ガーゼをあてるといういわば「公式の」ケアに加えて、腐敗の広がりに対処するために独自で行なっていた非公式のケアもありました。肉芽がどんどん広がっていってしまうので、それを自分で切り取っていたのです。医学的には自分でやることは奨励されていない処置ですが、人に知られてはいけないという焦りの中で、ひとりで何とかしようとして出てきた行為だったのでしょう。「もう、本当に何やっているの、っていう感じ(笑)」。こうした非公式のケアは、ケガや病気をしたときに多くの子供達がこっそりやっているものかもしれません。でもそれが、美佳さんの場合には肉芽を切り取るというショッキングなものであることに、胸が締め付けられるような切ない気持ちになります。
未来を描けない
中学生になると、皮膚に加えて、全身の関節が炎症を起こして痛むようになります。皮膚だけのときは軟膏を塗ってガーゼをすれば痛みが落ち着いていましたが、関節に関しては何をしても痛みがおさまらず、夜も眠れなくなってしまった。肩、手首、手、ひざ、足首、足の指、すべてが真っ赤に腫れて、ジン、ジン、ジン、ジン波打つように痛い。寝返りを打っても、起き上がっても痛く、立つことができませんでした。
あまりの痛みに、子供のころは未来を考えられなかった、と美佳さんは言います。「たぶんもう早いうちに、苦しくて死ぬと思っていた」。あまりの痛みに耐えきれず、また母の死も見ていたので、長く生きられるというイメージを持てなかったのです。将来の夢を無邪気に描くという子供時代の特権を奪われた時間感覚。それを思うと、目の前が暗くなるような絶望的な気持ちになります。しかも美佳さん自身の感覚としては、時間は将来どころかほんの十日先までつながっているかどうか不確かなものでした。「一週間後や二週間後の約束もあまりしたくない感じだった」と美佳さんは言います。「中学生のときのジンジンする痛みのときは、いつも寝るときに「明日目が覚めなければいいのに」って思いながら泣き疲れて寝るという感じでした」。
その時間感覚は、当然、進路の選択にも影響します。高校を選ぶにも、勧められた高校ではなく、なるべく近い農業高校を選ぶことにしました。どうせ生きているか分からないから、とにかく近いところで、という選び方でした。大学も、福祉関係に進みましたが、仕事ができるはずないから、介護技術の実習が始まったらやめればいい、卒業できなくてもいい、と思っていた。実際には美佳さんはいま四十代に差し掛かり、それまでに仕事や出産も経験していますが、当時はそんな日が訪れるとはとても思えなかった。自殺をしようという思いは一切なかったと言いますが、死が必然で生が例外状態であるような生活を、美佳さんは送ってきました。
その間にも、体は容赦なく変化していきます。関節の炎症には変形が伴いました。最初はひざ関節の変形でしたが、大学生になると手指の関節が変形しはじめ、鉛筆を持つのに痛みを感じるように。右手の中指に人工関節を入れ、左手の中指には骨盤から骨を取って入れる手術をしました。しかし当時流行していた院内感染にかかってしまい、人工関節は抜去することに。その後ピンみたいなものを入れて外から板で固定していましたが、その状態で生活していると指の先からピンが出てきてしまう。私には「指先からピンが出てくる」というだけで背筋がぞっとするような痛みを想像してしまいますが、美佳さんは「何回も戻したりはしてたんですけど、痛いし、結局抜けちゃった」と、どこか「勝手に生成変化していく体」に困りながらついていくような距離感で説明します。
現在、右手中指はピンも入っておらず、関節もないので、柔らかい状態になっています。もともとはぷらぷらしていたのですが、次第に縮んで、お正月に食べる「ちょろぎ」のような形に。息子さんはそれをストレートに「ウンチくん」と呼ぶそうです。美佳さん自身はずっと隠してきたその指を、息子さんはぷにぷに触りながら「かわいい」と言ってくれた。一方で、「この手になりたい?」と訊くと、「なりたくない、絶対」と答える。親しい人の口から飛び出す、いわゆる「寄り添い」とは真逆のこんな発言が、かえって長年抱えてきたコンプレックスに思いがけない風穴を開けてくれたりするものです。最近では、美佳さんはSNSでも自分の体を外に発信するようになってきています。
いやあ、そう言われましても
興味深いのは、いまは寛解して人生初の痛みのない生活を送っているとはいえ、こうした病気の経験を語る美佳さんの表情が、輝いていると言いたくなるほどに明るいこと、そして説明のなかに一度も病名が出てこないことです。
インタビュー中、病名を教えてくれたのはとなりにいた崇さんでした。崇さんによれば、美佳さんの病気にはPAPA症候群という診断名がついているそうです。それは、世界に一〇〇〇人くらいしかいないめずらしい病気とのこと。その後私が個人的に調べた情報によれば、この病気は、炎症反応を調節するタンパク質の生産にかかわる遺伝子に生じた異常が原因で生じることが知られています。発症のタイミングも、美佳さんのように小児期に発症するケースが一般的のようです。
けれども、病名はおろか、こうした病気発症の医学的なメカニズムも美佳さんの口からは語られませんでした。
なぜ美佳さんは病名やその医学的メカニズムについて語らないのか。それは一言で言えば、医学や科学の枠組みをつかって自分の体を説明することに、関心や期待を持てていない、ということを意味します。
美佳さんがそのように考えるようになった原因のひとつは、美佳さんがもともと持っていた性格や指向性の影響があるでしょう。「何が起こっているんだろう」と自分の体をいぶかしりながらも、それについてすすんで何かを調べたりするタイプではなかった。三〇代で脳出血を起こして入院したときも、崇さんとは異なり、美佳さん自身は医学関係の本はまったく読んでいなかったと言います。
美佳さんのこうした傾向の背後にはしかし、もともとの性格や指向性に加えて、やはり幼い頃から重ねてきた病院通いの経験が影響しているように思います。
保育園のころから、美佳さんは父親に連れられていろいろな病院を訪れていました。青森の田舎育ちで選択肢が限られる状況でしたが、地元の病院に通うだけでなく、少し遠くの大学の先生が来る病院に入院して検査を受けたりもしていました。
ところが、どこに行っても先生は首をかしげるばかりだった。「こんな病気見たことない」「大学病院でもこんな症状はない」。できることを探すというよりも、病気そのものを否定するようなお手上げの宣言。要するに、美佳さんの体は、医学の世界の中に居場所与えられなかったのです。医師という専門家たちに自分の体を担ってもらえなかった。
そんな経験について、美佳さんが語る言葉が秀逸です。「「いやあ、そう言われましても」っていう感じだった(笑)」。預けたものが、そのまま返ってきた、という感じでしょうか。さんざん検査をしたのに、結局分からないと突き返される。困っているから頼りに行ったのに、逆に頼られても困ると言われたのでは、科学としては誠実な返答だったとしても、人間どうしのやりとりとしては完全にすれ違っています。「いやあ、そう言われましても」という美佳さんの言葉には、解決の糸口が見えないトホホ感とともに、医学に対する諦めと不信感が感じられます。
私の痛み?
すがる先もなく、思春期の美佳さんは自宅でお父さんに当たっていました。「高校まではぐちゃぐちゃで、気持ちが安定しなくて、父に毎晩当たってたんですよね。父がいつも晩酌しながら聞いていて、言ってもしょうがないんだけど、言う相手がいないから父にばっかり当たっていて」。
でもあるとき、美佳さんは、自分の苦しみを受け止めていたお父さんが、トイレに入って泣いているのを聞いてしまった。それ以来、美佳さんはお父さんに当たるのをやめたといいます。「自分も苦しいけど、大事な子供が苦しんでいるのを見るのもつらいんだって、初めて気がついて。そのときから当たるのをやめたんです。そっかあ、って」。
興味深いのは、「当たるのをやめた」ことによって、美佳さんがむしろ「明るく痛みを伝える」ようになった、ということです。それまでは、「なんで私がこんな思いしなきゃいけないの。私がなんかしたの」と理不尽な境遇に対する怒りをそのままお父さんにぶつけていた。それが、トイレの一件以降は、「いま、傷3個だよ」などと笑いながらカラッと伝えるようになった。
それは決して本心を隠すということではなかった、と美佳さんは言います。それはむしろ、体と他者、二つの点に関する見方の変化であるように思います。
美佳さんは言います。「体に関してはなるようになるという感じで、隠しているというよりは、自分の大切な人に痛みを伝えることで、その方の悲しい顔を見たくない、いまこの時間を大事にしたいという感じですね」。
一般に、痛みを経験した人の多くが口にするのは、「親しい人にこの痛みをわかってほしい」という切望、しかし結局は「自分の痛みは決して他者には分からない」という絶望です。どこまでも「私の痛み」でしかないという、痛みの私秘性とその共有不可能性。その絶対的な事実に苦しむのです。
しかし美佳さんは、トイレの一件以降、ある意味ではリアリスト的な判断から、その先のステージに進んでいきます。痛みを共有してもらうことの無意味さに目覚め、共有したいという気持ちから離れていくのです。痛みを共有してもらおうと躍起になることで相手を悲しませ、今この時間を犠牲にしてしまうのだったら、そうしないほうがいい。美佳さんは言います。「もう慣れちゃって、自分がつらいんだということを見せたところでどうしようもないというか、見せようとも思わない。『すごい痛いんだよ、分かってよ』みたいな気持ちももうない」。
それは、美佳さんに対して失礼な表現になることを承知で言えば、逆説的にも、「この痛み」が「私の痛み」でなくなるということを意味しているように思います。先の引用中の言葉を借りるなら「体に関してはなるようになる」という感じ、つまり冒頭でも指摘したような、「体は体、私は私」と割り切るような距離感。もちろん、幼い頃からの「体の壊れ」によって、想像を絶する痛みを長い間経験してきたのは美佳さんです。その事実を否定するつもりは全くないのですが、伝えようとする気持ちを失ったことで、逆説的にも、痛みが美佳さんのものではなくなっているように思います。
体は体で勝手にやっている、その生成変化を、他者と自分の関係ではなく、より大きなものと自分の関係でとらえるようになる。そこに「宗教的」と呼びたくなるような身体観が生まれています。加えてそこには、痛みに自分を語らせるのはやめよう、という美佳さんの決意があるように思います。この痛みを分かってもらわないかぎり、私について分かったことにはならない。そんな自己像で、他者と関わることをやめているのです。痛みに私を語らせるのではなく、痛みとその先にあるものに私は誰かと問いかける。言葉にするとわずかな違いですが、そこには決定的な違いがあります。
病気の人になりたくない
もう少し丁寧に考えてみましょう。
因果関係にもとづいて症状を説明する科学的身体観から、それが意味するものを問いかける宗教的身体観へ。その変化を決定づけたのは、美佳さんの「病人になりたくない」という思いでした。
それは大学生のころ。親元を離れて仙台で一人暮らしをしながら、大学に通っていました。しかし症状はまだ続いていて、二週間大学に行ったら、一ヶ月入院する、というような生活を強いられていました。大学では、友達と話したり、合唱サークルに入ったり、バンドのボーカルをやったりして楽しかった。でも傷がどんどん悪化して、勉強をしようと鉛筆を持つことで、指の骨も変形してしまう。それでキャンパスから病院に引き戻され、頻繁に入院を繰り返していました。
では入院するとどうか? 大学生活の楽しさを知っていた美佳さんは、プツンと糸が切れたように気がついてしまいます。「こんなに入院していろんな薬飲んで、ステロイド飲んで顔がパンパンになっても、治らないじゃん」。それまでは、「いやあ、そう言われましても」とは思いながらも、病院に通い、医者の指示に従って治療をしていました。でもさすがにこれは治療ではないのでは?これに何の意味があるの?と思い始めた。
「病院信用ならないな」。そう美佳さんが考えるようになった背景は、環境が与える影響の大きさに気づいたことでした。「大学にいると、病気の人という感覚がなくて、わーって楽しめているんですけど、病院にいると病気の人になる」。どのような環境にいるかによって、自分の状態は変化する。これまでずっと病気に苦しめられてきたし、現に苦しんではいるけれど、でも自分が「病気の人」にならないような環境がある。そのことに気づけたことで、美佳さんは、自分と病気を切り離して考えられるようになります。
病気に自分を語らせない。検査によって、つまり原因を探索するような仕方で、体を説明することの不毛さも感じていました。「病院で検査の結果を説明されるとか、小学校のころからいやっていうほど受けてきたんで、もういいよ、聞きたくもない、という感じでした。またそういう自分だって思いこむことで、気持ちが病気のほうに向いていっちゃう」。病院という環境が与える影響は、単なる雰囲気的なものではなく、科学的身体観にしばられること、そのことによって病にばかり意識が向くことです。
薬との付き合い方も変わっていきました。病院で処方される薬を、それまでは医師に言われたとおりに真面目に飲んでいました。その結果、体が「薬漬け」のような状態になってしまっていた。加えて、歯の形成期から医師がいろいろな薬を試してきたので、奥歯が黒くなってしまっていました。しかし、それだけの犠牲を払っても結局どれも効かなくて、むしろ悪化していく。
それが、大学生になって病院と距離をとるようになってからは、言いなりで薬を飲むのをやめるようになっていきます。自分で調整して、飲んだり飲まなかったりするようになった。関節の痛み止めだけは、痛みが出るのではないかという恐怖で手放せませんでしたが、それ以外の薬は、自分で選ぶようになった。
社会人になってからは、飲み方がもっと「適当」になったと言います。例えば、高校生のときから飲んでいた免疫抑制剤は、子供が奇形になる可能性がありました。「あ、こんなの飲んでられない」。それは、未来を考えるということでもありました。来週の約束をするのも嫌だった幼少期からすると、これはとてつもなく大きな変化です。「体をクリーンにしたくて。いっぱいいただいてくるんですけど、ごっそり捨てた(笑)」。
自分の意志で病院や薬との付き合いかたを調整することは、美佳さんにとって、心を守るためにも必要なことでした。病気に自分を語らせてしまったら、そしてそのことによって「なぜ自分だけが」という恨みに自分の生活が支配されるようなってしまったら、それは自分の心までが病気に侵されてしまったということを意味します。美佳さんは、それだけは避けたいと思っていた。「私はこういう病気だということで、病気の人というのを自分が演じるようになっちゃうんで、そうじゃないよっていうところですね。心のほうまでこの病気にやられないで生きたいなってずっと思っていたんで」。
美佳さんの存在から感じる明るさ、経験されてきた痛みの大きさと不釣り合いなほどの輝きは、まさに美佳さんが心を守り続けた結果であると言えます。「表情が悪くなってくると、自分の心もまた病気になってくる。病気の人になっちゃう。私は体が病気なだけで、心はそれにやられてないよ、そっちは自分を保とうと思って」。ふさぎこんだり、恨むような気持ちになってしまったりすることも、大いにありえたはずです。でもそのネガティブな重力に負けなかった。美佳さんが獲得した魂の高貴さのようなものに、圧倒されます。
悪い霊が取り憑いている
病気の人にならない、ということは、文字通り、いま自分が生きていることに目を向ける、ということです。
なぜ自分は病気なんだろう、と病にフォーカスしてその原因を求めるのではなく、なぜ生きているんだろう、と生に光を当ててその意味を問いかけていく。
先述のとおり、幼いころの美佳さんにとって、生のほうがむしろ例外状態でした。死なないことが不思議だった。科学的身体観から解放されたことで、美佳さんは、この「自分が死なないこと」が投げかけるメッセージを問うようになります。美佳さんは言います。「こんなに明日来なければいいと思ってるのに明日が来るというのは、生かされている理由があるんだなあと思ってましたね」。
「神様、なんていうと変ですけど」とためらいながら、美佳さんは自分の生を受動態で語ります。「生かされている」「与えられたもの」「ギフト」。興味深いのは、美佳さんが、自分の生の源泉であると感じている大きなものと関わるやり方が、「問いかけ」であることです。いま自分がこうなっていることには、何らかの理由がある。「感謝」や「畏れ」もあるかもしれませんが、それ以上に「なぜだろう」と問うことが、美佳さんが前に進む具体的な力になっています。
別の言い方をすれば、「そこには理由がある」という感覚が、美佳さんにとって、生きるという試行錯誤を可能にしているとも言えます。理由があるなら、これをやってみよう。これがだめなら、あれをやってみよう。「これ」や「あれ」を試して、その結果どうなるか見てみること自体が、ひとつの問いかけです。理由があると思えなかったら、何かを試してみるという気持ちも生まれません。
そして、この「理由がある」という感覚は、おそらく、美佳さんが子供のころに経験したことと関係があるように思います。
先述のとおり、美佳さんは青森の田舎で育ちました。青森といえば、かつてはイタコの風習があったことで知られる土地です。イタコとは女性の霊媒師で、死者の魂を自らに憑依させ、口寄せを行うとされています。
美佳さんも幼いころ、病気になり、病院に通っても原因が分からないとなると、最終的にはイタコのもとに連れていかれたり、神社で拝んでもらったりしたと言います。「青森だったので、イタコだったり、神様と呼ばれる方がいて、そういうところにいったこともあります。悪いのが憑いているみたいなことを言われて、バンバン叩かれて、むしろ痛くて(笑)」。
悪いものが憑いている。こうした「神頼み」によって病気そのものが良くなることはありませんでしたが、幼い美佳さんは、そこで告げられた自分の病の理由を、受け入れていたと言います。それはこんな物語でした。「私が住んでいる村が昔戦場で、悪い霊が私に憑いていて、みたいなことを言われて、ああそうなんだって」。
もちろんここで語られる「理由」は、のちの美佳さんがたどり着いたポジティブな「生の理由」ではなく、「病の理由」というネガティブなものです。だとしても、科学的身体観とは異なる理由の語り方が、幼いころから美佳さんのそばにあり、それに一定の納得感を覚えていた。中学生くらいまで、美佳さんはこうした語りを信じていました。
「私でよかったな」とそのとき思ったと言います。「こんなに痛い思いをして、悪い霊が誰かにつきたいんだったら、兄弟とか父とか家族じゃなくて、私が苦しめば、みんなが元気なんでしょ、みたいな感じで、小中学校くらいは思っていました」。繰り返しになりますが、このときに語られていたのは、あくまで病の理由です。だからこそ、そこで与えられた理由は自己犠牲のような物語だった。
けれども、理由があるという感覚は、因果関係をさかのぼって原因を探すのとは異なる、「意味」を求める病とのつきあい方を提示しています。そして、大人になってそれが「生の理由」を問う物語に変わったとき、その信念は美佳さんにとって、自分の体を置く居場所になっていったように思います。
自分が花みたい
そして、二年前に人工関節を入れたことで、美佳さんは人生で初めて痛みのない体を経験しました。朝起きて痛みがない、というのが本当に新鮮だった。「『こんなのいいの?』という感じで」。「『ああ、これが生きるってことなの?』って」。
「生きる意味」が問われることはしばしばありますが、「生きている意味」を問う機会はなかなかありません。人生で初めて痛みのない体を満喫し、その感覚を味わう。興味深いのは、美佳さんの問いかけは、意味を求めながらも観念的にならず、湧き上がる欲望や感情、つまり生きていることそのものに忠実だということです。「これが生きることなの?」と実感した美佳さんは、自分に起こる変化に驚きます。「あれもやりたい、これもやりたいってどんどん気持ちが出てくるんですよね」。
変形した手を含め、自分の体を見せながらSNSで発信したり、コーチングを始めたりした美佳さん。中でも、着る服を変えたことによる変化も大きかった、と言います。それまでは、血が滲みても目立たないように、黒・グレー・茶色など「ねずみ男みたいな服」ばかり着ていた。それが、紫や青など、色を着たい、アクセサリーをつけたい、と思うようになった。もちろん体へのコンプレックスは大きかったので、そうした明るい格好をすることは、最初は非常に勇気がいることでした。
でも、実際に着てみたら服によって自分の気持ちが作られることに気づいた。環境によって自分が変わるように、着ているものによっても自分は変わります。そのときの感覚を、美佳さんは「自分が花みたいだと思った」と表現します。花みたい。まさに身体の内側から、生き生きと輝く喜びが外に溢れ出てくるような素敵な表現です。「気持ちいいなあ」と思った、と美佳さん。
ポジティブ心理学の分野では持続的幸福のことを「フラーリッシュflourish」と呼びます。「花みたい」という美佳さんの言葉は、まさに自身のポテンシャルが花開き、未来に向かって繁栄していけるという人生で初めての実感をとらえたものなのではないかと思います。その光は、美佳さんだけでなくそのまわりにいる人をも照らしています。