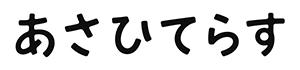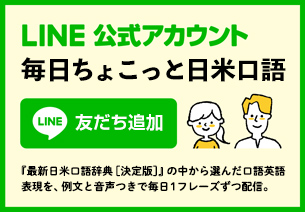第13回 言わないことを言う
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第13回は、好きなことで生活していきたい人の指南書としてベストセラーとなった本と、子どもにも大人にも人気の絵本の題名です。(編集部)
テレビCMだったろうか。タレントの高田純次が美しい女優(佐々木希だった気がする)に向かって「(自分と)似てますよね?」と真顔で尋ねた。
女優は戸惑い、周囲も「なにをいってるんですか高田さん!」みたいなムードになるが、そこにすかさず言を重ねる。
「えー、だって目が二つあってここに鼻があって口でしょ?」と指で顔のパーツを示しながら。それでどっと笑いが起きる。
これは高田純次のとぼけた言い方や間の取り方が絶妙だから笑えるのではあるが、この説明の言葉だけを、彼の個性や技術と切り離したらどうなるだろう。
笑いはなくなったとしても、ある種の感銘を残すのではないか。言われれば我々は(みんな)たしかに「似ている」のだ。
解像度を著しく下げたり、過剰にズームインしたり、単純化したり、当たり前すぎるから言わない前提を言ってみたりすることで題名が輝くという例を今回はみていきたい。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!