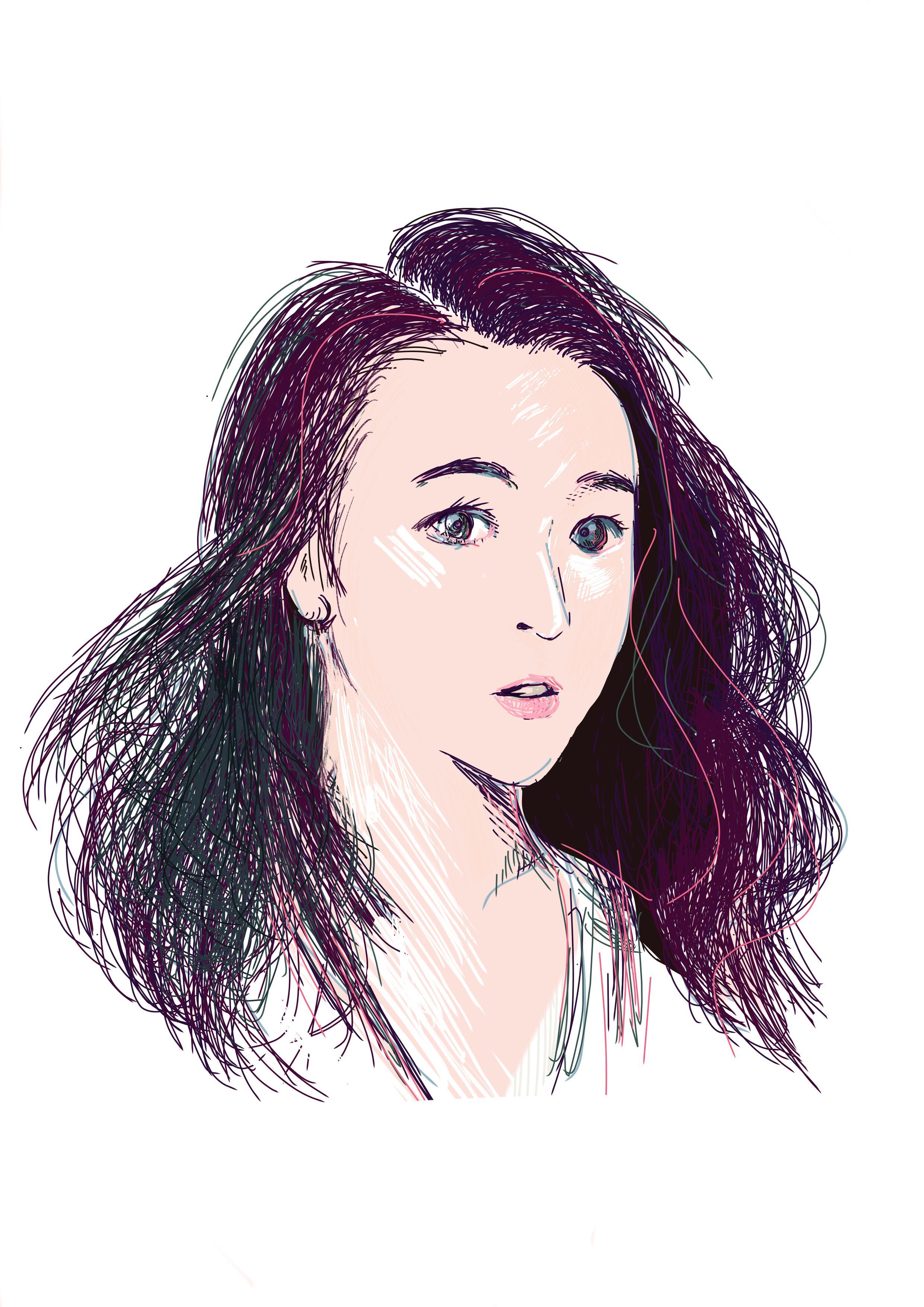韓国は詩を愛する人の多い国である。書店には必ず詩集のコーナーがあり、詩集を専一的に扱う書肆もある。駅のホームドアには詩が書いてあって、詩を眺めながら地下鉄が来るのを待つ。プレゼントとして詩集を進呈することも珍しくなく、陋巷の喧囂や熱鬧からは想像もつかぬほど、詩が身近なものとして生活の中に深く根を下ろしている。老若男女が詩集を舒巻する姿は韓国の日常的な光景であり、自ら詩作に淫する者も寡少ではない1。
一方で、日本では詩があまり読まれないという言説をよく聞覩する。たしかにそれはある程度正しい。しかし、そうした論調は、定型詩の存在を看過しているように思われる。詩には自由詩だけでなく、定型詩もあり、現代日本における短歌や俳句は、若年層をも含む一定の愛好者を擁している。俵万智や穂村弘、東直子、枡野浩一といったカリスマ的歌人の人気は衰微を知らず、彼らに次ぐ世代でも、染野太朗、永井祐、鈴木晴香、山田航、野口あや子、木下龍也、大森静佳など、数多くの優れた歌人を挙げることができる。韓国にも時調と呼ばれる伝統的な定型詩があり、現在も創作は行なわれているが、その存在感や普及の程度は日本における短歌や俳句に比較すべくもない。現代韓国について「韓国は詩の国」だと言うとき、それはどこまでも〈自由詩の国〉という意味であり、そして、その〈自由詩の国〉から日本の歌壇に颯爽と登場した新進歌人がいる。起業家、タレント、研究者としても知られる達才カン・ハンナ(康翰娜)である。
カン・ハンナは、1981年、韓国・ソウルに生まれた。10代の頃から、韓国の囲碁の全国大会で準優勝を果たしたり、数学オリンピック韓国代表に選抜されたりするなど、かなり早い段階でその異能ぶりを発揮していたようである。数学と短歌は一見交わらなそうだが、数学者の岡潔が「情緒」を重んじたことを想起すれば2、両者には相通う部分があるのかもしれない。淑明女子大学校(経営・統計学)卒業後、ニュースキャスターなどの職歴を経て、2011年に「一言も日本語を喋れない」状態で来日した。日本ではタレント活動をしながら横浜国立大学大学院に学び、今年3月に論文『韓国映画が再生産する記憶:韓国フィクション時代劇の拡大と集合的記憶の形成』で博士学位(学術)を取得。その後も、領域横断的に八面六臂の活躍を続けている。熱心な韓国語学習者には、NHKラジオ「ステップアップ ハングル講座」の出演者としても認知されているだろう3。
和歌との出合いは、新海誠監督のアニメーション映画『言の葉の庭』だったという。同作に現出する『万葉集』の〈鳴る神の少し響みてさし曇り雨も降らぬか君を留めむ〉という一首に心を打たれ、涙が止まらなかった彼女は、難解な『万葉集』を繙読し始める。詩歌を〈読むこと〉と〈詠むこと〉の間には千里の径庭があるはずだが、タレントでもあるカンは、運命に導かれるように、2014年からNHK Eテレの番組「短歌de胸キュン」にレギュラー出演する機会に恵まれ、短歌を自作することになる。そして、進境目覚ましく、「歌壇で最も権威のある新人賞」とされる角川短歌賞に3年連続で入選(2017年は次席、2016年と2018年は佳作)、2019年には第一歌集『まだまだです』を上梓し、第21回現代短歌新人賞に輝いた。本稿では『まだまだです』を繰りゆきつつ、カンの紡ぎ出す三十一文字の世界に分け入ってみたい。
『まだまだです』はカンの日常生活の断片を切り取り、その気づきや驚きを短歌という形態に圧縮させて編んだものである。押し並べて衒いのない平明な日本語が用いられており、写実的で「生活者」の視点から詠まれた歌が多い。一首一首に身辺の風景や心情の「細部」が写し出され、読者は短いことばの余白からその陰翳を延べて想像することになる。それゆえ、本書を耽読していると、いつしか彼女の日記をこっそり覗き読んでいるが如き不思議な錯覚に陥ってしまう。例えば、〈真っ暗な部屋の中からおかえりとみかん一個が静かに香る〉(p.118)、〈一枚ずつラッピングして食パンを凍らせる日は結婚がしたい〉(p.145)は、独身女性のリアルな日常の表現であり4、「生活者」としてのカンの姿が仄見える。〈持ち帰る紙袋から焼きたてのたい焼きの尾が揺れる幸せ〉(p.183)からは「小確幸」5のようなささやかな幸福感がよく伝わってきて癒される。〈らっきょうもオクラもみょうがも君に会い初めて食べた薄暑の野菜〉(p.103)と〈さわやかな苦味広がるみょうがから逢いたいと君の声が聞こえる〉(p.107)は呼応した恋の歌であろう。恋愛に関わる歌は他にも散見される。
もちろん、かかる「生活者目線」は他の歌人の作品にも広く見られるものだが6――と言ってもそのことがカンの作品の価値を些かなりとも損なうものではないことは贅言を要さない――カンのスペシフィシティ(特異性)は、やはり「外国人」「韓国人」としての「日本の生活者」という点に存すると言ってよいだろう。「外国人」という足場は、「生活者」であると同時に「観察者」としての立場性を必然的に帯び、新鮮な発見を読者にも齎してくれる。そして、それは他の追随を許さない本書の佳処でもある7。例えば、渋谷のスクランブル交差点を思わせる〈集まった人が一分で引いてゆく渋谷で見下ろす潮の満ち引き〉(p.45)や〈東京はエレベーターでも電車でも横目でモノを見る人の街〉(p.51)などに顕現している犀利な観察眼には思わず嗟嘆の声が漏れてしまう。
そうした「生活者」「観察者」としての日々は、日本に淹留しながら、日本語や日本文化に慣れ親しみ、肉迫していく道程でもある。〈浅草の「おこし」と同じ味がする「カンジョン」というソウルのお菓子〉(p.41)、〈牛丼を割り箸で食べる人々の横でスプーンくださいと言う〉(p.40)といった歌は日韓文化の同異の理会であり、〈ケータイに斉藤がいて斎藤と齋藤もいる来日六年〉(p.52)、〈日本語の「行けたら行く」は「待たないで」の意味だったのか 飴を舐めつつ〉(p.74)は日本語世界の堂奥に浸り込んでいく態様そのものである。しかし、そのプロセスが決して平坦なものでなかったことは、〈一ページ読み終えるのに一時間ルビだらけになる『日韓関係史』〉(p.20)、〈「各国」と「韓国」の音がどうしても聞き分けられぬ調子の悪い日〉(p.165)などに見える日本語との格闘や、〈ニッポンで何を超えたいのだろうか日が昇ってから本二冊閉じ〉(p.37)、〈がら空きの座席ですすり泣いててもバスは止まらず東京にひとり〉(p.100)などから察しうる精神的な煩懊によって分明である。
日韓関係を軫念する歌も多い。例えば、〈読み終えた『異文化理解』の中からは見つけられない日韓の距離〉(p.62)、〈韓国と日本の距離が十センチさらに隔たるニュース眺める〉(p.78)などがそれである。〈「に」を打つと自動変換の「日韓」が初めに出てくる人生を選る〉(p.110)という作品があるほど、カンは日韓関係について常に考思している人であり、歌集のあとがきでは「最近はさらに日本と韓国の関係が悪化していることが切ないです。できれば私自身も日本と韓国の間の架け橋になれたらと心から思いながらも、一番難しい国同士であることを実感しています」(pp.205-206)と真情を吐露している。その上で「それでも私が短歌を詠い続けてゆきたいと思う理由は、両国を想う純粋な私の気持ちが一番伝わる場所だと信じているからです」(p.206)と、自身が短歌を詠む根拠を表白する。この意味において、本歌集は日韓の〈津梁の書〉であり、文学の力でその断裂を埋めんとするカンの果断な挑戦に私は胸が熱くなる。
日韓と言えば、カンの短歌の外形的な特徴として、しばしば日本語に韓国語が混在する点も挙げられる。〈マグカップ両手で持って飲むわれにイルボニンぽいと友がまた言う〉(p.112)、〈そよそよと風が吹くようソウルでもサルランサルラン風は吹くだろう〉(p.199)といった歌である。「イルボニン」は《日本人》、「サルランサルラン」は《そよそよ》の意の韓国語であり、日本語の短歌に韓国語を埋め込むというのは新たな文学的企図だろうが、文学以前に、日韓両言語を知る者にとって、日本語と韓国語が混淆するのはごく自然な言語生活のありようである。日韓の狭間に生きるそうした「生活者」の日常がそのまま反映されたのが、如上の作品だと言えよう。そして、「あいだ」を住処とすることで、〈韓国と日本どっちが好きですか聞きくるあなたが好きだと答える〉(p.43)という秀逸な短歌が生まれてくる。大体「日」か「韓」かという、粗笨な選択を迫ること自体が詮無きことだが、日頃否応なしに「韓国人」であることを意識させられているに違いない「日本の生活者」の、軽忽な問いに対する「あなた=個」が好きだという応答は見事と言うほかなく、そこには超脱した清々しささえ感取される。
さらに、本書を読み解く上で重要なのは、「女性」という鍵語である。カンの短歌には「母」が頻現する。「異国の生活者」であるがゆえに生じる母との物理的距離は、母への思慕をより強くし、同時に離れて暮らすことの申し訳なさも自ずと生む。〈猫舌と知りながら母は熱々のコーヒーを出した旅立ちの朝〉(p.13)、〈「誰よりも優しく賢く産んだのに寂しくさせる子」母がまた言う〉(p.25)、〈東京で母の香りがふいに舞い電話をすれば香り強まる〉(p.199)など、母に触れた作品は枚挙に遑がない。一般的に言って、「母―娘」という女性同士の関係性は、「父―娘」間の感情とは明らかに異なり、また「母―息子」のそれとも微妙に異なるだろう。中でも印象的だったのは、〈「三人目も娘を産んでごめんなさい」若き日の母は言ったんだろう〉(p.93)という歌である。「言ったんだろう」という過去推量形で母を女性として一歩引いた視角から眼差すとともに、その娘が自分であることの哀切さを表わしている。「男児選好思想」が根深く残る韓国社会を表徴した秀作だと判じてよい。これに続く一首〈娘など家を継げない他人だと言ってた祖母も誰かの娘〉(p.94)は家父長制的イデオロギーへの批判であり、「祖母―母―娘」という女性三代の分厚い時間性が感ぜられる。これは『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ)や『シソンから、』(チョン・セラン)など、最近の韓国文学とも通底したテーマである。〈「アラサーは卵子凍結がいいんだよ」それ以上でも以下でもないが〉(p.98)などといった歌もあって、「女性としての生活者」という側面が頻回に露頭を現す。
上来述べ来ったように、『まだまだです』は、日本を暮らしの場とする「韓国人女性」が「生活者」「観察者」としての視座に徹して、その日常を繊細に描き切った快作である。一身にして「二生」(福澤諭吉)どころか、「四生」も「五生」も経るカンの第二歌集を鶴首しつつ、本書の中で私が最も好きな短歌を引いて、拙文を閉じたいと思う。
〈ソウルより一時間早く日が落ちる時差のない街まぶしい夕焼け〉(p.83)
本来日韓の間には時差があるが、歴史的な事由により、時刻が統一された状態になっているのは周知の事実であろう。一見同じようで絶妙に異なる両国の文化がこの「一時間」という語には籠められているように思料される。「まぶしい夕焼け」という抒情的な描写は、日韓の明るい未来への希望を湛えており、いつまでも心に揺曳する作品である。他にも紹介したい歌はあまたあるが、歌集所収の短歌という性質上、これ以上具体的に言及することは差し控える。ぜひ実際に『まだまだです』を手にとって一首一首を翫味されることを慫慂したい。
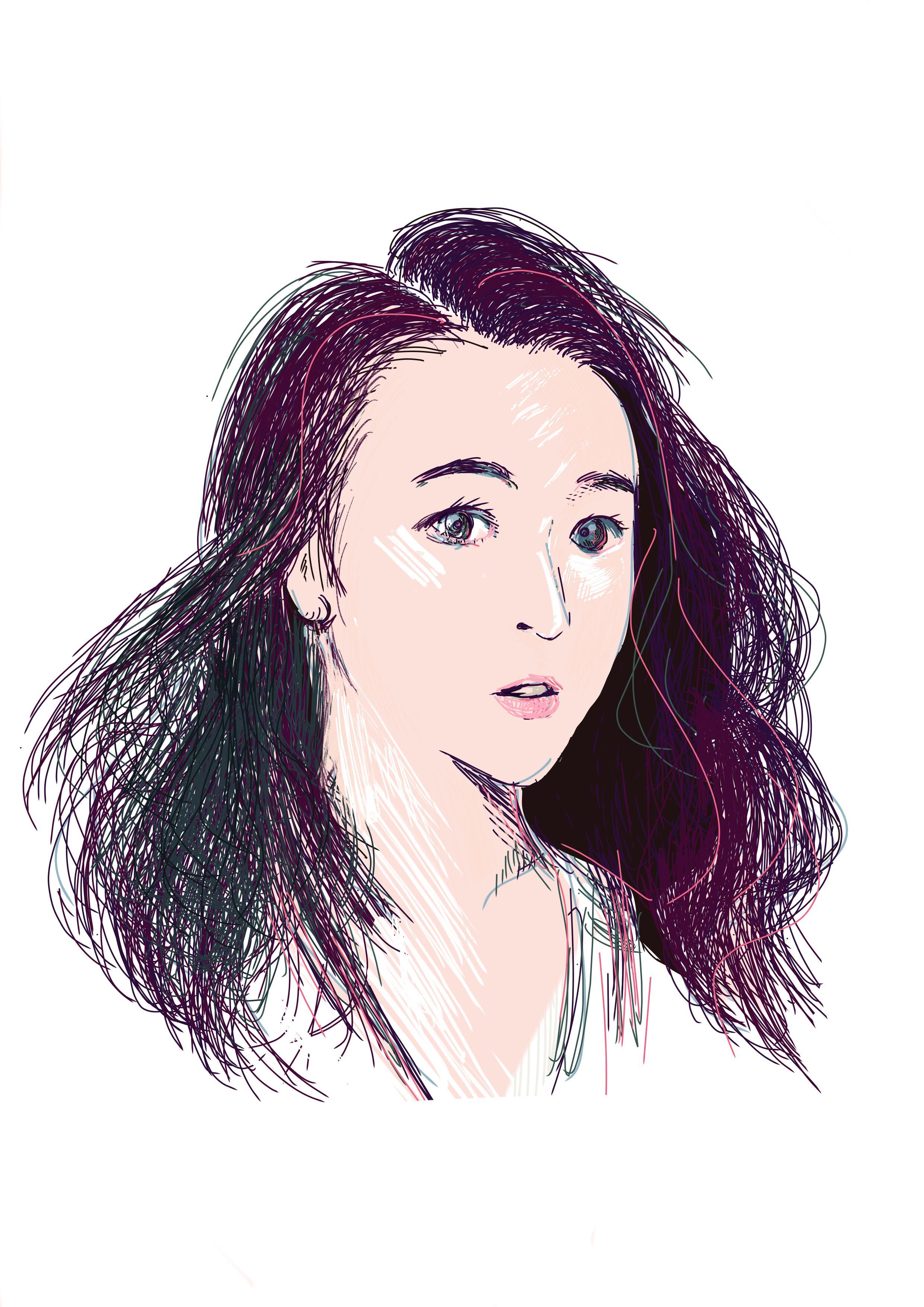
・書誌情報
『歌集 まだまだです』、カン・ハンナ著、KADOKAWA、2019年
・注
1 本パラグラフの内容は、以前「東洋経済オンライン」掲載の拙文「日本人が知らない現代韓国に根づく「ある文化」 駅のホームからプレゼントまで――驚きの背景」(2022年10月22日)でも述べたことである:https://toyokeizai.net/articles/-/625588
2 岡潔(1969;2014)『春宵十話』、角川学芸出版
3「八田とハンナのハングルメ・チャンネル」(講師:八田靖史、2022年10月~12月)。「ハンナのハングル短歌」というコーナーも。なお、その20年前の2002年のNHKテレビ「안녕하십니까? ハングル講座」(講師:小倉紀藏)では俳人の黛まどかが生徒役として出演し、「恋するハングル俳句」というコーナーがあったことを懐かしく思い出す。併せて、兼若逸之の「ハングル俳句」の試みも想起する。
4 なお、今年6月には日本人男性と結婚されたとのこと。
5 村上春樹の造語。「小さいが確かな幸せ」の意。
6 例えば、写実的で生活密着的な歌風は、正岡子規を鼻祖とするアララギ派の特徴であり、近代短歌の伝統的なひとつの潮流を成す。現代短歌においても、技巧に走らず、ストレートな表現を大切にする歌人は多い。
7 結社に所属していないことも、〈外部〉からのカンの自由な表現を保証しているのかもしれない。
Illustration: Maiko Suzuki