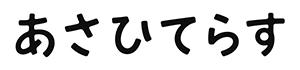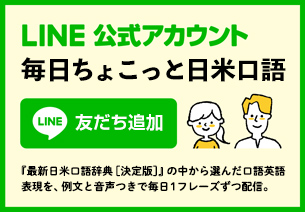第10回 題を付け続ける
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第10回に取り上げるのは、歴代の劇場版『名探偵コナン』の副題と、長年読み継がれているコナン・ドイルのデビュー作、デビュー45周年を迎えた今も活動を続けるアイドルの曲、気鋭の新世代歌人のエッセイ集の題名です。(編集部)
料理を作る人は、それ自体の労以上に「今日なににするか決める」ことの辛さを吐露する。筆者も料理をするようになって痛感している。自分だけの食事ならともかく、複数人の料理を毎日考えるときは大変だ。子供の給食のメニューを月に一度みて、昼の給食と夜ご飯をかぶらないようにしているが、みるたびに感心してしまう。毎日、違う品を予定しているということそれ自体に。題名もだ。今回は題を「付け続ける」ことの難しさと、続けていることからみえてくるものとあるはずだ、という話。
劇場版『名探偵コナン』の副題を考察する
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』
常々思うのだが、『名探偵コナン』の映画の副題は「次」を予想できるんじゃないか。
|
No. |
副題 | 公開年 | ||||
| 1 | 時計じかけの摩天楼 | 1997 | 15 | 沈黙の15分(クオーター) | 2011 | |
| 2 | 14番目の標的(ターゲット) | 1998 | 16 | 11人目のストライカー | 2012 | |
| 3 | 世紀末の魔術師 | 1999 | 17 | 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 2013 | |
| 4 | 瞳の中の暗殺者 | 2000 | 18 | 異次元の狙撃手(スナイパー) | 2014 | |
| 5 | 天国へのカウントダウン | 2001 | 19 | 業火の向日葵 | 2015 | |
| 6 | ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 2002 | 20 | 純黒の悪夢(ナイトメア) | 2016 | |
| 7 | 迷宮の十字路(クロスロード) | 2003 | 21 | から紅の恋歌(ラブレター) | 2017 | |
| 8 | 銀翼の奇術師(マジシャン) | 2004 | 22 | ゼロの執行人 | 2018 | |
| 9 | 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 2005 | 23 | 紺青の拳(フィスト) | 2019 | |
| 10 | 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 2006 | 24 | 緋色の弾丸 | 2021 | |
| 11 | 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 2007 | 25 | ハロウィンの花嫁 | 2022 | |
| 12 | 戦慄の楽譜(フルスコア) | 2008 | 26 | 黒鉄の魚影(サブマリン) | 2023 | |
| 13 | 漆黒の追跡者(チェイサー) | 2009 | 27 | 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 2024 | |
| 14 | 天空の難破船(ロスト・シップ) | 2010 | 28 | 隻眼の残像(フラッシュバック) | 2025 |
(総集編などを除く)
……こうしてみると多いな。さすが人気シリーズ!
なにしろ大ヒットしているので、ファンならずとも、どの題にもどこか馴染みがあるのではないか。観て知っているわけでなくても、なんつうか「コナンの映画の題名ぽさ」を感じ取るはずだ。副題同士に共通点がいくつもあるからだ(それで、共通項を抑えつつ、これまで使われたモチーフや手法を避けていくと、次の副題が絞り込める気がするのである)。共通点をみてみよう。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!