冷やかし/みみずく書房
文・イラスト すずきたけし
ページを指で滑らす。紙が互いに擦れる乾いた音が店内を漂う。指に弾かれた紙がページに収まる音の大きさが店内の静けさを深め、戻される本が書棚をノックする。
自らも静けさの音色に加わるように私はレジでページをめくっていた。ささやかな静けさを保って立ち読みをしている客がこのまま本を読み続けてレジに誰も来なければいいのにと思い、わずかに自省の笑みがこぼれた。
とんっ、とレジのカウンターに本が置かれた音で私は読んでいた本から顔を上げた。「それ、まだ読んでるの?」と私の手元を覗き込んできたのは木崎さんだった。彼女は近所では有名な有閑マダムで、聞くところによると近所にあるマンションのオーナーであるらしい。いつも昼食後に愛犬アリスの散歩のついでに店にやってくる。「あ、どうも」自省の笑みを見られたかもと慌てた返事をしながら木崎さんが置いた本を両手で受け取った。
「面白いの、それ?」と木崎さんは目で私の手元の本を指し示した。「親子の物語なんですけどくノ一がでてきたり、マフィアがでてきたりしてメチャクチャですね」と苦笑いして見せた。「バイン・・・なんとかだっけ」と彼女はたどたどしく声に出して「満州生まれの私には縁がなさそうな本ね」と笑いながら言葉をつないだ。彼女は満州生まれが口癖だ。そして「死ぬまでに読みたい本がいっぱいあるから余計な本を教えないで」といつも言う。
「『ヴァインランド』です。この店を始めてからこの作家の本を年1作ずつ読むのを続けているんですよ」と本を持ち上げて表紙を彼女に向けた。「へぇ、いま何冊目なの?」「3冊目です」「あと何作残ってるの?」「5作です」
「いつ死ぬかわからない私はそんな読み方できないわよ」と意地悪に笑った。私もつられて意地悪に「木崎さんならこれから『失われた時を求めて』を読み始めても大丈夫ですよ」と言うと「プルーストは昔に挑戦したけどダメだったわ」と彼女は眉をひそめた。あ、と思い出した私はレジから離れ書棚から『ファンホーム』というグラフィックノベルを持ってきた。「これ、アメリカの漫画なんですけど、この中で“『失われた時を求めて』を読むことはないと気づいた時に中年になるそうだ”って言葉が出てくるんですよ」と本を渡した。「アタシはもう中年どころか後期高齢者よ」と言ってページをめくる彼女に「同性愛の父と娘が文学を通して交流していく話なんですけどとても良かったですよ」と言うと「面白そうね。じゃあ、それと一緒にもらっていくわ」と『ファン・ホーム』を私に差し出した。
もう一冊は宮下奈都の『羊と鋼の森』だった。「昨日本屋大賞に選ばれたってテレビで見たのよ、そしたら読みたくなるのよねぇ」と笑った。木崎さんは文学賞の受賞作を中心に読書を楽しんでいる。以前にはある文学賞を受賞した小説を読み終わった直後に店に駆けつけてきて「これ最高よ!」と私にその小説の素晴らしさを1時間以上も聞かせてくれた。感想も終わり一息ついた木崎さんに私はその小説が受賞した選評が掲載された雑誌を紹介した。すると選考者の一人の酷評に目が止まった木崎さんはそれから1時間をその酷評した人がいかにこの作品を理解してないのかを語り続けたことがあった。
2冊にカバーを掛けて木崎さんに渡すと、わざとらしく背伸びをして店の外のガードレールに繋がれたアリスを窓越しに覗いた。私につられて木崎さんも窓の外を覗くと、それまで大人しくしていたアリスが外から窓越しの飼い主に気づき、機敏に後ろ足で立ち上がってこちらに向かって前足を上下に振り出した。「あ、じゃ、またね」と挨拶をして店から出た木崎さんの「さあアリスちゃん帰りましょう……」の声が入口のドアが閉まるのに合わせて小さく消えていった。
再び戻った静寂を店内に押し広げるように私は手元の『ヴァインランド』のページをめくり始めた。
100ページほど読み進めてふと我に帰り、顔をあげると店内に客はいなくなっていた。また自省の笑いを吐き出すと一人の男性が入店してきた。
スーツに中折れ帽をかぶった年配の男性で、背筋が伸びて整った姿勢はとても若々しい雰囲気だ。男性は私を一瞥してレジの前を通り店内の奥へと歩を進めた。その一瞥が少々気になった私は手元の本に頭を傾けながらも男性を視野に入れていた。
男性は本を手にとることもなく、書棚に目をやりながら店内をぐるりと歩いてこちらに戻ってきた。
「アンタに聞いてもわからないかなぁ」と男性は言いながらレジのカウンターに左の肘を乗せた。「文芸専門書店と聞いて来たけど、私が若いころ熱中した本がしっかりと置いてあって感心したよ。いや素晴らしい」と言って笑った。私はありがとうございますと頭を下げた。「いろいろ聞いてみたいことがあるんだけど店長さんはいらっしゃる?」と言うので私が店主であることを言うと「あ、アナタが店長なの? へえ」と丸くした目を私の手元に移した。「ほおピンチョンですね。『ヴァインランド』ですか?」私はわざと気のない返事をした。「たいしたもんだ。けどピンチョンなら『重力の虹』がいいですよ。おすすめです」
男性の態度にイラっとした私は音を立ててページを閉じて「お聞きしたいことというのはなんでしょうか」と笑顔で応えた。「店長さんから私になにか本をおすすめしてほしいと思って来てみたのですよ。文芸専門と聞いて私と同年代くらいの店長さんかと思ったらアナタのような……お若い方だったので」
「それなら」と私はレジカウンターのイスから立あがり、店の奥から一冊の本を手に取り男性のもとへ戻った。私と向かい合った男性は同じ身長である私にまた目を丸くしたが、気づかれないようにしたのか手にとった本に目を下げた。「極北……ですか」男性は書名を口に出してページをめくった。「ご存知ですか?」と私が言うと「いやこれは読んだことはありませんね」とページをペラペラとめくり続けた。
「文明が終わろうとしている近未来のシベリアが舞台なんですが、そこで暮らす主人公に強く惹かれる小説なんですよ」と私はレジカウンターに戻りながら言った。男性は「SFですか」と鼻で笑った。「ピンチョンを読まれていたのでお嫌いではないかと思ったのですが」というと「いえ、アナタがSFを読まれるとは思ってもみなかったので」といって男性はこちらを向いて口角を上げた。「世界観が近未来というだけで、そこまでSF色が強い小説でもないのですが、お客様には是非最後まで読んで欲しいと思った本です」“最後まで”という部分を少し強めて言った私は男性の反応を待った。
「なるほど」と言って男性は開いていた『極北』を閉じて私に差し出した。そして「また次来た時にでも買いますよ」と言って男性は店から出て行った。たぶん次はないかなあと軽い徒労感を振り払い、気分転換に外の自販機でお茶でも買おうと私は店を出た。
すでに日が傾いてオレンジ色に染まった歩道で背伸びをすると「お疲れさま」と木崎さんがアリスと一緒に後ろに立っていた。「休憩?」と言った木崎さんは買い物袋を手にサンバイザーにサングラスをかけ、アリスとともに西日を浴びて光り輝いていた。私はその姿がおかしくて笑いだした。「そんなところです」と言って木崎さんとアリスに目をやった。アリスは後ろ足で立ち、私に向かって前足を揃えて上下に振り出した。手を差し出すとアリスは前足で私の腕ごと掴んで嬉しそうに舐めだした。
「そういえばアリスの名前は『不思議の国のアリス』からですか」とアリスの舌触りを感じながら聞いた。「いや違うのよ、主人が有栖川有栖の小説が大好きだったのよ。それで主人が亡くなってからウチにきたアリスちゃんに私が名前をつけたの」
10年以上前に亡くなったご主人は大変なミステリファンだったと木崎さんはよく話してくれた。「ということはアリスちゃんはオスだったんですか」と言うと「え、有栖川有栖って男なの?」と木崎さんの表情が固まった。「はい。男ですよ」固まったままの木崎さんは「やっぱり『不思議の国のアリス』を名付けの由来にするわ」と言って笑いだしてアリスの頭を撫でた。アリスは気持ちよさそうに木崎さんの手のひらに自分から頭を擦り付けてきた。
「女3人、仲良くしましょうね~」と木崎さんはアリスに向かって言った。
私も笑いながら「本当に可愛いですね。何歳になるんですか?」と聞いた。
「え、今年で80よ。あら、アタシ言わなかった?」
私はまた笑った。木崎さんも気づいて笑いだした。
声を出して笑う私たち3人に道行く人たちは視線を投げて静かに過ぎていく。
夕日の眩しさに目を細めながら、私たちはしばらく笑い続けた。
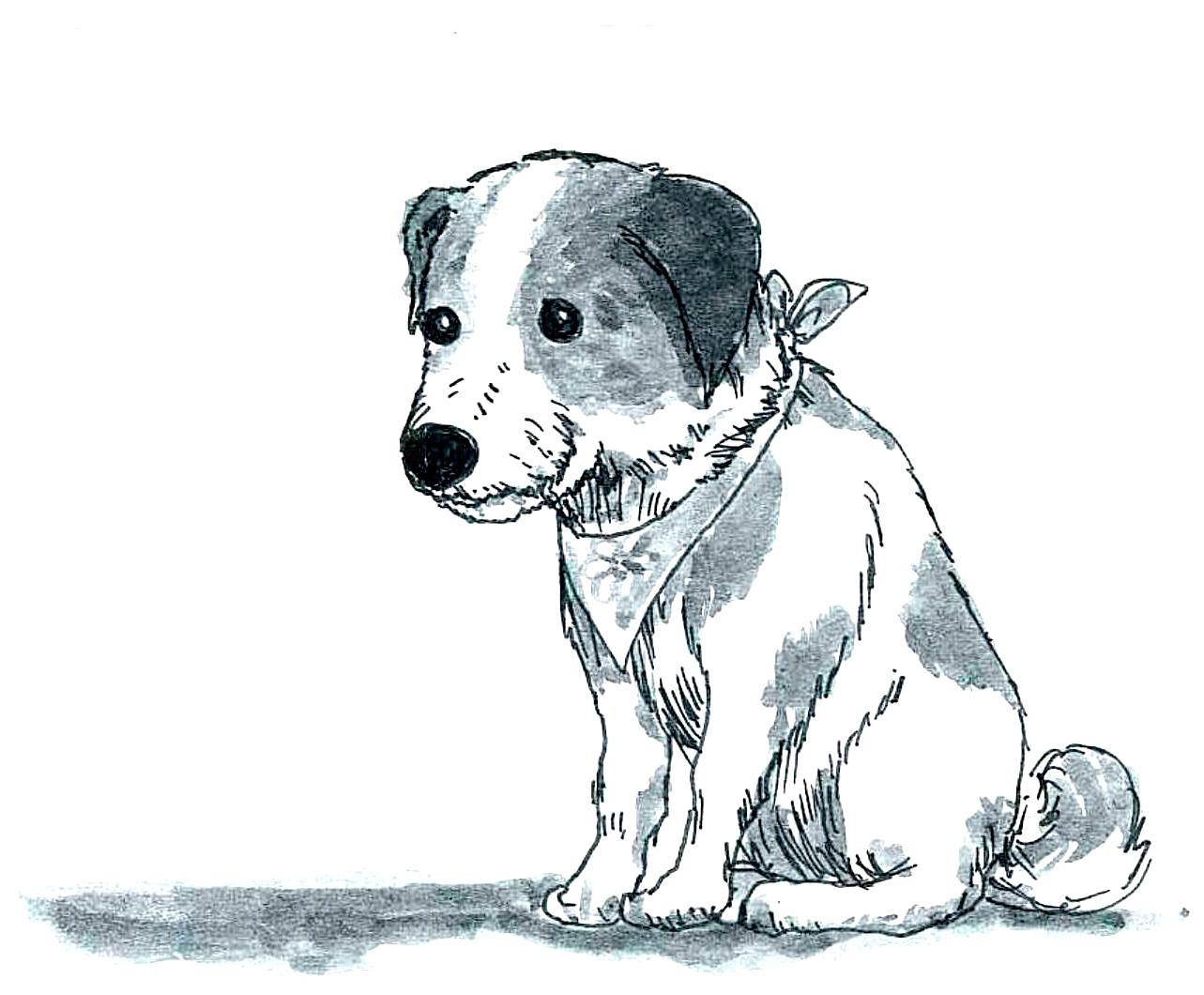
※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。




