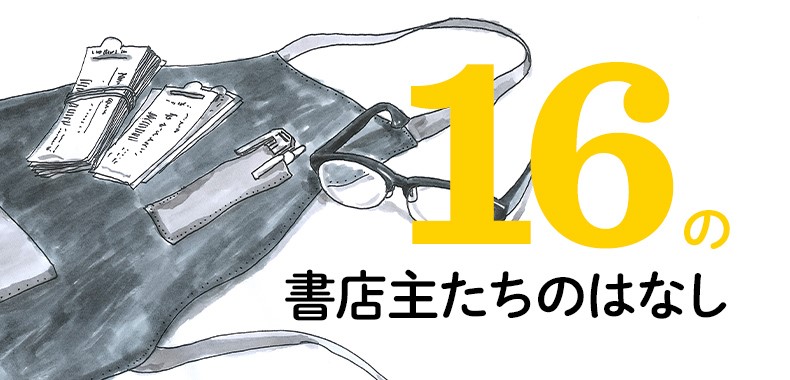郵便ポスト/タンチョウ書店
文・イラスト すずきたけし
「はい。ありがとうございます。では16時にお伺いいたします。お忙しいなかありがとうございます。はい。いえいえ、とんでもございません。はい。よろしくお願いいたします。はい。では、失礼いたします……」
先方が電話を切るのを待ってから携帯電話を胸ポケットに入れ、営業車から降りた。駐車帯から車のキャラクターが携帯電話で話しているイラストの標識を眺めながら、両腕を頭において背中を伸ばした。雲ひとつない青空の下一面に田植えの終わった田んぼが広がり、真ん中を灰色の国道が真直ぐに伸びている。田んぼ。田んぼ。国道。田んぼ。田んぼ。見渡す限りの田んぼだらけ。「ホントなんにもねえなぁここは」と20年ぶりに訪れた故郷へあてつけるように声に出した。
車に乗り込み、エンジンをかけると田んぼばかりの静かな国道へ車を滑り込ませた。
運転席の窓を開けるとまだ乾いた初夏の風が気持ち良く、営業先のアポの時間が延びたことで少し気持ちが軽くなった。
カーラジオのチャンネルを地元のFMラジオ局に切り替えた。男性グループがなにやらラップで歌っている。普段はめったに聞くことのないラジオだが、こうして遠方で営業車を使う時は運転中の暇つぶしにラジオを聞く。いまでは音楽を聞く時間も少なくなり、流行りの歌も耳にひっかからないまま流れ過ぎてゆく。そんななか、営業車の運転中が音楽に耳を傾ける数少ない時間になった。男性アイドルグループの歌が終わるとDJの女性が「『お静かに』ってプラカードが上がると観客が一斉にシーンって黙るんですよ~!」と地元のどこかで行われたプロゴルフの大会を観に行ってきたという他愛のない話をしていたが、またいつの間にか次の新しい歌が流れていた。
歌が終わると地元のカメラチェーンの屋号を連呼するCMが唐突に始まり「頑張ってるねぇ」と車の窓の外へと独り言を吐き出した。CMが明けると「ほんとに本でしょう!」と先ほどの女性DJがコーナータイトルを快活に叫んだ。どうやら本屋の店員が毎月オススメの1冊を紹介するコーナーらしい。地元の本屋もそういうことやるようになったのかと「頑張ってるねぇ」とまた外へ独り言を言った。「どうもこんにちは~!」と登場した本屋の店員は挨拶のあとも最近の話題を面白おかしく話し出した。ゴルフの大会の話よりよっぽど面白い。感心していると、いつの間にか本の解説に入っていた。時代小説らしく、いがみ合っている隣の藩同士がなにものかに襲われるという話らしい。「なにか得体の知れないモノだからこその恐ろしさがハンパないんですよ!」と店員は紹介を締めくくった。「わたしこれは絶対読買いに行きます!」とDJが締めの言葉に入った。「……ということで、みなさんも週末に読書はいかがでしょうか。せーの……」
「ほんとに本でしょう!」とDJと店員が二人で締めの言葉を叫んでコーナーが終わった。
運転しながらなぜか少し恥ずかしい気持ちになったが、そういえば本の題名を聞き逃していた。本屋に行けばあるものだろうか。
昔に住んでいた地区に小さな本屋があったことを思い出した。
20年前は田んぼしかなく、存在していなかった国道バイパスを10分ほど走ると見覚えのある旧道へと合流した。毎日学校へと歩いていた通学路だった。ふたクラスしかなかった小学校で5年生が終わると両親とともに東京へ引っ越した。中学校からでは友達が作りづらいだろうという両親の配慮だったが、東京で1年だけ過ごした小学校の卒業アルバムは何度開いても他人に見せられたそれと同じにしか見えなかった。
この場所で過ごした記憶もいまや断片しかない。それだけの記憶でここが自分の故郷と言えるのかわからない。けれども割れた鏡の破片に映り込む景色のように、いまに至るまで記憶は繰り返し頭に浮かんできた。
アクセルを緩めた。夏休み、学校のプールへ行った帰りに自由に水を飲ませてくれる小さな自転車屋があった。店の外にある水道には、昔テレビで放送していた人形劇のキャラクターがプリントされた黄色いプラスチックのマグカップが置いてあり、夏の日の下校途中は皆そこで水分を補給した。とても暑い日には黄色い通学帽に水道水を溜めて頭から水ごとかぶって友達とはしゃいでいたが、自宅に着くころには帽子も服もほとんど乾いていた。
自転車屋はまだあった。建物だけは。店のガラスは割れていて廃屋になっていた。外の水道の前には錆びた自転車が立てかけてあった。黄色いマグカップに目を凝らしたがそれはやはりなかった。
建物が残っているだけで嬉しくて思わず笑い出し、この先にある何度も渡った踏切を思い出した。踏切手前で一時停止をして、ゆっくりと踏切を横断する。運転席から下の線路をのぞいた。テレビで見たのを真似してか、皆で線路に耳を当てて電車が近づいているかを予想しあった。後日、だれかが学校に連絡が入れ、なぜか自分たちであったことまで知られていて担任の先生にこっぴどく怒られた。「懐かしい」と声が漏れた。
そのまま車を走らせると道路は雑木林の中に入っていく。昔と変わらず木々が生い繁り、昼というのに暗い。日が短い冬の夕暮れには電灯もないこの道は暗闇が恐ろしく、皆で走って通り抜けていた。車ではあっという間だった。100mにも満たなかった。あの頃はとても長く感じたこの道をたった数秒で通り抜けた。
雑木林を抜けて細い道へと左折して、昔住んでいた家があった地区に入った。田畑に沿って続く道から今度はまた一段と狭い道へと左折する。車一台分の路地を恐る恐る車を進めた。そこは道路に白チョークで線を引いて近所の子供たちでドッジボールをやった道だ。こんな狭かったことにいまさらながら驚く。しかし周囲の家々は目新しく記憶の景色とは程遠い。そのまま車を進めると三浦くんの家が見えてくるはずだった。小学校3年生の時に転校してきた三浦くんの家に初めて遊びに行った時には玄関に出てきたお父さんから「こんにちはは?」「お邪魔しますは?」と挨拶の仕方を注意された。その時以来、三浦くんの家で遊ぶことはなかった。そんな三浦くんの家はなくなっていた。代わりに目新しいアパートがあった。記憶の景色とは遠くかけ離れたその場所を車の窓から見て気持ちが早まる。その先には自分がかつて住んでいた平屋の家があったはずだ。しかしそこもまた新しいアパートが建っていた。昔の名残がないか探そうと思うものの、なぜかこの場所からすぐに抜け出したくなり、そのまま来た道へと引き返した。カーラジオのスイッチを切り、大きなため息を吐き出した。昔住んでいた家がすでに存在していないという、ありきたりで当たり前のことに自分が落ち込んでいることに驚いた。自分がここで暮らしていた証拠が跡形もなく消えてしまった。車の外の景色が、打って変わって知らない土地に来たように思えた。
小さな本屋もなくなっていた。毎月『コロコロコミック』を買いに走って行った本屋だった。床に座りこみ漫画を読みまくった。あの本屋が消え、代わりに大きな本屋になっていた。営業車で国道を走らせるとよく見かけるDVDレンタルと本屋が合わさった全国チェーンだ。昔の道路が拡張され、大きなスーパーと隣あわせになっている。本屋の駐車場に車を停め、さきほどラジオから聞こえていた本でも探そうと店内に入った。右手にはCDやゲームが並ぶ中、左手に本屋のスペースがあった。そのままレジカウンターの前を通り過ぎ本の棚の前をウロウロする。久々に入った本屋に戸惑った。そういえばあの本が文庫だったのか単行本だったのかも聞いていなかった。本棚の前でまたため息をつくと、「旅行ガイド」というサインが見えた。目当ての本を探すのを諦めてこの地元のグルメガイドでも買おうかと旅行コーナーの前に立った。
そこには「郷土本」というコーナーが作られ、この地区周辺の史跡が掲載されている本がまとめられていた。この近くにある古墳には、小学校の時にクラスで見学に行ったことを覚えている。顔を上げると壁面にはこの地区の地図が貼られ、たくさんの史跡や見どころが手書きの可愛いイラスト付きで紹介されていた。自分が住んでいた地区に目をやると神社が描かれていた。日露戦争で戦った将軍が必勝祈願でお詣りに来たという。「へえ」なんて声を出して顔を下げると、その神社が「掲載されています」とコメントが書いてある本が下に置いてあった。その本を手に取りページもめくらずレジカウンターへ向かった。レジの女性は同い年くらいだったので、もしかすると見覚えがないかジロジロと顔を見てしまった。「1,944円でございます」と顔を上げた女性と目が合うが見覚えがなかった。千円札2枚を出して、今度は女性の名札を見た。これまた「鶴田」という聞き覚えのない名前だった。
店を後にすると先ほどの神社に向かった。神社はここからすぐ近くにある中学校の先にあった。引っ越しをしなければ通うはずだった中学校だ。この中学校の秋の文化祭は子供にとっては大きな楽しみだった。文化祭の恒例だった仮装行列は生徒がダンボールや廃品で作った衣装を身につけて校庭を練り歩く。しかし子供たちのお目当てはそれではなかった。仮装で使われた衣装や小道具は後夜祭で盛大に燃やすために、仮装行列が終了すると校庭の一箇所に集められた。待ち構えていた子供たちはそこからダンボールで作られたロボットの衣装や怪獣の被り物を持ち出して遊びまわった。
仮装行列は今もやっているのだろうか。あの頃と変わらぬ校庭と校舎の景色を車から緑色のフェンス越しに眺めた。中学校の隣には駄菓子屋があった。その駄菓子屋には近所の小学生が毎日のように集まっていた。たった100円を握りしめては通ったあの駄菓子屋に近づくと、タバコと飲料水の自販機5台が一列に並んでいる空き地になっていた。自販機の前に車を停めた。車を降りて自販機の前を端から端へとゆっくりと歩いてみた。10歩。ほんとうに小さな駄菓子屋だったと実感する。飲んで瓶を返すと10円戻ってきた瓶コーラの自販機が置いてあった場所、テーブル型のビデオゲームが置いてあった場所、自販機の前を歩きながら思い出す。その先に車から見えた丸型の古い郵便ポストがあった。あの頃と同じポストだった。目を凝らしポストの脇に目をやった。そこに目当てのものが残っていた。手の形をした模様。そっとその形に自分の手を合わせた。あの頃は自分の手よりも大きかったその手形もいまでは自分の手で隠れてしまう。駄菓子屋がまだあった頃、このポストの脇には「新幹線」というとても古いゲームがあった。投入した10円玉を脇についているレバーで弾いて東京から名古屋、大阪と運んでいき、ゴールの博多までいくとアタリ券がもらえるゲームだった。アナログなゲームだったが、子供たちは何度も挑戦するもののゴールまで辿り着けず、ハズレのポケットに10円玉が吸い込まれていった。ある日このゲームでゴールの博多の一歩手前まで辿り着いた。友達や近所の子供たちが周りで見守る中、緊張感をほぐすためだったのか思いついたように「アタリますように!」と大声でこのポストの手形にタッチをした。そうして弾いた10円玉は見事に当たりのポケットに吸い込まれ、100円分のアタリ券を獲得した。
大きく息を吐きだすと自販機で缶コーヒーを買って車に戻った。エンジンをかけてラジオのスイッチを入れた。なぜかうるさく感じたので音量のつまみを回して音を消し、缶コーヒーの蓋を開けて喉へと流し込もうと顔を上げるとバックミラーに黄色い帽子をかぶった小学生たちが見えた。「え、もうそんな時間か」と腕時計を見るとアポの16時まであと20分を切っていた。これは間に合わない。急いで胸ポケットから携帯電話を取り出して先方へと電話をかけた。呼び出し音が鳴り続けた。1回、2回、3回。先方が電話を取るとすかさず名乗り、「本当に申し訳ございません!」と謝り続けた。3回目の「申し訳ございません」の時だった。バックミラーに映った黄色い帽子をかぶった男の子二人と女の子の三人が車の脇を駆けていき、三人それぞれが「ラッキー!」と叫びながら赤いポストのあの手形の場所に続けて左手をタッチしていった。そのまま駆けてゆく三つの黄色い帽子を眺めながら、4回目の「本当に申し訳ございません!」では顔は笑っていた。
「ええ、本当に……道ですか、あ、それはわかります。はい大丈夫です。はい、僕の地元なので」

※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。