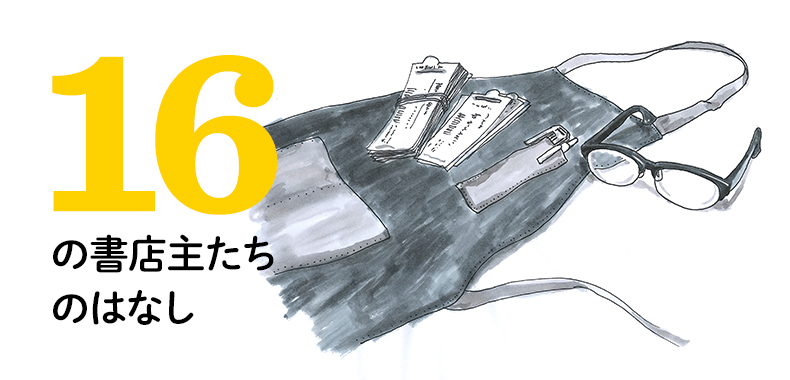ある本屋のはなし
文・イラスト すずきたけし
汗で濡れたシャツが肌に張り付いたまま、テラス席の固い椅子に腰を下ろした。
ビアガーデンのテラス席には私たちとネクタイを緩めたサラリーマン3人のひと席だけが埋まり閑散としていたが、テラスから見える冷房の効いた屋内席は満席だった。
神宮外苑は夕暮れとはいえすでに薄暗い。昼間にあれだけ攻撃的だった日差しも幾分和らいでいるだろうと思っていたが、日が暮れても重くのしかかるような暑さは居座り続け、湿ったシャツは一向に乾かずに肌に張り付いていた。この不快ともうしばらく付き合わなくてはならないと思うと気が滅入った。
「木下さんはなにします~? ビールでいいですか~?」
なんでもいいからこの不快をぬぐい去りたい私は河合くんに愛想のない返事をした。
せっかくなのでビアガーデンにいきましょうと誘ってきた河合くんは私が以前に働いていた中堅出版社の後輩だ。なにがせっかくなのかよくわからないうえ、この息苦しい暑さの中なぜ外で飲まなければならないのかと思いながら、私はシャツの胸元をつまんで汗で濡れた肌に外気を送り込んだ。
「今日は暑いですねぇ~」とやたらと語尾を伸ばす癖のある河合くんと運ばれてきたビールで乾杯をすると、最近の書店や他社の動向、顔見知りの同業たちの近況などの話が始まった。5年前に出版社を辞めて業界紙で書店の記事を書いている私は、いつのまにか全国の書店を訪ねて紹介記事を書くようにもなった。出版不況という世の流れから記事となる書店も徐々に昔ながらの町の書店が尊ばれていき、そしていまでは「消えゆく」という言葉を臆面もなく付けるようになっていた。私が出版社を辞めて5年のうちに書店を取り巻く状況はとても厳しいものになっていたので、現役の書店営業である彼の情報はとても助かっていた。
「木下さん、まえに古書店の取材もはじめなきゃって言ってたじゃないですかぁ?」
「そうなんだよ」と私はグラスの結露で水浸しになったテーブルをナプキンで拭きながら話を続けた。「出先でGoogle Mapで新刊書店を検索するだろ? そうすると駅の近くやそこそこの町なのに新刊書店が1軒だけだったり、最悪書店が無いことがあるんだけど、古書店は結構な確率であるんだよ。そこを見なかったことにして新刊書店ばかり取材しているのも違う気がしてなぁ」
「昨日営業中に車で回っていたらいい感じの古書店見つけましたよ。たまたま昼時で飯食うところないかなぁってスマホで調べてみたら食堂が一軒あったので幹線道路から降りてみたんですよ。食堂もザ・町の食堂って感じだったんですけど、食べ終わってちょっと辺りをぶらぶらしてたら木下さんが好きそうなザ・地場って感じの古書店があったんですよ」
「へえ、店の名前は?」
「そういえば名前なんていったかなぁ、鳥の名前だったんですよ、ブンチョウじゃなくて、セキレイじゃなくて……」
私はスマホでGoogle Mapを開いて検索する用意をした。河合くんはそれを見て「あ、検索しても出ないですよ。僕もその場で検索してみたんですが登録されてないみたいで出ませんでした」と言っていつのまにかビールから変わっていたハイボールを飲み干した。
写真は撮ってこなかったのか聞くと「それが撮ろうと思ったんですけどぉ、店の向かいの家の二階からずっとこっちを見ている人がいたのでちょっと写真を撮れる空気じゃなくて…」
と河合くんが言ったところでサラリーマンの3人組が大きな笑い声をあげた。
「ただ、寂れた漁村みたいなところだったんですけど、独特の雰囲気がありましたよ。時間が止まったような感じというか」
「詳しい場所教えてよ」と私が言うと河合くんは書店の場所のリンクをメールで私へ送ってくれた。届いたメールのリンクをタップすると画面にmapが表示され、海沿いの太い幹線道路の脇から小枝のように伸びた細い道の先に赤いピンが立っていた。
「なんだ都内から結構近いじゃないか」。
顔を上げると、テラスの外をたくさんの人が賑やかに歩いていた。
河合くんも私の目線を追って「あ、試合終わったんですね」と言った。
野球の試合が終わり神宮球場から帰りの途についた観客たちだった。
「駅は混んでそうですねぇ」
シャツは汗で濡れたまま、私と河合くんはもうしばらくグラスを傾けあった。
起きたのは昼も回った頃だった。重い体をベッドから転がして洗面所で顔を洗いながら昨晩を思い出そうとしたが、飯田橋で降りて2軒目に入ったところからその先は思い出せなかった。洗面所から出てスマホを手にすると河合くんから昨晩のお礼がショートメールで届いていた。返事をしようと画面をタップした瞬間、ドンッとベランダの窓から大きな音がした。驚いて思わずスマホを落とした私は、拾おうか音の方を調べようか戸惑った。窓に近づくとベランダの下で翼をバタつかせたカラスが鳴きもせず暴れていた。窓に目を向けるとカラスがぶつかった汚れた跡があった。その跡に手を添えた私は「なんだよおい」とつい声を漏らした。暴れているカラスを見ながら窓を開けようか迷っていると、カラスは突然浮き上がるように私の目の高さまで羽ばたき、ベランダから外へと落ちるように消えた。窓を開けると熱風が顔にまとわりつき、日差しの眩しさに目をしかめながらベランダに出た私はカラスの姿を目で追おうとした。しかし視界のどこにもカラスは見当たらず、落ちたのかと真下を見ても自分の車以外に駐車場にはいなかった。すると突然セミが鳴き出した。カラスが消えるまで静かだったことに気づき、汗が体を濡らした。カラスの黒い瞳がしばらく頭に残っていた。
昨晩に河合くんから聞いた書店に向かおうと考えていた私は、車で高速道路に乗るとそのまま1時間ほど走り続けた。高速道路を海岸と並走する国道と交わるところで降りると、工業地帯特有の幅の広い道路が目の前に広がり、視界の大半を占めた青空に自然と笑みがこぼれた。
コンビニで遅い昼食を済ませた私は、休日の半日を寝て過ごしてしまった後悔を少しでも取り戻そうと小旅行気分に頭を切り替えた。せめて海を眺めながら気分よく車を走らせようと、なるべく海に面した道を選んだ。バイパスや国道などの新しい幹線道路は海から離れたところにあるため、海を視界に入れて走る道は旧道である生活道路を走ることになる。狭いながらも往時は車の往来も多かったであろう道には商店や洋品店の看板を掲げた店舗が軒を並べていたが、みな外観からは営みを感じられなかった。この暑さのためか歩いている人はひとりもいない。都内から車で1時間少々の距離にあるにもかかわらずここには人の営みが感じられなかった。海側に目を向けると、建ち並ぶ家屋の隙間からもったいぶったように海の鮮やかな青が通り過ぎ、私の中の寂寥感をわずかに拭っていた。
しばらく進むと繋留された三隻の小さな漁船が見えた。道から数十メートル離れた海岸で男性と奥さんらしき女性が屈んで船の脇でなにやら作業をしている。すると私の車の音に気付いたのか二人とも立ち上がって私の方に顔を向けた。男性は帽子を深くかぶり、女性も頭巾をかぶっていたが老齢に差し掛かった感じだ。強い日差しのせいか表情は影になって窺えない。二人は会話するでもなく真一文字に口を閉じ、その両手は汚れていた。なにか濡れたものを持ってはいたがよくは見えなかった。近づくにつれてよく見ると手の汚れは血のように見えた。私が通り過ぎるまで二人はそのままの顔を私に向け続けた。少し気まずい雰囲気になったので私は目を合わさずに前方に顔を向けて通り過ぎるのを待った。通り過ぎたところでそっとバックミラーを見ると二人はまだこちらを見ていた。すると二人は口を開いてなにやら声をあげていた。夫婦で会話をしているというよりも私に向かってなにかを言っているようだった。やはりよそ者が走るような道ではなかったなと私は後ろめたくなった。すると前方から自転車にのった年老いた男性がこちら側に向かってやってきた。私の車に気づくと道路の脇に自転車を止め、先ほどの二人と同じように私を見た。見たことない男が乗った車が走っているのだ。それは気になるだろう。とまた気まずい雰囲気が流れた。わずかに男性に目を向けると、口元を少し前に出して彼もなにやら声に出していた。男性は野球帽をかぶっていたが、近づくと目元がわずかに見えた。白目がなく、黒目だけのように見えた。
少しアクセルを踏んでスピードを上げて男性の横を通り過ぎた。男性は私のほうを向いて「お…おお……」と聞き取れない声でなにかを言っていた。
車を進めると幹線道路に合流した。
件の書店はここより少し先になる。昨晩に河合くんから教えてもらった書店の場所をスマホのGoogle Mapで開き、そのままカーナビとして設定した。現在地からの経路を青いラインがするりと伸びて所要時間が23分、12kmと表示された。幹線道路は海沿いの集落から陸側の山側に沿うように通っている。右手の海を見下ろすと草木の間に古びた民家の青い屋根が視界を流れていった。
「この先、分岐を左です」
ナビの音声を聞くと幹線道路から左に分岐した細い道へとハンドルを切った。幅が車一台分ほどしかない道はぐるりと左回りに弧を描くと、自分が走ってきた幹線道路がその細い道への日差しを遮った。山の斜面に沿った細い道は一日中陽が当たらないのか、アスファルトがうっすらと苔で覆われていた。暗い小道を下りていくと、先ほど走っていた幹線道路の下に回りこんだ。苔蒸したコンクリートの壁にぽっかりと車一台分の黒い穴があいていた。幹線道路の下をくぐるトンネルは短いはずなのに中はとても暗く、そのまま地底へと通じているような薄気味悪さを感じた。しかし車を進めるとなんのことはない、トンネルはSの字を描いていて先の明かりが出口には直接届かない構造になっていただけだった。トンネルを抜けると焼けるような日差しが目を覆った。目を細めると道はまっすぐと伸びて堤防のコンクリートにぶつかり、その先に海が覗いた。
木造の黒い壁の民家が両脇に一軒ずつ並んだ道をまっすぐ進むと堤防に突き当たり丁字路になっていた。スマホのナビが左へ曲がるよう案内したので、そのままハンドルを左に切ると堤防に沿って道が続いていた。ゆっくりと車を進めた。堤防で視界が遮られ海は見えない。不思議なことにその先には海があるはずだが波の寄せる音は聞こえない。窓を開けると強烈な磯の匂いとともに手で握れるかのような熱く重たい空気が車内に溢れてきた。しかし波の音は聞こえず、自分の車がアスファルトの上の砂利を噛む音だけが小さく鳴り続けた。
「目的地は右側です。おつかれさまでした」
ナビの音声ガイドが到着を告げた。
黒い木造の平屋の建物は一見すると民家のように見えたが、正面はガラス戸で占められ商店ということがわかった。上部には庇を支えていた骨組みだけが残り、黒い錆で覆われていた。ガラス越しに店内に目を凝らすと、確かに本が並んでいる。ガラス戸に経年で色が落ちているものの、うっすらと残った跡から屋号が読めた。
“ほおじろ書店”
私はこんな場所に書店があることにあらためて驚き、また店内に本が並んでいることに喜んだ。車から降りると相変わらず磯の生臭い匂いに眉をしかめたが、河合くんに写真を送ってやろうとスマホのレンズを店に向けた。河合くんが訪れて写真を撮ろうとしたときに向いの家の二階に人がいたと言っていたのを思い出し、私は振り返った。そこには二階建ての家はなく、木造の平屋が一軒あるだけだった。スマホで店の写真を3枚ほど撮って、お礼のメッセージと合わせて河合くんにメールを送った。
ガラス戸をガタガタと鳴らしながら開けると、木と強烈な紙の匂いが鼻をついた。これこそ本屋の匂いだと気分が高まった。10坪もない店内にはガラス戸から差し込む陽の光以外に明かりはなく、店の奥は薄暗い。狭い店内には誰ひとりいなかった。棚にある本を覗いて適当に一冊の本を手に取ると、その本は漁で財を成した地元の名士らしき人物の自伝だった。なるほど郷土出版の本を中心に置いてある書店なのかと納得した。そのほかにも測量史や、集落についての歴史を記した本があった。中でも目を惹いたのは“神海図経”という本だった。いまどき和綴じで製本するなんて洒落ているなと感心して出版社を確認しようとしたが奥付が見当たらなかった。ページをめくっていくと魚に四本の足が生えている生き物の薄気味悪い絵が現れた。そのあとも人魚のように下半身が魚、またその逆の上半身が魚で下半身に人間の足が生えた生き物の絵が描かれたページが続いた。絵に添えられた説明は古文書のようにくずし字で書かれており、なにを表した絵なのか私にはわからなかった。ページをめくり続けると、手足のある魚がバラバラに解体されて桶の中に入れられていた。その横に二人のふんどし姿の男性が描かれ、左の男性は肉片を両手でつかみ、腕から肩まで滴る血で赤く染めながら嬉しそうに両手を空に掲げていた。その隣の男性は口から上半身まで血に染めながら解体した魚の“手”に噛り付いていた。いつの時代の絵なのかわからないが、血の色合いや筆の線が直筆かのように生々しく、印刷であれば素晴らしい出来だった。店主がいまだ姿を現さないので、わたしは店の奥へむかって「ごめんくださーい」と声をかけた。どうしてもこの本を買って帰りたかった。すると母屋と思われる奥の暗がりから廊下の床を踏み鳴らす音がこちらに近づいてきた。
ぎっぎっぎっ
わたしは「突然お邪魔してすみません」と音のするほうへまた声をかけた。また、ぎっぎっぎっと先ほどよりも大きな音がした。すると強烈な生臭い匂いが私の目鼻を叩いた。目から涙が溢れ、両手で鼻を覆うが吐き気を催し顔を上げてはいられなかった。かろうじて音のした方向に目を向けると、白目のない真っ黒な目と、鱗に覆われた人の形をしたなにかが見えた。ぎっぎっぎという音はその生き物が発する鳴き声だった。ここにいてはいけない。そう感じた私は引き戸を勢いよく開けて店から飛び出した。車に飛び込み、薄暗い道を引き返して幹線道路へと戻った。
鼻の奥にはまだあの生臭さが残っていた。
あれはなんだ? 車を走らせながら私は混乱した。暑さにやられて幻覚でも見たのだろうか。しかしあの匂いだけはいまだに鼻から喉にかけて残っている。意識するとえずいてしまう。鼻と喉の生臭さを飲み物でぬぐい去りたくて自販機を探した。自販機が設置された駐車場を見つけ車を停めて降りると異様な湿度に一瞬でメガネが曇った。湿った重い空気が私の体を包み、またあの強烈な魚の生臭い匂いが鼻をついた。鼻を押さえながら自販機へと向かった。缶コーヒーを買った私はすぐに喉に流し込み、生臭さがまだ抜けない気がしてもう一本空けた。さっき見たものがなんだったのか何度も思い浮かべようとした。だがなぜか頭の中で記憶の像が結べなかった。ポケットに入れたスマホから着信音が聞こえた。河合くんからのメールだった。
“お疲れ様です。そこどこですか?(笑)さすがにそんな古い建物じゃないですよ。もしかして道に迷いましたか?”
私はGoogle Mapを開くと、あの書店の前の道をタップした。画面はストリートビューに切り替わった。そこに映ったのは、コンクリート建築二階建ての書店だった。道路を挟んで向いに画面を移すとベランダのある二階建ての民家があった。地図ではたしかに私がいた場所を指しているが、写真に写る建物、道路は明らかに最近のものが映っている。
私がいた場所ではなかった。
どろりと汗が背中を流れ落ちた。ようやく一息ついて顔を上げるとここからは海が一望できた。薄暮の中で目を凝らすと海に向かって据えられたベンチに男性が座っていた。ももひきに白いランニングシャツの老人であった。両手を両膝において正面より少し横に顔を向けて海岸あたりを眺めている。なにを眺めているのだろうかと気になった私は男性の視線を追った。小さな砂浜が見えた。すでに西陽も力を失った砂浜へと私は目を凝らした。海からのベトついた風が頬を撫でた時だった。黒いなにかがひとつ海から現れた。そのそばにもうひとつ現れた。そしてまたそばにひとつ。気がつくと数十の黒いものが海に浮かんでいた。いや、浮かんではいなかった。返す波に留まり、ゆっくりと砂浜へと向かっていた。歩いている。砂浜に近づくにつれ黒いものが上半身を露わにし、二本の足で歩いていた。前傾した姿勢でだらしなく前に垂らした両腕は異様に長い。濡れた肌は黒く、どう見ても人間の肌ではなかった。魚のような、爬虫類のような、暗さではっきりとは見えないが、明らかに人間以外のなにかであった。
「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛……あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛……あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛……あ゛あ゛……あ゛あ゛あ゛あ゛……」
突然ベンチに座っていた男性から喉を鳴らすような声が上がった。
驚いた私は男性を見た。すると男性は海に向かって頭を突き出しなおも叫び続けた。
私は再び海に目を向けると、海から上がってきた数十の生き物たちが砂浜に立ちどまり、一斉に男性と同じような声を上げ始めた。
男性はゆっくりとこちらを向いた。
濡れた体は黒い鱗で覆われていた。膝に置いていた両手は地面にすれすれまで長く垂れ下がっていた。
開いた口には無数のトゲのような歯が並び、人間のそれではなかった。
私はその場から動けず、助けを呼ぼうと手に持っていたスマホに目をやり、また視線を前に戻すとそれは目の前に立っていた。
自分が見ているものがなんなのか考えることができなかった。強烈な臭気に涙が溢れ、胃の中のものを足元に吐き出した。涙を拭い、自分の瞼を精一杯こじ開けた。
私が最後に見たのは魚の目だった。
※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。