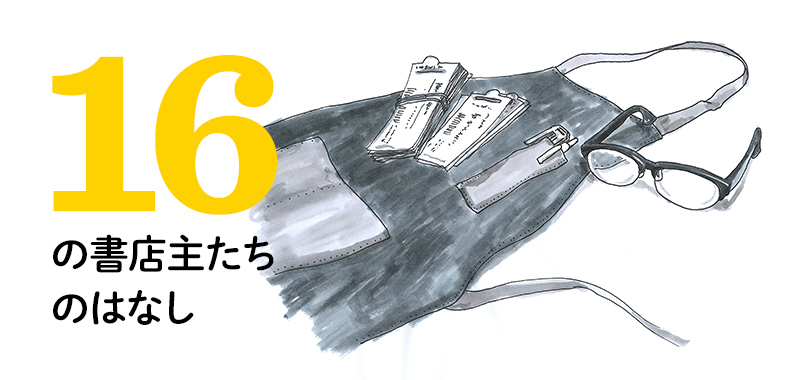母のしおり/コクリコブックス
文・イラスト すずきたけし
「リョウイチ、この先の信号を越えて左ね」
助手席で母が言った。
母と私は眼前に広がる一面の田畑をまっすぐに貫く幹線道路を車で走らせていた。
「え、この道のままでも行けるよ」とハンドルを握った私が言うと
「そっちの方が近いのよ」と母は水の入ったペットボトルを口に運んだ。
信号を過ぎて左へと延びていた道は車が一台入れるほどの農道だった。
私は慎重にハンドルを切った。
道の両側の畑に車が落ちないようゆっくりと進むと、前方の地面が盛り上がり視界の下半分を遮った。川の土手だった。土手と並行に緩やかに右へカーブするとそのまま土手の側面に沿って道は登っていく。車が土手の頂上へと出ると視界が開け、開放感の心地よさが車内を明るくした。私は助手席の母の先に対岸の土手まで数百メートルはある広い河原を見た。それに比べれば拍子抜けするほど細い川が河原真ん中を流れていた。母はその河原の景色をただ黙って助手席から眺めていた。
対岸の土手の奥にはいくつもの送電塔が青い空の遥か先まで続いていた。
「よくこんな裏道知っているね」
「20年以上もこの道使って通勤してたんだもん。この辺の道はだいたい知っているよ」と言って母はまたペットボトルに口をつけた。
病院の入り口の前に車を寄せると「じゃ、三時くらいに迎えに来てね」と母は車を降り、少しかがんで助手席の窓越しから私に向かってかるく手を上げて病院の中へと入っていった。
三ヶ月後、母は亡くなった。
明け方の病室の窓の外はまだ暗かった。看護師が病室に来て呼吸が止まった母を確認して「先生を呼んできますね」と穏やかに言った。それから窓の外が白み始めるまで、私はベッドの隣のソファに座りながら母の横顔を眺め続けた。
窓の外から陽が差し込んできた頃、担当医が来て母の死を正式に告げた。
病室から出ると大きなガラス窓に囲まれた誰もいない5階の休憩コーナーで葬儀会社に電話をかける。近くにベンチがあったが座ってしまうと立てなくなりそうで、そのまま立ち続けて電話の向こうから聞こえる声に相槌を打った。
窓の外に目をやると朝陽が私の顔を温めた。鋭い光が目を覆ったが私は眩しくとも目を閉じることを諦めて光の先を見つめ続けた。
今日の朝日をついに母は見ることができなくなったと思うと、朝陽の眩しさを涙が和らげた。
葬儀会社の女性スタッフ二人が母を迎えに来た。
私は私物を取りに誰もいなくなった病室に戻ると、自宅から持ってきた湯飲みやタオル、着替えを備え付けの戸棚からバッグに移した。ベッドの横の椅子に置いてある、母が生前に編んでいた編みかけのマフラーと編み物道具、そして日焼けして茶色くなった古い編み物の本は紙の手提げ袋に押し込んだ。
病室から出る前にもう一度忘れ物がないか振り返った。
母が一ヶ月以上暮らしたこの小さな病室はあっけなく誰のものでもなくなった。
* * *
葬儀も終わり弔問客も落ち着き始めた頃、私は母の遺品の整理を始めた。
ガラス戸の付いた棚の中に本が数冊並んでいるのを見つけた。本を読んでいる母の姿を見たことはなかったが日に焼けて茶色くなった本と薄い編み物の本が10冊ほどあった。私は編み物の本を一冊抜き出した。表紙はスレ傷でボロボロだったが、綺麗に七三に分けた眉の濃い凛々しい男性モデルがセーターを着てポーズを決めていた。ページを開くと男性向けのセーターの編み方が解説してあった。パラパラとページをめくると、するりと一片の紙切れがページから滑り落ちた。足元に落ちた細長い紙片を手に取って裏返すとニワトリのイラストとともに「生活のおともにコクリコブックス」と書かれた本のしおりだった。
本屋の名前の下には「新宿区上落合」と住所が書かれていた。
母は昔この本を東京の書店で買ったらしい。
私は棚からもう一冊抜き出してページをまたパラパラとめくった。すると同じしおりがまた挟まっていた。
ポケットからスマートフォンを取り出して「コクリコブックス」と入力するが検索結果に本屋らしき店は現れなかった。続けてしおりに書いてある住所を入力してみる。
すると地図が画面に表示され、中央に赤いマークが示された。指で画面を拡大していくと建物の名前が現れた。それは書店だった。
私はその場所を保存し、手に持ったしおりの一枚を財布に入れた。
* * *
2月のある日、新宿区の中井という駅で降りた。
改札を抜けると冷たい風が私の頬をひっかいた。細めた目をゆっくりと開くとそこは細い路地だった。
右へ視線を移すとすぐそこに目的の書店が見える。見上げると緑色の看板に「飯野書店」と書いてあった。
軒先には雑誌がラックに入って置いてあり、中央に人ひとりほどの幅の自動ドアが見えた。私は店に入ろうとドアの前に立ったが、自動ドアは微動だにしなかった。もしかして休みだったか。店内の様子を伺おうと自動ドアのガラスに顔を近づけると同じくこちらを覗く男の顔が目の前に現れた。
驚いた私はうわっと声を出して二、三歩あとずさると自動ドアがガタガタと音を立てて横に動いた。
「すみません、自動ドアが調子悪くて開かない時があるんですよ」とドアを手で開けながらエプロンをつけた背の高い男性が笑った。
男性は「どうぞどうぞ」といって店の外に出て店内へと手を伸ばした。
「あ、どうもすみません」と私はかるくお辞儀をして店の中に入った。
後ろでは男性が自動ドア上部にあるスイッチを入れ直してドアから離れた。ピっと音がして自動ドアがゆっくりと動きだして完全に閉まると、エプロンの男性はまた自動ドアの前に一歩進んだ。すると自動ドアがガガガガ・・・と音を立てて開いた。「よし」と男性は満足そうに入り口横のレジカウンターに滑り込んだ。
私は男性に黙ったまま頭を下げると改めて店内を眺めた。正方形の店内の中央には書棚が二つほど平行に並んでいて子供の頃に友達とよく行った本屋に似ていた。ゆっくりと店内を進むと正面奥の壁には漫画が並び、小学生くらいの男の子が棚の前でぶつぶつ言いながらジリジリと左に動いて棚を睨んでいる。中央の二つの棚にはそれぞれ文庫本と単行本があった。入り口から向かって左手には旅行の本があり、スーツを着た二十代くらいの女性が「台湾」と書かれたガイドブックのページをめくっていた。その奥には料理や育児の本があり、角には子供向けの絵本があった。
私は文庫本の棚から適当に一冊を手に取りレジに向かった。レジにいる男性に本を差し出すと男性は「いらっしゃいませ」と言って本を受け取り、本のバーコードを機械で読み取った。
「880円です。カバーはおかけしましますか?」
「ああ、じゃあお願いします」と私が言うと「かしこまりました」と男性は丁寧に答えた。
私は1000円を出して受け取ったお釣りを財布へ入れると、代わりにあのしおりを取り出した。
「少々お待ちくださいませ」とまた丁寧な言葉で男性は文庫本にカバーをかけ始めた。
待っている間にレジの右手に目をやると、小さなラックに文庫本が並んでいる。文庫コーナーとは別に文庫が並べていることになにか意味があるのだろうかと書名を目で追った。『砂の器』、『魚影の群れ』、『寒椿』、そして最後の本に目が止まった。
『鬼怒川』
そういえば母の棚にあったのも文庫本ではなかったが『鬼怒川』という本だった。
「お待たせしました」という男性の声で私は向きなおり、男性が差し出したカバーがかけられた文庫本を受けとると、ここに来た本題を話し始めた。
「あの、突然ですみませんが、このしおりの本屋さんは以前こちらにあったのでしょうか?」
財布から出したしおりを男性に見せる。
「あ、それは昔のウチの屋号ですよ。父の代のものです」
男性は驚いた表情で歯切れよく言った。
「へえこんな名前入りのしおりを作ってたのかあ。よく残ってましたね? もしかしてご近所さんですか?」
「いえ栃木からです。実は亡くなった母が持っていた本に挟まっていたもので、しおりに書いてある住所を調べたらこちらの本屋を見つけまして、もしかしてこのしおりの本屋さんと関わりがあるかなと思って」
私はレジ横のあのラックの中の文庫本を指差して
「ここにある本はなにか意味があるんでしょうか?」
「あ、これは僕の父がそのコクリコブックスという本屋を始めた時から置き続けた本らしくて、店のお守りみたいなものなんだってことで今でも置き続けているんですよ」
「へえ、そういうもんなんですか。面白いですね」
「昔はもっとたくさんあったらしいのですが、絶版とかで今はだいぶ少なくなったと言ってましたね」
男性は穏やかに笑った。
「この『鬼怒川』って本、母の本棚にもあったんですよ。同じしおりが挟んであったのでこの本もこちらで買ったんですね」
私はまっさらな新しい表紙の『鬼怒川』を見つめた。
「へえ、ちょっと待っててください」
男性はそう言うとレジの奥へ引っ込んだ。トントントンと階段を上っていく音がした。
私は一人でレジに残された。店内は先ほどの子供と女性と私の客三人だけになったが、いつもこんな調子なのだろうか。
しばらくするとまたトントントンと階段を降りてくる音がして「すみません、お待たせしました」と男性は戻ってきた。
「いま父が降りてくるのでちょっと待っててもらっていいですか?」
そのままぽかんとしていると、トン、トン、トン、と音がして年配の男性が顔をだした。目が会うと男性は「いらっしゃいませ」といって頭を下げた。男性は息子と違って小柄だった。
「もしかして静子さんの倅さん?」
「え、あ、はい。」
私は男性の口から母の名前が出たことにびっくりしてすこし大きな声を出した。
「どうも飯野と申します」と言って頭を下げた。
「これは息子のマサユキです」と言われて店番をしていたマサユキさんも頭を下げる。
「これなんですが」と私は件のしおりを飯野さんに見せた。
「ああ、この店を開業したときに宣伝も兼ねて作ったやつですよ。懐かしいね。このニワトリの絵は死んだカミさんが描いたんですよ。うまいもんでしょ」としおりを見つめながら言った。
「死んだ母の本に挟まっていたので、住所を見てこちらに来てみました」
「栃木の人で『鬼怒川』を持っていると聞いてピンときましたよ。いつ頃静子さんはお亡くなりになったんですか」
「昨年の12月に」
「それはそれは、ご愁傷様です」といって飯野さんは今度は深く頭を下げた。
私も黙って頭を下げると「母はこちらの本屋さんの常連だったんですか?」と訊いた。
「静子さんはこの近所のアパートに住んでてね。いまは小綺麗なアパートばかりだけど、昔はこのあたりは木造アパートがたくさんあってね」といって男性は宙を指差した。たぶん母が住んでいたアパートのほうを差しているのだろう。
「いらしゃいませ」とマサユキさんが言った。
旅行ガイドを立ち読みしていた女性が私の傍から本をレジに差し出した。
私はそそくさとレジの前からわきへと避けて飯野さんの話を聞いた。
「私はもともと材木屋をやってたんだけど昭和47年に本屋のほうが楽そうだってこの店を始めたんですよ。けどあの頃は本なんてそれまで読んだこともなかったから売れる本もわからない。だから店に来る客に何を置いて欲しいか聞きまくったんですよ。あのころはこのあたり下宿が多くてみんな東京に働きに来ている若い人たちばかりでね。そしたら自分たちの故郷を舞台にした小説ばかり言ってくる」と言って笑った。
つられて私も笑う。
「その『鬼怒川』は静子さんから置いてくれって言われたんですよ」
「そうだったんですか」私は大きく息を吐き出した。
「ありがとうございました」マサユキさんが先ほどの女性客に声をかけた。
「ありがとうございました」と飯野さんも続いた。
「で、お客さんが置いてくれっていうものを本屋である私が読まないわけにはいかねえってんで、私も『鬼怒川』読んでみたんですよ。そしたら主人公の旦那と倅が埋蔵金だかなんだかにのめり込んでいくろくでもねえ話なんですよ。あ、まさか親父さんと埋蔵金探してたり」と言って飯野さんは意地悪そうな顔をして私を指差した。
「いやいや父も私が20歳の時に亡くなりまして」
「あ、これは悪い事言ってしまったね。申し訳ない」
「いえ、私は父と仲が悪くてすぐに家を出てしまいまして、あまり家にも顔を出さなかったものですから、母の若い頃のこととか全く知らないままだったんですよ。だからしおりを見つけた時に母の過去に興味が湧いてきまして、まさか東京の本屋に通ってた事も、ましてやここに住んでいたことも知らなくて。お恥ずかしい限りです」
私は俯いて頭をかいた。
「あのころの静子さんは百貨店の手芸用品の売り場で働いているって言ってたよ。よく編み物の本を買ってた」
私はあの本棚の本を思い出した。
「このあたりは若い人の一人暮らしばかりだったから料理の本とか実用書がよく売れてね。裁縫とか手芸の本も人気だったからけっこうな量を揃えていましたよ」
「ああ、だから『生活のおともに』というキャッチコピーが」
私はしおりを飯野さんに向けて掲げた。
「そうそう、実用書の専門店みたいなもんだったな」
「その当時からここは変わらないんですか?」
「昔はコンクリの二階建だったね。今のここはマサユキが継いだ時にリニューアルするってんでついでに建て替えてね。それでももう20年くらい経っていてエアコンは言う事聞かねえし、自動ドアも開かねえしでどこもボロボロだあね」
マサユキさんは胸の前で腕を組みながら笑った。
「昔は木製の棚でね。なんせ俺は材木屋だったから」
あ、そうだと飯野さんは思い出したように「ちょっと待ってもらっていいかい?」と言って、私の返事も待たずに奥の階段をトン、トン、トンと上っていった。
なにか店の中だけのんびりとした時間が流れているようだった。マサユキさんは片眉を下げながら「すみませんね。昔話をしだすと親父は止まらないんですよ」と言った。
しばらくするとまたトン、トン、トンと階段を降りてくる音がして飯野さんが顔を出した。手には写真アルバムがあった。
「これ昔の店の写真」といって私に手渡した。
私は「すみせん」と言って両手で受け取ると、茶色に変色したビニールカバーに包まれたアルバムを右手で抱え、ページを開いた。
一枚目の写真には『生活のおともにコクリコブックス』という看板を掲げた軒先に飯野さんと奥さんが並んで立っていた。建物はコンクリートの二階建てで、看板を見なければ本屋には見えなかった。
細身で凛々しい飯野さんとハツラツとした笑顔の奥さんはお似合いに見えた。
「建物だけ出来上がったときに記念で撮ったもんだね。まだ本も並べてなかったけどね」
「コクリコブックスという名前はなにか意味があったんですか?」
「いやたまたま」と言って飯野さんは笑った。
「なんでもよかったんだけど、カミさんがニワトリを飼っててね。まさかニワトリブックスなんて屋号はカッコつかねえから横文字で良さそうなのないかって調べたらフランス語でコクリコって言うんだとかで、じゃあそれでいいじゃねえのってことで決めたんですよ。あとでコケコッコーの鳴き声がフランス語のコクリコって言うらしいって知ったんだけどね。結局マサユキがダサいとかなんとか言って改装したときにおとなしく飯野書店になったんだ」
といって飯野さんは息子の方を向いた。
「コクリコはダサいよね」といってマサユキさんが言うと
飯野さんは「あの頃はカタカナがかっこよかったんだよぅ」と笑った。
私はページをめくり続けた。
木製の書棚を軒先で組み立てている写真があった。
「これこれ。あの頃は手作りで棚を作ったんだよな」
続けてページをめくると開業して軒先に花が並んだ店の写真が出てきた。
その周りには大勢の人が囲んでいた。
「オープン初日だね。みんな本屋ができるってんで喜んでくれてねぇ」
レジで微笑む女性。
「カミさんだね。若かったねえ」と飯野さんは嚙みしめるように言った。覗いたマサユキさんは「こう見ると姉さんにそっくりだな」と言った。
どこかの会社の制服を着た三人の女性と一緒に本を持ってポーズをとる飯野さん。
店の前でセーラー服を着た女子高生と飯野さん。
飯野さんも当時はまだ20代くらいだろうか。凛々しい飯野さんが女性にモテたのは想像がついた。
写真は飯野さんと女性との写真ばかりだった。
ページをめくるとまた長いまつげにミニスカートのスレンダーな若い女性と一緒に写る飯野さん。
「あ、それが静子さんだよ」
「ええええ!!」
私はまた大きな声を上げてしまった。
漫画の棚の前にいた小学生が迷惑そうな目でこちらをチラッと振り向いた。
私は声を抑えて「これ、母ですか・・・・。いや、私が知っている母とだいぶ違うんですが・・・・」
「そりゃこのときはミニスカート流行ってたもんなぁ。ツイッギーとかなぁ?」
マサユキさんは「知らないよ」と言って首を横に振った。
そのあとも飯野さんと女性との写真ばかりが続いた。
ページが残り少なくなったところで私は手を止めた。
一枚の写真が目に飛び込んできた。
その写真は右に飯野さんが、真ん中に先ほどのミニスカートの女性。つまり私の母、そして左には七三にビシッと分けて眉の濃い男性。
私の父だった。
そして母の腕の中には小さな赤子がいた。
気づいたら私は飯野さんとマサユキさんの前で涙を流してた。
飯野さんは黙ってティッシュを私に差し出した。
涙を拭きながら私は写真を見続けた。
父と母は笑っていた。
最期の日まで母はあの朝陽を何回見たのだろうか。

<実用書専門書店「コクリコブックス」今回のはなしの1冊>
『鬼怒川』有吉佐和子 著(ISBN:9784101132150)
※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。