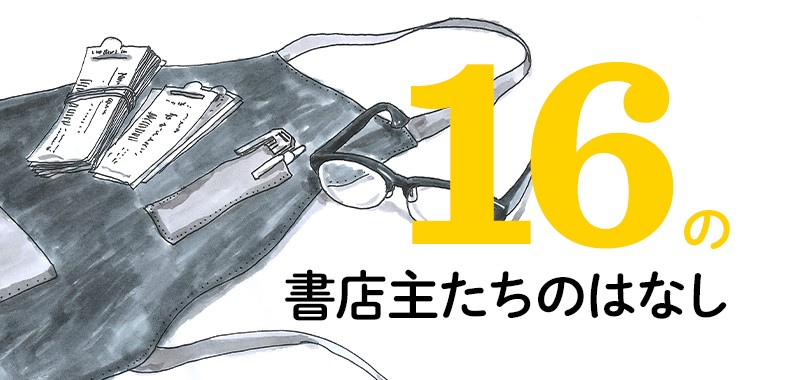星の町/絵本のペンギン堂
文・イラスト すずきたけし
現在 2093年 ぺんぎん堂
雲ひとつない突き抜けるような秋の青空が町を包んだその日、ペンギン堂の店主はレジのカウンターでひとり座りながら仕入れた絵本を検品していた。店に差し込む明かりの先にある窓に目を向けると濃厚な青い空の下に佇む町並みが窓枠に収まっていて、まるで額装された絵画のように見えた。
絵本の専門書店ぺんぎん堂はここ星乃町で50年以上本屋を続けている。もとは父が始めた本屋だったが30年ほど前に亡くなり、大学を卒業してそのまま本屋を継いだ。父が本屋を始めた頃は5万人ほどの人口だったという星乃町だったが、いまでは3万人にも満たなくなっていた。
遠くで子供のはしゃぎ声が聞こえた。店主は老眼鏡を鼻の下にずらして店の外を見ると、駆け足の音が次第に近づいてきて男の子が横切っていった。男の子は「ぼううううっ」と奇声をあげながらロケットのおもちゃを頭に掲げていた。続いて母親と思しき女性が「不要跑!(こら、走らないで!)」と叫び、その脇を歩いていた男性が「火箭不是横着飞,而是往上飞。(ロケットは横じゃなくて、上に昇るんだぞ!)」と笑いながら通り過ぎた。そのあとからも多くの家族連れが通り続け、いっとき店の前はお祭りのように賑やかになった。
店主は何事もなかったように老眼鏡をかけ直して納品書に目を落とした。
すると勢いよく店の中に男が駆け込んできた。
「え、なに、マサさん、打ち上げ見にいかないの?」斜め向かいにある理髪店のキョウさんだった。
「店を留守にするわけにいかないでしょう」
「今日くらい休んでもいいんじゃないの、お祭りみたいなもんだし」レジに歩みながらキョウさんが言った。
「うちは年中無休。親父の代からね」マサはわざとキョウさんと目を合わせずに納品書に目を落としたまま返事をした。
「今日は町の子供たちみんな打ち上げ見物に出かけていて絵本なんて買いに来ないでしょうよ」
頭を下げたまま老眼鏡越しに上目でキョウさんを一瞥したマサは何も言わず持っていたボールペンで店の奥を指し示した。
店の奥にある窓際のテーブルには5、6歳くらいの男の子と、絵本を読み聞かせている20歳くらいの女性がいた。
「打ち上げに興味のない親子もそりゃいるか・・・」
キョウさんは自分の肩越しに二人を覗きながら言った。
「キョウさんも、なにもこんなに早く行かなくてもいいでしょうよ。打ち上げの時間はまだ先でしょう?」
「いや、場所取りしておかないとね」
マサはため息まじりに「運動会じゃあるまいし」と言った。
「運動会みたいなもんだよ、いや花火大会かな。マサさん打ち上げ行ったことないの?」
顔を上げたマサはキョウさんの目を見て言った。
「打ち上げは一度も見たことないよ」
「え、星乃町に住んで何年なのよ? 一度も見たことないの?」とキョウさんは目を丸くした。
「ここにいると打ち上げよりも面白いものが見られるからね」
そう言うとマサは老眼鏡を外し、折りたたんで胸ポケットにしまった。
「え、面白いものってなんだい?」キョウさんは体を揺らしながらマサの話に食いついた。
「あれはもう15年前だ」
そう言ってマサはレジで話し始めた。
15年前 2078年 ぺんぎん堂店主
あの時も雲ひとつない秋晴れでロケットが打ち上がった日だった。
打ち上げも終わり見物人たちも家路につき、町はいつものような静けさに戻った。日も傾きかけるとひとりの女の子が店に入ってきた。
まっすぐレジまで歩いてきた女の子はカウンターの下から私を見上げながら
「ろくさいの、おとこのこに、よんで、きかせたいほんが、ほしいです」と、一言一言を丁寧に言い終えた。
女の子は見るからに6歳の男の子より年下だった。年上の男の子に読み聞かせをしてあげようと背伸びする女の子を私はとても微笑ましく思った
「その男の子はどんなものが好きなのかな」と聞くと「パイロットになりたいって」と言った。
この町の子供たちの将来の夢はほとんどが宇宙飛行士かパイロットだ。
といっても、いまの日本では人口8000万人のうち16歳以下の人口は総人口の1割を割っていて子供を見かけることが珍しい。人口が減り続けた日本はいたるところで町を維持することができなくなり、昔は都道府県に分かれていた地域も州制になり合併を繰り返している。30年ほど前に国は経済とインフラを維持できなくなった地方都市に商業、製造、農業、情報といった専門の特区を定め、海外の企業や研究機関を積極的に誘致し始めた。特区に指定された星乃町はその昔「越乃町」という小さな港があるだけのなんの取り柄もない海の町だったが、いまでは宇宙科学開発特区として「星の町」として生きながらえている。すでに海外からの科学者、研究者、技術者とその家族が関連企業と共に1万人ほどこの町に根を下ろし、10年前に町名も越乃町から「星乃町」と変更した。比較的若い科学者やエンジニアが多いこの町は他の都市と比べても子供が多かった。だからこそ『ぺんぎん堂』という絵本の専門店を50年も続けられていたのだ。
パイロットに憧れる子供に勧める本はいつも決まっていた。『リンドバーグ』という大空に憧れるネズミの絵本だ。
「これはどうだい」
と私は女の子の前に絵本を差しだした。
女の子は目一杯に両腕を伸ばして本を受け取ると抱えるようにしてページをめくった。
「すこし自分で読んでもいいですか?」
私は「どうぞごゆっくり」と言って奥の読書テーブルを指差した。
女の子は窓を背にした席に腰かけるとテーブルに本を優しく置いてページをめくった。
「ねずみのものがたり なんねんもまえのこと、おおきなみなとまちに、しりたがりやのねずみがいた・・・・」
西日が窓から差し込み女の子を強く照らした。
女の子が言葉を区切るたびにページをめくる音がして、大きく息を吸い込んではまた新しいページを読み始める。そのリズムと、ゆっくりだが明瞭な声は私の耳にとても心地よかった。
私は仕事の手を止めて朗読を聴きながら女の子をしばらく眺めていた。
「・・・・ひこうきはとびだし・・・ちゅうにういた」
パタンと音を立てて女の子は本を閉じた。
途中で朗読が止んだことに少々落胆した私は「最後まで読んでもいいんだよ」と言った。
西日は深く傾き女の子を柔らかく照らしていた。
「このあとを読むのがもったいなくなっちゃった」といって椅子から降りた女の子は「これをください」と言って私に絵本を差し出した。子供専用の電子マネー、キッズペイカードで支払いをすませると、本の入った袋を手にして早足に店から出て行った。女の子のキッズペイにはHWANG YURIIという名前の刻印があった。
女の子は1年後に同じようにロケットの打ち上げがあった夕方に店にやってきた。
すこし背が伸びていてレジのカウンターからちょっとだけ顔を覗かせていた。そして1年前と同じく「6歳の男の子に読んで聞かせたい本をまた探しに来ました」と、小川の優しい水音のような声で流れるように言葉をつないだ。
私は1年前の朗読を思い出して嬉しくなった。
また6歳の男の子ということは昨年と違う子なのかなと思った私は
「今度の子はどんなものが好きなのかな?」と聞いた。すると「宇宙飛行士になりたいって」と言った。今度は宇宙飛行士になりたい子なのか。たまには消防士とか警察官とかに憧れてもいいようなものをと思いながら、星乃町の児童書専門店の定番絵本『アームストロング』を渡した。今度はネズミが月へと飛び立つ話だ。昨年の『リンドバーグ』につながるちょっとした仕掛けもあって、宇宙飛行士になりたい子供にはいつもこの絵本を勧めていた。
「そういえば去年の男の子は『リンドバーグ』を読んでもらってなにか言ってたかい?」と聞くと
「返事はまだこないの」と女の子の顔が曇った。
本を受け取った女の子は「またここで読んでもいいですか」と言った。
私は「もちろん!」といって奥のテーブルを指差した。
昨年と同じ窓際の席に腰を下ろしゆっくりと本を開いて朗読を始めた。
「星をみつめて。小さな手が、大きなぼうえんきょうのつまみをまわす・・・・」
私は1年ぶりの朗読を楽しんだ。
それから毎年の秋、ロケット打ち上げの日になると女の子は店に訪れては6歳の男の子に読み聞かせる絵本を買っていった。
そしてそれは15年続いた。
2078年 フアン・ユーリ
ユーリがガラス窓に両手をついて見下ろすと、足下ではたくさんの大人たちが机に座り手元のモニターを見ていた。正面の壁には大きなモニターが6枚もあった。数字や四角形や丸い形が色々な色で映し出されていたが、4歳になったばかりのユーリにはまだその意味はわからなかった。
「いち、に、さん、よん・・・」ユーリは大人たちを指差しで数えていた。
「じゅうよん、じゅうご・・・・」スピーカーから様々な声色が広々とした部屋に忙しく響きわたり、隣にいた母がユーリの手を握った。
「ママ、おとなのひとたちじゅうはちにんいるよ」とユーリが言うと、「そうね」と言ってユーリの頭をもう一方の手で撫でた。
「フアンさん、もうすぐです」と黒い服を着た男性が母に声をかけてきた。
「大丈夫です。もう今回の実験で13回目です。無事に打ち上がりますよ」
「もちろんよ」
そう言って母は笑った。
館内に甲高いアラームが鳴り響いた。そして女性の淡々とした口調で放送が続いた。
“内部電源切り替え”
“イグニッション点火”
“全システム準備完了”
“メインエンジン点火”
“リフトオフ”
母に握られていた右手がきつく締め付けられて痛かったがユーリはなにも言わなかった。握られた手が汗で濡れてきたのを感じて母の顔を見上げると、ユーリの視線に気付いた母は「ユーリ、パパとルイのほうを見て」と言って正面の大きなモニターを指差した。管制室の大きな画面に視線を戻すと、ロケットがゆっくりと地面から浮き上がっていた。青い空にクレヨンで描いたような白い線を引きながら昇っていくロケットをユーリはモニター越しに眺めていた。画面いっぱいに映ったロケットが徐々に小さくなり、しばらくすると真っ青な空に力の抜けた白い煙が糸くずのように漂っていた。
管制室の大人たちが笑いながらお互いの肩を軽く叩き握手するのが見えると、ユーリの手を握っていた母の手からすっと力が抜けた。母は近寄ってきた大人たちと何度も握手を交わした。周りの大人たちは嬉しそうにしていたけれど母の表情はなぜか悲しそうだった。それでも室内の空気が明るくなるのを感じたユーリはパパとルイが無事に宇宙へ辿り着いたことを理解した。
先ほどの男性がまた母に近づいてなにかを話していた「今後の実験のスケジュールですが、3ヶ月かけて光速の10分の1の速度まで加速して・・・・」
大人たちの忙しない喋り声を背中にユーリは管制室を見下ろす窓ガラスに両手をつき、正面の大きなモニターに映し出された青い空をいつまでも眺めていた。
* * *
「ユーリ、パパとお兄ちゃんに会えるのは15年後よ」
宇宙センターからの帰り道、車の窓の外を後ろへと流れていく海岸をユーリは助手席から眺めていた。
「15年? どのくらい?」窓の景色から運転席の母のほうへユーリは体ごと向き直した。
「ユーリは19歳ね。その時はもう大人。ママはもうオバさんね」
「じゃあ、じゃあ、お兄ちゃんも大人でパパはおじいちゃん?」
母は笑ったが、泣いているようにも見えた。
「ううん、ルイもパパも今日のまま」母は鼻をすすりながら言った。
「今日のまま?」
「そう。私たちの思い出のままで15年後にまた会えるのよ」
「そんな長くパパといたらお兄ちゃん寂しくならないかな」
「パパとルイはそんなに長く感じないのよユーリ。けど・・・そうね、ルイは寂しがり屋だからユーリがルイに絵本を読んで聞かせてくれる?」
「お兄ちゃんに絵本を届けるの?」
「絵本は届けられないけど、一年に一回、宇宙(そら)に声は届けられるんだって」
「じゃあ、じゃあ、本屋さんに絵本を買いに行かないとね!」
母はユーリの肩に左手を回して自分の元へ引き寄せて、それから頭にキスをした。
そしてまた左手でユーリを強く抱きしめた。
母に抱かれたユーリが前を見ると、その先には星乃町が青空の下に蜃気楼のように揺らめいてユーリにはクレヨンで描いた絵のように見えた。
現在 2093年 ぺんぎん堂
「じゃあ、じゃあ、こんどはこれ読んで!」と奥のテーブルの男の子が大声で叫んだ。
「また? ほんとうにこの本が好きなのね」
「絵があるともっと面白いね!」
キョウさんと店主は大声に驚いてテーブルのほうを覗いた。
少年の横で静かにページを開いた女性は小さく息を吸い込んだ。
少年は膝に手をついて本に顔を近づける。
「ねずみの物語。何年も前のこと、大きな港の町に、知りたがりやのねずみがいた・・・・」
言葉を区切るとページをめくった。そして小さく息を吸い込んではまた新しいページを読み始める。読み聞かせの心地よいリズムが静かな店内を満たした。
それは15年変わらない朗読だった。
「マサさん、もしかしてあの子」
店主は口に人差し指をあててキョウさんに黙るように言った。
「キョウさんは運がいい。これがロケットよりも良いものだよ」
キョウさんと店主の二人は静かにその朗読に耳を傾けた。
「・・・・飛行機は飛び出し・・・宙に浮いた」
ルイは勢いよく両手を上げた。
「ここ大好き!」とまた叫んだ。
ユーリは笑いながらページを開いた本を持ち上げた。
「お兄ちゃんと同じ、私もここが一番好き」

<児童書専門書店「絵本のペンギン堂」今回のはなしの2冊>
『リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険』トーベン クールマン 著/金原 瑞人 訳(ISBN:9784893096005)
『アームストロング 宙飛ぶネズミの大冒険』トーベン クールマン 著/金原 瑞人 訳(ISBN:9784893096289)
※このお話はフィクションです。登場人物、物語などは実際の出来事ではありません。