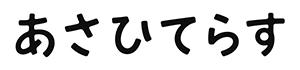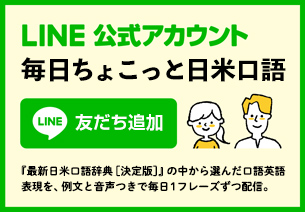第8回 レンジを広くとる
ブルボン小林さんの連載、「グググのぐっとくる題名」。小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第8回は、実写映画化も決定した、銭湯で働く吸血鬼が主人公の漫画と、先月発表の第172回芥川賞を受賞した小説の題名を取り上げます。(編集部)
ファミレスで筆者が一番好きなメニューは「チーズinハンバーグ&甘エビクリームコロッケ」だ。恥ずかしい。弁当屋で好きなのは「生姜焼き&とんかつ弁当」。恥ずかしい。こないだ家で「塩焼きそばとソース焼きそばのハーフ&ハーフ」を作った。我ながらバカみたいだと思う。
友人に「皆が好きな食べ物はハンバーグとかコロッケだけど、ブルボンさんが好きなのは『&』ですね」と言われた。
ハンバーグが、とか、生姜焼きが、ではない、一度にいろいろ食べたい。食べたかろう、という欲からの逆算が、弁当やメニューの品名に露呈していて、まんまと釣られる自分がいる。
そういう「どちらも取りにいく」というのは必ずしも成功するとは限らないが、うまくすればスパークするはずだ、題においても! 今回は「レンジを広くとる」という話。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!