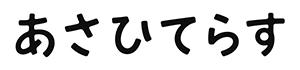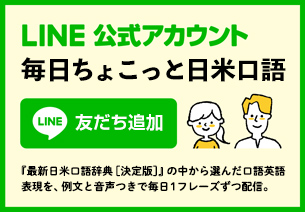第11回 題の中を時間が流れる
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第11回に取り上げるのは、中島らもの名小説と、大槻ケンヂ率いるバンドのアルバム、デジカメ情報マガジンのユニークな連載の題名です。(編集部)
ハチドリが花の蜜をすう写真がある。カメラのシャッタースピードを示す例で、奇麗に静止しているでしょ、ということをみせるための写真だ。
ほとんどその(カメラの性能を表す)ときしかハチドリをみない。なんか言いたいんじゃないかと思う(ハチドリが)。またそれですか、みたいな一言を。
しかし、そのように空を飛んでいる鳥を撮った写真をみるとき、その鳥が静止していると人は考えない。写真は絶対に止まっているのに、だ。その前も飛んでいただろうし、その後も飛んでいく姿を我々は感じ取る。
それ自体が静止していても、人は動きを感じ取る。題名においてもそれがある、という話。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!