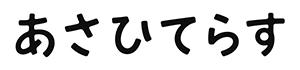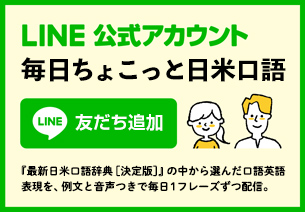第12回 題名の賞味期限
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第12回で取り上げるのは、公開以降「題名」界の流行にもなった映画と、人気特撮作品のすぐれたパロディ作品の題名です。(編集部)
1982年に「ホテルニュージャパン火災」があった。33名が亡くなった痛ましい事件だ。その後、もちろんホテル全体の防災対策の意識は高まって杜撰な管理による人災は減っていったと思うが、同時に、ニュージャパンというような名称のホテルもなくなっていったと思う。当時はあちこちの建物につけられていた「ニュー」が(火災のせいではなかろうが)古び、みるみる色褪せていったのだ。題名にもそういうことはある。今回は「題名の賞味期限」という話。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!