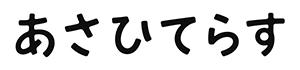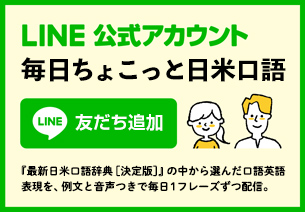第9回 題を題につける
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第9回に取り上げるのは、2015年公開の映画『バクマン。』の主題歌と、2018年公開の『映画ドラえもん のび太の宝島』の主題歌の曲名です。(編集部)
刑事コロンボの愛犬の名は「ドッグ」だ。原文でもdogらしい。大昔に読んだ小説版では、dogを「犬っころ」と訳している人もいた。
コロンボを楽しんでいる者からすると、犬をドッグと呼ぶのが実に彼らしいと思うが、犬っころかもしれない。どっちなんだろうと悩む。
犬を犬と呼んでいたら、それは「名付けてない」ということだ。
日本人が「ドッグ」とカタカナの名を付けたら、それは諧謔のある命名だが、コロンボはイタリア系移民だ。さてどんなつもりだったんだろう。今回は「名付けていない名付け」ということが題にもある、という話。
|
本連載は加筆・改稿のち書籍化しました。( |
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!