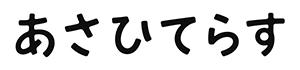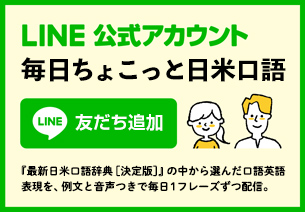第十五回 遊びの現象学(後半)――ルールのない〈遊び〉
遊びの現象学(後半)――ルールのない〈遊び〉
西村は『遊びの現象学』で遊びに共通の骨格を提唱する。だが、彼が唱える遊びの骨格をもたない〈遊び〉がある。というのも、〈子ども〉は一人で一回だけ遊べるからである。
まず、〈子ども〉は、期待があっても、それを誰とも共有しないかもしれない。たしかに、西村が言うように、誰かと一緒に遊ぶには[65]、同じ一つの期待が共有され宙づりにされなければならない[66]。共に遊ぶものは、「宙づりにされた期待の遊隙」の中で、「相手がどうくるか、それにどう応えるかを、おたがいに予期し了解しあう」[67]からである。だが、〈子ども〉は期待を宙づりにしておけない。期待の充実が待ちきれないのである。そのため、〈子ども〉は、遊ぼうと思ったときには、――あるいは、そんなことを思う間もなく、気がついたら、――すでに遊んでしまっている。そんな〈子ども〉と期待を共有できる大人はいない。だから、〈子ども〉は一人で遊ぶのである。
また、〈子ども〉は、(自然)世界が同調しようと、それを反復しないかもしれない。たとえば砂の同調がなければ、むろん〈子ども〉は砂を遊べない[68]。しかし、そこに「同調された反復的な遊動」はありえない。というのは、期待が宙づりにされないなら、そもそも何の反復の余地も生じないからである。たしかに、たとえばバウンサー上の赤ちゃんでさえ、「上昇しては、反転して、またかならず降下してくる遊動の往還」[69]を楽しむことはあるかもしれない。だが、期待を宙づりにしておけない〈子ども〉は、行きつ戻りつする「遊動」に身を任せていられない。だから、そんな〈子ども〉はバウンサーの上昇以上に飛び跳ねる。(あるいは、下降以上に反り返る。)しかし、これもまた〈遊び〉である。期待の充実へと突き進むだけの「遊動」である。〈子ども〉は行くだけの〈遊び〉を遊ぶことができる。すなわち、一回だけの〈遊び〉を遊べるのである。
かくして、一人きりの一回だけの〈遊び〉がありうることになる。だが、どうしてそれが〈遊び〉なのだろうか。なるほど、西村によれば、どんな遊びであれ、それが遊びであるなら、「それを遊びたらしめている(…)共通の単純な骨格」[70]が見いだせる。だから、彼は、遊びの「もっとも単純な骨組み」として、「宙づりにされた期待の遊隙」と「同調された反復的な遊動」を標榜するのである。――もちろん、遊びの(様態を支える)共通の構造として、さらに「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」と「遊ぶものと遊ばれるものの役割交替」を加えてもよい。――しかし、〈子ども〉の一人きりの一回だけの〈遊び〉には、西村の掲げる、遊びの共通の骨格がないのである。にもかかわらず、それが〈遊び〉であるのはなぜなのか。
ところで、それが一人きりの一回だけのものであるのなら、それはルールのない〈遊び〉であることになる。なぜなら、ルールとはそもそも一般的なものだからである。つまり、ルールには複数人ないし複数回の適用が最初から前提されている。だから、単発的なルールというものはそもそもありえない。だから、一人きりの一回だけの〈遊び〉にはルールがない。
でも、遊びにルールがないことなんて本当にあるのだろうか。たとえば、ホイジンガによれば、「どんな遊びにも、それに固有の規則がある」[71]。だから、第七回の連載で見たように、彼(とカイヨワの)遊びの定義には、規則に従うことが含まれる。たしかに、すぐに思いつく遊びにはルールがある。カードゲームやボードゲームはもちろん、ワードゲームや(e)スポーツを含む、あらゆるゲームには必ずルールがある。――おそらく、私たちがすぐにルールのあるゲームを考えてしまうのは、それぞれのゲームには、固有のルールがあるがゆえに、固有の名前があるからである[72]。――さらに、――特に決まった呼び名があるわけではないが、――友人と食事をしながら会話を楽しむこと、気ままに一人で街をぶらつくこと、バーでおいしいお酒を教えてもらうこと、SNSや動画をとりとめなく見ることにも、それぞれ固有のルールが暗黙にある、と考えられる。というのも、どんな遊びであれ、それに固有のルールが破られてしまえば、そもそもそれで遊ぶことにならないからである[73]。
西村は、遊びのルールについて、次のように述べている。
(…)遊びのルールとは、ふつう「遊びかた」ということばで理解しているようなものにもっとも近い(…)。遊びかたとは、個々の行動の手順の指定であり、ルールにしたがうとは、不法行為をさしひかえることではなくて、遊びかたの指示どおりに遊ぶことである。それは、責務を課すルールではなく、おもしろい遊びをなりたたせ現出させる手順である。[74]
たとえば、規則から外れた駒の動かし方をするのなら、それだけで将棋にはならないし、あるいは、必要な買い物だけをするのなら、気ままにぶらつくことにはならない。だから、この意味では、「(…)ルールのない遊びというものは、考えることができないくらいである」[75]。どんな遊びも、その遊び方に従うことで、その遊び自体が成り立つからである。すると、西村が(心理学者のガーヴェイを拠り所として)言うように、「そもそもルールのない遊びというようなものは存在しない」[76]のだろうか。
いや、カイヨワの「パイディア」の(極にある)遊びはどうだろうか[77]。なるほど、彼の考える「パイディア」の遊びは、「即興的で不規則的という特徴が(…)その本質なのだ」[78]から、むしろ規則的ではありえないのかもしれない。だが、彼が「パイディア」の極に置く遊びにはルールがあるように見える事例も少なくない。たとえば、「パイディア」に置かれる「偶然(アレア)」の遊びは「じゃんけん」であるが[79]、「じゃんけん」にルールがあることは明らかである。また、空想的な「まねっこ」は「パイディア」とされる「模倣(ミミクリ)」の遊びであるが[80]、西村によれば、少なくとも「ごっこ遊び」には「(…)はっきりと、各人がどのようにふるまい、なにをしなければいけないか、なにをしてはいけないかについてのとりきめ、すなわち、あらかじめきめられた遊びの形式と、一定のルールがある」[81]。というのも、たとえば、ティラノサウルスとトリケラトプスの「まねっこ」をしているのに、互いに空を飛ぼうとしたり、後者が前者を捕食しようとしたりしてしまっては、そもそもそれらの「まねっこ」にならないからである[82]。さらに、同じことは「パイディア」とされる「競争(アゴン)」の遊びについても言える。たとえば、規則のない「取っ組み合い」をカイヨワはそこに置いているが[83]、それが「取っ組み合い」の――争いでなく――遊びであるのなら、まずはティラノサウルスが襲い掛からなければならないが、次にはトリケラトプスも応戦し簡単にやられてはならないのである。というのは、もちろん、さもなければ、「取っ組み合い」の遊び自体が成り立たなくなってしまうからである[84]。
それゆえに、――第七回の連載で見たように、――結局カイヨワにとっても遊びは「規則のある活動」と定義されることになる[85]。だが、先に述べたことは、何も遊びについてのみ言えるのではない。というのは、たとえば、仕事として真剣に対局する棋士もまた、将棋ということ自体を成り立たせているルールを破るのであれば、そもそも将棋をしていることにはならないからである。ようするに、それが何であろうと、――したがって遊びでなかろうと、――それ自体を成り立たせているルールが破られるなら、それが為されることにはならない。これは遊びにだけ当てはまることではない。だから、もちろんルールを守るだけで遊べるわけではなく、遊びにはさらに「遊戯的態度(lusory attitude)」が必要になる[86]。たとえば、各駒の動かし方のような個々のルールに従っているだけでは、なお将棋で遊んでいることにはならず、さらにまさに将棋で遊ぼうとされなければならない[87]。しかし、そもそも、遊ぼうとするということは、何をすることなのか。一体どうしたら、何であれ、何かで遊ぶことができるのか。
もちろん、たとえば将棋であれば、それはまさに将棋として遊ばれなければならない。そのため、個々の駒の動かし方などのルールを守るだけでなく、そもそも相手より先に王将をとろうとしなければならない[88]。これもまた将棋のルールである。むろんこれは、将棋の中で個々の行動を規制するために「構成されたルール」でなく、それがどんなゲームであるのかを「前提的な(prelusory)目標」によって定義する[89]、まさに将棋ということを「構成するルール」である[90]。だが、西村によれば、ゲームにおいてはこれらのルールはひとつなのである[91]。というのも、「ゲームのルールとは、まさにそのゲーム行動の目的を指定し、また、個々の行動を、この目的へと一義的に動機づけるものだからである」[92]。
とはいえ、たとえば、名人戦に臨む棋士は、まさに将棋をしているが、けっして遊んでいるわけではない。なぜなら、彼らにはいわば「遊戯的態度」が欠けているからである。すなわち、彼らはそもそも遊ぼうとしていないのである。では、彼らは一体どうしたら将棋で遊ぶことができるのか。この問いに対する西村の答えは明快である。つまり、彼によれば、「勝敗を競いあう形式をもったゲームが、しかも遊びであるとは、その行動の本質が、勝利をめざす企てよりも、それを遊び行動として内的に構成している、遊び関係と遊動にある、ということを意味する」[93]のである。
たとえば、プロの棋士は、勝って賞金を得るために対局するかもしれないし、アマチュアを指導するために対局するかもしれない。また、将棋ファンとの交流を深めるための対局もあるだろうし、自らの将棋の研究と鍛錬のための対局もあるだろう。だが、遊びが自己目的的であるのなら、遊び以外のために指される将棋は、すべて遊びの将棋ではありえない。なぜなら、それらはすべて他に目的があるからである。それゆえに、遊びの将棋は、まさに遊ぶためだけに指されなければならない。そして、西村によれば、「遊びが自己目的的であるとは、(…)遊びが遊び関係と遊動からなる、遊びの構造の実現を目指している」[94]、ということなのである[95]。
なるほど、遊ぶという態度は、まさに遊ぼうとすること、つまり遊びの実現を目指すことなのかもしれない。だが、目指される実現は、遊びの構造でなければならないのだろうか。遊ぼうとするものは、本当に、西村の唱える、遊び(の様態を支える共通)の構造の実現を目指さなくてはならないのだろうか。もしそうだとしたら、遊びの構造(の骨格)がないことは、遊びにはなりえないことになる。しかし、そもそも遊びとは「人間行動のいたるところに見いだされる」ものではなかったか。第三回(と第十二回)の連載に書いたように、およそ何であれ、それが遊び(の存在様態)でされるのなら、何でも遊びですることができるのではなかったか。おそらく、西村もまた、それが遊びの様態で為されるのなら、何であれ遊びで為される、と言ってくれるだろう。しかし、彼によれば、遊びの様態とは、まさに遊び(に共通)の構造に支えられるものである。すると、一人きりの一回だけの〈遊び〉はやはり彼にとっては遊びでないことになる。というのも、――もちろんそこには遊びの構造の骨格がないのだが、――彼に倣うのなら、遊びの構造の骨格をもたないことは、遊びの様態にあることができず、したがって遊びにはならないことになってしまうからである。
たしかに、一人きりの一回だけの〈遊び〉には、「宙づりにされた期待の遊隙」も「同調された反復的な遊動」もないので、遊びの構造の骨格もない、と言わざるをえない。だから、それはもちろん西村の考える遊びではない。しかし、それはなお〈遊び〉でありうる。なぜなら、それは、それが何であれ、それ自体の実現を目指すからである。この意味でそれもまた(さらに?)自己目的的なのである。したがって、このことから、それもまた〈遊び〉である、と言えるなら、ルールのない〈遊び〉があることになる[96]。というのも、一人きりの一回だけのルールというものはありえないが、それは一人きりの一回だけの〈遊び〉だからである。
とはいえ、もちろんそれは遊びの骨格のない〈遊び〉である。期待を宙づりにし行きつ戻りつする遊びでなく、期待の充実へ行くだけの〈遊び〉である。しかも、それは期待したときにはすでに充実している〈遊び〉である。それは、充実しかない〈遊び〉であり、たんなる実現の〈遊び〉である。
[65] そもそも、西村にとっては、遊ぶということは、人であれ物であれ、「なにものか『と・遊ぶ』」(西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,27頁)ということである。
[66] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,37-38頁.
[67] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,45頁.
[68] たとえば、西村は、物で遊ぶことについて、「わたしが戯れかかるのに応じて、ものの方でも遊びをかえさなければ、わたしは遊びつづけることができなかった」(西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,47頁)、と書いている。とはいえ、もちろん彼が論じているのは、物「と・遊ぶ」ことであって、物「を・遊ぶ」ことではない。
[69] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,53頁.
[70] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,36頁.
[71] ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』高橋英夫訳,中公文庫,2021年6月5日,39頁.
[72] つまり、そのルールさえ守られていれば、いつどこで誰にどのようにプレイされるとしても、そのゲームであることになるので、それらをまとめて同じ一つのゲームとしてくくるための名前である。
[73] 現代のゲーム研究の中心人物であるミゲル・シカールもまた、「あらゆる遊びの文脈は、なんらかの意味でのルールを含んでいる」(シカール,ミゲル.『プレイ・マターズ:遊び心の哲学』松永伸司訳,2021年5月20日,25頁)、と考えている。なぜなら、「遊びはルールから生まれ、ルールによって媒介され、ルールを通して位置づけられる」(シカール,ミゲル.『プレイ・マターズ:遊び心の哲学』松永伸司訳,2021年5月20日,25頁)からである。
[74] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,310頁.
[75] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,278頁.
[76] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,222頁.
[77] カイヨワの定める遊びの二極については第七回の連載を参照のこと。
[78] カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,68頁.強調傍点引用者。
[79] カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,81頁.
[80] 実際の『遊びと人間』の表には「子供の物真似」と書かれている(カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,81頁)。
[81] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,222頁.
[82] なお、カイヨワは、(厳格な)規則のない「ごっこ遊び」では、他の何かになりきって、それをなぞらえる楽しみが、規則のような機能を果たしている、と述べている(カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,37-38頁.)
[83] カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,81頁.
[84] もちろん同じことは「パイディア」の極におかれる「眩暈(イリンクス)」の遊びについても言える。たとえば、回らずに真っ直ぐ進んでしまったり、そもそも立ち止まったりしてしまったら、ただぐるぐると回って遊ぶことさえできないのである(Cf. カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,81頁)。
[85] 第八回の連載で見たように、カイヨワが『遊びと人間』で目論むのは、「遊びを出発点とする社会学の基礎づけ」である。すなわち、彼によれば、私たち人間(社会)の文化の運命は、どのような遊び(のカテゴリー)を選んでいるかによって、決まってくるのだが(Cf. カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,123-124頁)、「ルドゥス」こそが「文化的効力と豊饒性という点で、最も際立ったもののように思える」(カイヨワ,ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,77頁)のである。
[86] Cf. シカール,ミゲル.『プレイ・マターズ:遊び心の哲学』松永伸司訳,2021年5月20日,25, 168頁.なお、スーツによれば、「遊戯的態度(lusory attitude)」とは、「構成的ルールを受け入れることで可能になる活動を成立されるためだけに構成的ルールを受け入れることである」(スーツ,バーナード.『キリギリスの哲学:ゲームプレイと理想の人生』川谷茂樹・山田貴裕訳,ナカニシヤ出版,2015年4月16日,36頁)。
[87] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,294-297頁.
[88] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,294-295頁.
[89] 「前提的な(prelusory)目標」はスーツの用語である(スーツ,バーナード.『キリギリスの哲学:ゲームプレイと理想の人生』川谷茂樹・山田貴裕訳,ナカニシヤ出版,2015年4月16日,32頁)。
[90] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,285-297頁.
[91] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,287, 297頁.
[92] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,297頁.
[93] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,315頁.
[94] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,319頁.
[95] すると、――もちろん、企てにおいても、何であれ、それを成り立たたせているルールが守られなければ、それをすることにはならないが、――遊びにおいては、何であれ、それを成り立たせているルールに従うことだけが目的であることになる。というのも、そうするだけで、まさにそれは実現されるからである。しかし、遊び以外の企てにおいては、他にも何らかの目的があるのだから、それを成り立たせているルールに従うことだけが目的ではないのである。
[96] かつて私はいわゆる「アカデミックな哲学」と対比して「遊びのような哲学」を提案したことがある(成田正人『なぜこれまでからこれからがわかるのか―デイヴィッド・ヒュームと哲学する』青土社,2022年9月28日,14頁)。だが、この「遊びのような哲学」がまさに〈遊び〉のような哲学であるのなら、これに対し「遊びの哲学のルールを示して欲しかった」(高萩智也「成田正人『なぜこれまでからこれからがわかるのか―デイヴィッド・ヒュームと哲学する』(青土社、2022年)書評」『フィルカル―分析哲学と文化をつなぐ』Vol. 8 No. 1,2023年4月30日,409頁)という声があるとしても、残念ながらそれを示すことはできないことになる。というのは、もちろん〈遊び〉にはルールがないからである。〈遊び〉のような哲学には、――それが哲学であるのなら、哲学を成り立たせているルールはあるだろうが、――遊び(の構造)を成り立たせているルールがないからである。