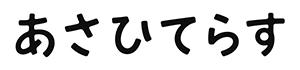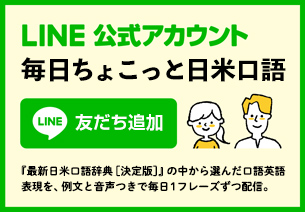第十四回 遊びの現象学(後半)――一人きりの一回だけの〈遊び〉(後半)
遊びの現象学(後半)――一人きりの一回だけの〈遊び〉(後半)
前回の話が少し入り組んでしまったので整理しておきたい。おそらく、そうすることで、一回だけの〈遊び〉の姿もまた浮かび上がるだろう。
たとえば、私が二歳の〈子ども〉と砂場で遊べなかったのは、私たちの間に「宙づりの期待」の共有がなかったからである。すなわち、西村の提唱する遊びの共通構造に倣うなら、「宙づりの期待」の共有なしには、一緒に遊ぶことはできないのである。だが、私たちが「宙づりの期待」を共有しなかったのは一体なぜなのか。可能性は三つある。
一つ目は、私には「宙づりの期待」があったが、〈子ども〉がそれを共有しなかった、という可能性である。その日、私は、公園に着く前から、一緒に砂場で穴を掘ったり池を作ったりして遊ぼう、と考えていた。しかし、彼は、一人で穴を掘り始めたし、私の掘った穴には見向きもしなかった。池は、私が一人で作ったし、彼に砂で埋め立てられた。明らかに私は遊ぶのが下手である。西村によれば、「(…)わたしに遊びがおとずれるかどうかは、わたしの意志や企てによってねらわれた目的ではない」[54]。だが、私はまさに彼との遊びを企てたのではないか。私は彼「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」を築きたかった。しかし、西村(とボイテンデイク)によれば、遊びとは「ひとつの『僥倖(Beglückung)』」[55]である。つまり、私がそれを狙ったところで、運よく彼に遊んでもらえなければ、それは私のところには現れない。私たちは、幸運に恵まれなければ、遊べないのである。西村曰く、「いっさいの遊びは、原理的には、遇運との戯れである」[56]。遊べるということは、幸運の女神がほほえむということなのである[57]。しかし、その日、〈子ども〉は私にほほえまなかったのである[58]。
だが、こうした遊びの失敗は、誰との間にも起こりうるものである。つまり、それは私の遊び相手が〈子ども〉であったから、起こった失敗でなく、たとえば、私が妻と遊ぼうとしても、妻が忙しいときには、起こりうる失敗である。というのは、大人であれば、――すなわち〈子ども〉でなければ、――誰にでも、遊べないときがあるからである。遊べない人と遊ぼうとしても、遊べないのは明らかである。
しかし、〈子ども〉には遊べないときなんてないのではないか。ここに二つ目の可能性が開かれる。すなわち、それは、〈子ども〉には「宙づりの期待」があったのだが、私がそれを共有できなかった、というものである。〈子ども〉は、たんに遊ぼうとしていたのでなく、まさに遊んでいたのである。なるほど、そのとき彼には何らかの期待があったのかもしれない。だが、そうだとしても、たしかに私にはそれは共有できなかった。なぜなら、彼は、子どもではなく、〈子ども〉だったからである[59]。すなわち、大人である私には一緒に彼の〈遊び〉が遊べなかった。大人には〈子どもの遊び〉は遊べないのである。たとえば、彼は、きれいな水が入ったバケツに、何のためらいもなく砂を入れる。しかも、その水は私が砂場に池を作るために汲んできたものである。そんな〈遊び〉ができる大人が本当にいるだろうか。あるいは、他の人に砂がかかるのに、砂を空中にばら撒ける大人がいるだろうか。もちろんいないだろう。そんな〈遊び〉が遊べるのは〈子ども〉だけである。他の人が作った池をすぐに泥で埋め立ててしまう大人はいない。大人は〈子ども〉のようには遊べない。だから、私は彼と遊べなかったのである。とはいえ、彼がそのとき遊んでいなかったわけではない。むしろ彼は間違いなく遊んでいた。彼は、バケツの水に砂を入れたり、砂を頭上からばら撒いたりした。私の作った池に砂を入れ続け、砂場を泥だらけにもした。一体これが〈遊び〉でなくて何であろうか。これは〈遊び〉でしかないのではないか。
だが、彼が遊んでいたとしたら、それはいかなる〈遊び〉だったのだろうか。なるほど、西村なら、それは砂との遊びである、と言うかもしれない。しかし、(比喩的な意味でなければ)砂に彼の期待が共有できるとは思えない。そもそも、物は、人と違って、何も期待しないからである。それゆえに、彼は砂と遊んだのでなく、砂を遊んだのである、とここでは言いたい。というのも、「宙づりの期待」を共有し、「と・遊ぶ」関係を築けるのは、まずもって、物でなく、人だからである。だから、もちろん、がらがらを振る母は子と遊んでいる、と言えるし、そのときには子もまた母と遊んでいる、と言える。しかし、母はけっしてがらがらとは遊んでいないし、ましてがらがらは母とは遊んでいないのである。だが、子はがらがらと遊んでいるのではないか。西村なら、そう考えるかもしれない。しかし、がらがらは人とは遊ばない。なぜなら、それは物だからである。遊ぶのは、物ではなく、人だからである[60]。すなわち、〈子ども〉ががらがらを遊んでいるのである。
では、それはどのような〈遊び〉なのか。もちろんそれは〈子どもの遊び〉である。つまり、それは、大人でも遊べる人間(社会)の遊びでなく、〈子ども〉にしか遊べない自然(世界)の〈遊び〉である。〈子ども〉は(人間)社会の外で(自然)世界を遊ぶのである。すると、たしかに砂はむしろ私よりも自然(世界)の一部である。大人である私は、砂と違って、人間(社会)の一員でもあるからだ。とはいえ、砂が彼と期待を共有するはずはない。物である砂はそもそも何も期待しないからである。だが、すると、期待が共有されていなくても、――つまり砂が彼「と・遊ぶ」のではないとしても、――一緒に遊ぶことはできるのだろうか。〈子ども〉が砂を遊ぶとき、――西村の用語法とは異なる意味で、――〈子ども〉は砂と遊んでいる(とも言える)のだろうか。
たしかに、〈子ども〉が遊ぶ砂もあれば、遊ばない砂もある。彼に掬われ、バケツに入れられた砂は、彼に遊ばれる砂であるが、彼が見向きもしない、砂場の端に溜まった砂は、彼に遊ばれない砂である。では、前者の砂と〈子ども〉の間には、何が起こっているのだろうか。なるほど、もしかしたら、そこには(ふれあいと)同調はあるのかもしれない。というのも、〈子ども〉が遊ぶ砂は、(彼に直接ふれられ、)彼に自在に遊ばれるからである。たとえば、彼に遊ばれる砂は、――急に固まってしまったり、突然ドロドロに溶けたり、勝手に消えたりしないで、――彼の一挙手一投足に従って、宙を舞って私の目に入ったり、バケツの水を茶色く濁らせたり、泥となって池を埋め立てたりする。まさしく砂は彼の〈遊び〉に同調しているのである。さもなければ、〈子ども〉は自在に砂を遊べないだろう。
だが、砂が従っているのは、〈子ども〉というよりは、むしろ自然法則であるのではないか。そう思われる方もいるかもしれないが、もちろんそうとも言える。しかし、そうだとすれば、砂はまさに〈遊び〉で自然法則に従っているのである。そもそも、〈子ども〉は、人間(社会)の一員でなく、自然(世界)の一部である。また、当然、砂も自然(世界)の一部である。だから、それらは互いに〈遊び〉で同調できる。すなわち、一緒に遊べるのである。もちろん、もし仮に、私もまた〈子ども〉であったなら、それらと一緒に遊べたにちがいない。すると、むしろ――大人にも遊べる現象学的な遊びでなく――〈子ども〉にしか遊べない形而上学的な〈遊び〉において、自然(世界)と遊ぶことはできるのかもしれない。その(西村の用法から離れた)意味では〈子ども〉はすべてと遊ぶのである。しかし、「と・遊ぶ」の意味が西村の用法で解されるならば、やはり〈子ども〉はすべてを遊ぶと言うべきであろう。
まだ可能性は残されている。つまり、〈子ども〉にはそもそも「宙づりの期待」がなかったのかもしれない。これが三つ目の可能性である。だとしたら、私にそれが共有できるはずはない。共有されるべき期待がそもそもないからである。とはいえ、「宙づりの期待」なしに遊ぶことはできるのだろうか。もちろん、西村なら、そんなことはできない、と言うにちがいない。というのも、彼によれば、「宙づりにされた期待の遊隙」の内に「同調された反復的な遊動」は生じるからである[61]。たしかに、期待があるということが、いまだ充実されない不在があるということであるのなら[62]、どんな遊びにも何らかの期待はあるのかもしれない。というのは、――何をしても遊べるとはいえ、――何かをしなければ遊べないのであれば、何かをして遊ぶことによって、どうしても何らかの不在が満たされうるからである。だが、仮に〈子ども〉に何らかの期待があるとして、〈子ども〉がそれを宙づりにしておけるだろうか。むしろ〈子ども〉はそれをすぐに充実させてしまうのではないだろうか。(それゆえに、それは、実のところ、「期待」とも言い難く、言わば「すでに充実している期待」である。〈子ども〉は、気がついたときには、もうやってしまっているのである。)もちろん、大人であれば、――たとえば「いない・いない」と言って隠れ続ける母のように、――あえて期待を宙づりにしておくことができる。そして、――たとえば顔の一部だけを少し見せてはまた隠れてしまうように、――その遊隙の内で遊動を繰り返すことができる。しかし、〈子ども〉にそれができるだろうか。〈子ども〉はすぐに「ばあ」と言って出てきてしまうのではないだろうか。〈子ども〉はがらがらを鳴らしまくってしまうのではないだろうか。もちろん、それができなければ、大人との「役割交替」はできない。しかし、大人と「役割交替」ができるのは、もはや大人になった子どもなのである。大人にならない〈子ども〉には、そんなことはできっこない。
しかしながら、〈子ども〉が遊べないわけではもちろんない。〈子ども〉は、期待を共有されなくても、もちろん遊んでいる。〈子ども〉は一人で遊べるからである。たしかに〈子ども〉にも何らかの期待はあるだろう。けれども、それを宙づりにしておくことは〈子ども〉にはできない。というのも、〈子ども〉は常に遊んでしまっているからである。すなわち、〈子ども〉は、遊ぼうとするときには、すでに遊んでしまっている。だから、〈子ども〉の期待は充実されないことがない。言うなれば、それは、期待されるときには、すでに充実してしまっている期待である。〈子ども〉には遊べないということがありえないのである。
したがって、〈子ども〉が遊ぶとき、そこには「遊隙」がないことになる。しかし、それはやはり〈遊び〉なのである。なぜなら、そこには「遊動」があるからである。むしろ〈子ども〉は「遊動」を抑えられない。だから、期待を宙づりにしておけないのである。とはいえ、〈子ども〉のそれは「同調された反復的な遊動」ではない。なぜなら、そこには、「遊隙」がなく、それゆえに反復する余地がないからである。たしかに(自然)世界は〈子ども〉の「遊動」に同調するかもしれない。さもなければ、〈子ども〉は(自然)世界を遊べなくなってしまうからである。だが、「遊隙」のない〈子ども〉の「遊動」は反復的ではありえない。すなわち、それは、行きつ戻りつする往還的な「遊動」でなく[63]、期待の充実へ向かうだけの一回かぎりの「遊動」である。それは、たとえば、いきなり「ばあ」と現れるだけの〈遊び〉であり、突然がらがらを鳴らすだけの〈遊び〉である。こうした〈遊び〉はきっと大人には遊べない。大人には、何が楽しいのか、まったくわからない。しかし、〈子ども〉は唐突にバケツに砂を入れるだけで遊べるのである[64]。このとき大人は驚き戸惑うことしかできない。しかし、〈子ども〉は一人で(自然)世界を遊んでいるのである。それは、「遊隙」なき〈遊び〉であり、それゆえに一回だけの〈遊び〉である。そこには期待の充実への「遊動」しかないからである。おそらくこれが〈子どもの遊び〉である。〈子ども〉は一人きりで一回だけの〈遊び〉を遊べるのである。
[54] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,102-103頁.
[55] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,103頁.
[56] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,319頁.
[57] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,333頁.
[58] もちろん、私は砂と遊ぼうとは思ってもいなかった(ので、砂も私にはほほえまなかった)。そもそも、西村の推察に反して、砂が「宙づりの期待」を共有してくれるとは(比喩的な意味でなければ)思えないからである。たしかに、私たちの遊びには、人も物も関わりうるし、むしろ大人にとっては、人も物もなしに、まったく一人で遊ぶことは難しいかもしれない。しかし、私の考えでは、人と遊ぶことは、物で遊ぶことと、やはり異なるのである。その日、私は、砂と遊びたかったのでなく、子どもと遊びたかったのである。(だが、彼が、子どもでなく、〈子ども〉であったために、私は彼に遊ばれなかったのである。)
[59] 〈子ども〉とは、いわば「大人の小さなもの」である子どもでなく、そもそも大人とは独立の異質な存在である。詳しい考察は第十回の連載を参照のこと。
[60] ここでは人間以外の生き物には特に触れていないが、犬や猫はもちろん、イルカやシャチも、遊んでいるように見える。とはいえ、〈子ども〉のように遊べるのは、やはり動物の〈子ども〉だけであるのではないだろうか。
[61] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,24-25, 38頁.
[62] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,38頁.
[63] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31, 44頁.
[64] とはいえ、たしかに〈子ども〉はしつこく同じ〈遊び〉を繰り返す。たとえば、私のバケツには実際には二度砂が入れられ(たところで私が止めてしまっ)たのだが、それは原理的には三度でも四度でもありえたはずである。しかし、〈子ども〉は、必ずしもそれを繰り返すわけではなく、突然〈遊び〉を一回かぎりでやめてしまうこともある。それゆえに、私の考えでは、それは、――一箇所の「遊隙」における反復的な「遊動」でなく、――一回かぎりの「遊動」の複数回の再現であるのだが、〈子ども〉のしつこさについては、いずれもう少し踏み込んで考えてみたい。