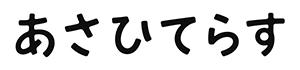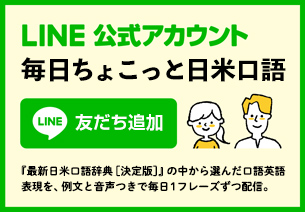第十二回 遊びの現象学(前半)――遊びの構造
遊びの現象学(前半)――遊びの構造
だが、どうして西村の考える遊びは、大人にも(大人になる)子どもにも遊べるのか。――大人だって遊べるに決まっていると思う人もいるかもしれないが、大人は驚いてしまうような〈子ども〉にしかできない〈遊び〉があるわけである。――それは、彼の考える遊び(現象)が「人間のもっとも基本的な存在様態のひとつ」[16]と見なされるからである。すなわち、西村は、「バンヴェニストにならって、『遊びをひとつの特殊な行動としてではなく、むしろ人間のすべての行動がとりうる、ある種の様態(modalité)として』考えて」[17]いる。そして、「遊び手がある行動様式のうちにとるひとつの独特の存在様態、あるいは、そのような存在様態を支えている、ある共通の構造関係が見いだされはしないかを探索する」[18]ことが、彼の『遊びの現象学』が目指すところである。
たしかに、西村の言うように、遊び(現象)は「人間行動のいたるところに見いだされる」[19]。というのは、第三回の連載に書いたように、私たちが自由にすることは、おそらく何でも遊びになるからである。たとえばサッカーは遊びにも仕事にもなる。もちろん、誰でもそれを仕事にできるわけではないし、仕事もまた遊びになるのなら、遊びで働く人もいるかもしれない。(あるいは、園庭で園児とサッカーをする幼稚園の先生は仕事で遊んでいるのかもしれない。)しかし、ワールドカップの決勝で戦う選手たちはけっして遊びでサッカーをしているわけではない(し、休日に公園で子どもとサッカーをする親はけっして仕事で遊んでいるわけではない)。だが、どんなことであれ、遊びですることができるとはいえ、そもそも、遊びでするとは、どのようにすることなのか。それは、「『遊び手にとって、(…)いかなる様態であるのか』」[20]。もちろんそれは遊び(現象)の様態であるだろう。私たちは、遊んでいるときには、そのような様態にいるのである。とはいえ、それは一体どのような様態であるのか。
西村によれば、遊びの様態には、それを支える「共通の構造関係」がある。つまり、どんな遊びをする、どんな遊び手であれ、遊んでいるのなら、その「共通の構造関係」に支えられる様態にあるわけである。では、遊びの様態を支える「共通の構造関係」とは、どのようなものなのだろうか。
まず、西村は「遊隙」と「遊動」という語を導入する。というのも、遊びがあるということは、そこに遊びが生じる余地と、そこで自在に揺れ動く往還がある、ということだからである[21]。そして、彼はこれらをそのまま遊びの様態を支える構造の「もっとも単純な骨組み」[22]と考える。だが、それらはより具体的にはどのようなことなのか。西村が「遊びの祖型」と呼ぶ「いない・いない・ばあ」を通して見てみよう[23]。
それは、二人の遊び手、たとえば母と子が、一つの連係を共有することから始まる。この遊びの連係への加入の儀礼は、通常お互いが見つめ合うことで設定される。その後に、母は、「いない・いない」と言いながら、顔を覆い隠す。このときの母の声は、子の注意を引き付け、母はなお覆いの背後にいるという理解を助ける。これに対し、子は、母が再び現れるのを期待し、今か今かと待ち受ける。そして、子の興奮が高まったところで、この遊びの核心が期待通りに現れる。すなわち、母が、「ばあ」と言いながら、覆いをとって、再び顔を見せる。最後に、母と子は、緊張から解かれ、笑いながら、再びお互いに見つめ合う。こうして、二人は最初の儀礼に戻り、この遊びは一巡する。
西村は、「いない・いない・ばあ」は、「(…)遊びというものの骨格、つまりふれあいの遊戯関係、宙づりにされた期待の遊隙、同調された遊動、遊ぶものと遊ばれるものとのあいだの役割交替を、もっとも単純で透明なかたち見せてくれる(…)」[24]、と述べている。だから、それが「遊びの祖型」なのである。ところで、ここでは、「遊隙」と「遊動」だけでなく、「遊戯関係」と「役割交替」もまた、遊びの様態を支える構造の骨格と見なされている。そこで、以下では、これら四つの遊びの骨格をそれぞれ確認しておこう。
まず、「遊隙」とは「宙づりにされた期待の遊隙」である。すなわち、遊びには「未決定で不安定で自在な余裕」[25]がある。もちろん子の期待は必ず実現されねばならない。というのも、たとえば仮に「いない・いない」で終わってしまったら、「いない・いない・ばあ」で遊んだことにならないからだ。けれども、母が「ばあ」と現れるまで、それは宙づりにされている。なぜなら、母は、それをいつどのように実現させるか、自在に変えられるからである。たとえば、母は、「いない・いない」の後、すぐに現れるかもしれないし、しばらく現れないかもしれない。あるいは、少し大きな声で「ばあ」と言うかもしれないし、少し面白い顔で現れるかもしれない。だから、期待がいつどのように実現されるかは、あらかじめ決まっているわけではないし、それゆえに、子はそれを知る由もない。つまり、その間それは宙づりにされているのである[26]。
だが、「遊動」とは「同調された遊動」である。だから、母だけが自ら動き、子はたんにそれを待っているわけではない。たとえば、母が、しばらく現れなければ、子は焦れて急き立てるかもしれないし、面白い顔で現れたら、さらに笑って喜ぶかもしれない。また、子がさらに楽しそうであれば、母は、次はさらに面白い顔をするかもしれないし、しかし、急かされたことで、さらに現れるのを遅らせるかもしれない。こうして遊ぶ母と子の間には、「(…)ひきよせてははぐらかし、追いかけては身をひく両者の呼吸の、デリケートな同調と往還の遊動がある」[27]、と言える。すなわち、遊び手と遊び相手は、期待が実現されるまでは、「遊隙」の内で互いに同調し付かず離れずの「遊動」を反復するのである。
でも、どうしてそんな同調が可能なのだろうか。それは、西村によれば、遊び(の様態)というものが、そもそも「相互的な同調」[28]の関係だからである。なるほど、第七回の連載で見たように、遊びは伝統的には自由な活動と定義されていた(し、私も〈遊び〉は自由な行為であると考えている)。しかし、西村はそれを遊び手を主体とする能動的な活動とは見なさない。そうではなくて、彼によれば、遊びとは、遊び手と遊び相手の間の「(…)いずれが主体とも客体ともわかちがたく、つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス的関係」[29]なのである。これが彼が「遊戯関係」と呼ぶものである[30]。だから、たとえば、「いない・いない・ばあ」で遊ぶ母と子は、――母が子を遊ぶのでも、子が母を遊ぶのでもなく、――互いに「と・遊ぶ」関係にある。すなわち、母は子と遊び、子は母と遊ぶ――もしくは母と子が遊ぶ――のである。あるいは、二匹のじゃれ合う子犬は、どちらが主体とも客体ともなく、互いに噛み合ったり組み合ったりする[31]。ここにあるのは、――たとえば他の種類の遊びと区別される「競争(アゴン)」という種の遊びではなく、――「いない・いない・ばあ」で遊ぶ母と子の間にあるのと同じ、「『と・遊ぶ』ふれあいの[遊戯]関係」[32]である。すると、遊び手は、遊ぶときには、それが人であれ物であれ、つねに遊び相手に同時に遊ばれることになる[33]。鍵束を掌で玩ぶ遊び手(の掌)は鍵束と「ふれあいの遊戯関係」にあるのである。
また、それゆえに、「遊ぶものと遊ばれるもの」は、「おたがいにその役割を投げかえし、交換しつつ遊ぶ」[34]ことができる。たとえば、子は、十五か月くらいになると、かつては母の役割だった隠す側に回るし[35]、あるいは、じゃれ合う二匹の子犬は、交互に飛びかかったり逃げ回ったりする[36]。(とはいえ、鍵束はいかにして掌の役割を引き受けるのだろうか。鍵束でも掌を玩べるのだろうか。)さらに、この「役割交替」は「鬼ごっこ」などに顕著である。たとえば、「変わり鬼」や「増やし鬼」では、――捕まった人が鬼になるので、――皆、鬼になるまいと鬼から必死に逃げるだろう。しかし、実は、「鬼から完全に逃げ切ることが、鬼ごっこという遊び行動の本質なのではない」[37]。そうではなくて、「挑発してははぐらかし、追われては、反転して追うという、宙づりのスリルにこそ、その本質はある」[38]。だから、最後まで逃げ切った人も、今度は鬼になって他の人を追ってみたくなるのである[39]。
以上の四つが、西村の考える、遊び(の様態を支える「共通構造」)の骨格である。とはいえ、おそらく、「宙づりにされた期待の遊隙」と「同調された反復的な遊動」は、――彼によれば、「もっとも単純な骨組み」であるのだから、――「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」と「遊ぶものと遊ばれるものの役割交替」よりも、さらに基礎的な骨組みである、と思われる。だが、本当にすべての遊びが「遊隙」と「遊動」を宿しているのだろうか。たしかに、大人(になる子ども)にも遊べる遊びは、――西村が『遊びの現象学』で展開するように、――「遊隙」と「遊動」から説明できるかもしれない。しかし、大人には遊べない〈遊び〉はどうだろうか。〈子ども〉にしか遊べない〈遊び〉もまた「遊隙」と「遊動」から理解できるだろうか。はたして〈子どもの遊び〉に「宙づりにされた期待の遊隙」と「同調された反復的な遊動」があるだろうか。もしそうだとしたら、私たちは〈子どもの遊び〉に驚かないのではないか。
[16] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[17] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[18] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[19] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[20] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[21] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,24-25頁.
[22] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,38頁.
[23] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,38, 41-42, 44頁.
[24] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,44頁.強調傍点引用者。
[25] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,25頁.
[26] とはいえ、西村によれば、それはいわば「仕組まれた宙づり」である。彼は、「ゆりかご」と「ブランコ」を例に挙げ、次のように述べている。「ゆりかごやブランコの心地よさは、子どもと母親がわらいかける遊びの連係の枠組みのなかで、同意され仕組まれた、往還の遊動の軽快な同調にある。幼児も子どもも、大きくせりあがって、一瞬宙づりになる。だからといって、かれらがそこで自己をうしないめまいをおぼえる、などということはない。なぜなら、この宙づりは、遊隙のうちに仕組まれた宙づりであり、つぎの瞬間にはかならず降下することが知られているからである」(西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,55頁)。
[27] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,37頁.
[28] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31頁.
[29] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31頁.
[30] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,32頁.
[31] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,45頁.
[32] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,45頁.
[33] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,33頁.
[34] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,43頁.
[35] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,43頁.
[36] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,45頁.
[37] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,97頁.
[38] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,97頁.
[39] Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,76頁.