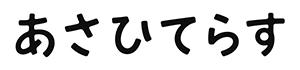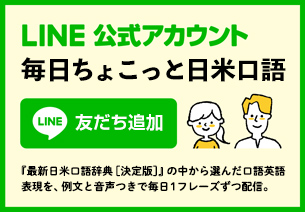第十一回 遊びの現象学(前半)――遊びの哲学へ
遊びの現象学(前半)――遊びの哲学へ
ここまでは、哲学以外の遊び研究、すなわち、遊びの社会学と遊びの心理学を検討してきたが、そこで主眼が置かれるのは、「遊びとは何か?」という問いよりは、むしろ「なぜ遊ぶのか?」という問いであった。むろん「なぜ遊ぶのか?」も興味深い問いではある。しかし、遊びに(必然的な)原因があるとは思えない。なぜなら、遊びとは、そもそも、してもしなくてもよい、自由な行為だからである。また、〈子どもの遊び〉は、自己目的的であるのだから、〈遊び〉以外に何か目的があるわけではなく、したがって、「なぜ〈子ども〉は遊ぶのか?」と問われても、「〈遊び〉のために」と答えるしかない。しかし、そもそも〈遊び〉とは何なのか。
たしかに、カイヨワは、ホイジンガに倣って遊びを定義し、さらに遊びを「競争(アゴン)」、「偶然(アレア)」、「模擬(ミミクリ)」、「眩暈(イリンクス)」の四つに分類しているので、一見すると、「遊びとは何か?」という問いに答えているようにも見える。しかし、彼の遊びの四分類(と「パイディア」と「ルドゥス」の二極)は、私たち大人に馴染みのある種々の遊びを互いの区別と関係から体系的に整理するものであって、私たちにとって未知であり驚異である〈子どもの遊び〉の本質を洞察するものではない。あるいはむしろ、それ(ら)は「なぜ、ある種の社会では、ある種の遊びが遊ばれるのか?」という問いに答えるために道具立てられる。彼が『遊びと人間』で目論むのは「遊びを出発点とする社会学」だからである。もはや彼の視線は、遊び自体でなく、社会に向けられている。カイヨワは、遊びから社会を考察したいのであって、遊び――少なくとも〈子どもの遊び〉――自体を洞察したいのではない。
同じことはピアジェの遊びの心理学についても言える。すなわち、彼によれば、子どもの遊びは「実践のあそび」、「象徴的あそび」、「ルールのあるあそび」に分けられるが、これらは「なぜ、ある発達の段階では、ある種の遊びが遊ばれるのか?」という問いに答えるための道具立てである、と言える。むろん、彼の興味は、カイヨワと違って、子どもの遊び(と発達の関係)にある。しかし、彼が研究する子どもは、潜在的にはすでに大人である。なぜなら、(発達)心理学が調査するのは、諸星が「子供の遊び」で描くような〈子ども〉ではなく、やがて成長し大人になりうる子どもだからである。――そもそも、〈子ども〉の心理学は、それが大人から独立の存在であるなら、いかにして可能なのだろうか[1]。――おそらく、諸星の描く〈子ども〉は、大人と一緒には遊ばない。それは大人とは別の異質な存在だからである。しかし、ピアジェによれば、初めは「実践のあそび」を遊ぶ子どもたちも、いずれ成長し大人と共に「ルールのあるあそび」を遊べるようになる[2]。この意味でピアジェもまた〈子どもの遊び〉の洞察に注力しているわけではない。彼が論究したいのは、大人から独立の〈子ども〉でなく、大人に成長しうる子どもなのである。
したがって、カイヨワもピアジェも、そもそも〈子どもの遊び〉自体をまっすぐに見ているわけではない、と言える。そうではなくて、彼らの視線はむしろ〈遊び〉の外に向けられている。むろん彼らの見ているものは互いに異なる。つまり、カイヨワが見ているのは人間社会の変容であるが、ピアジェが見ているのは子どもの心の発達である。しかし、彼らはいずれも遊び以外のものを遊びと結びつける。そして、社会や発達から遊びを論じている。あるいはむしろ、遊びから社会や発達を論じている。これが彼らの(遊び)研究の方法である。
ここで彼らの研究が因果(関係)を前提することは明らかである。というのも、一定の原因からは一定の結果が生じる(傾向がある)と信じることなしには、遊びとそれ以外の何かの関係を一般化し、一方から他方を論じることに、正当な理由を与えられないからである。もちろん、たとえば、雨が上がったら虹が出た、と述べるのに、因果(関係)の信念は前提されなくてよい。それ(ら)は、偶然つながって経験された、過去の事実の報告でありうるからである。しかし、むろん彼らの研究はたんなる過去の事実の報告ではない。たとえば、カイヨワが、原始的な社会では「模倣(ミミクリ)」と「眩暈(イリンクス)」の遊びが支配的である、と論じるとき[3]、彼は、――具体的な国名をいくつか挙げてはいるが、――個々の国の遊びについての事実を報告しているわけではない。そうではなくて、彼は、どんな社会であれ、原始的であるなら、「模倣(ミミクリ)」と「眩暈(イリンクス)」が支配的である、すなわち、原始的な社会では一般に「模倣(ミミクリ)」と「眩暈(イリンクス)」が遊ばれる、と主張しているのである。同じことはピアジェについても言える。つまり、彼もまた、観察した個々の子どもの遊びについて、たんに事実を述べているのではなく、そこから一般的な理論を導いているのである。たとえば、彼は、言語以前の発達の段階は「実践のあそび」に特徴づけられる[4]、と書いている。しかし、これはもちろん、彼の観察した子どもがたまたまそうだった、と言っているのではない。彼は、言語以前の発達段階では一般に「実践のあそび」が遊ばれる、と言っているのである。
ようするに、カイヨワもピアジェも、たんに個別的な事実を報告するのでなく、むしろ一般的な理論を提唱している。(あるいは、個々の事実を自らが唱える理論の一事例として分析している。)このような個別事例からの一般化の根底には、因果(関係)の信念がある[5]。というのは、もし仮に、どんな原因からでも、どんな結果でも起こりうる(と信じる)のであれば、あらゆる社会ないし発達の段階で、あらゆる遊びが生じうることになってしまうからである。だが、彼らによれば、一定の社会ないし発達の段階では、一定の遊びが生じる(傾向がある)のである。彼らがそのように言(うことが正当だと思)えるのは、彼らが、一定の原因からは一定の結果が生じる、と信じているからである。さもなければ、彼らは自らの一般化をいかにして正当化するのだろうか[6]。
さて、彼らの研究が、遊びと因果的につながる何かから、遊びを論じるのなら、(あるいは、遊びから遊びとは別の何かを論じるのなら、)彼らの研究は、因果(関係)を前提する科学的なものである、と言える。というのも、すでに第二回の連載で引用していたように、西村清和によれば、「科学的精神は、観察された所与事実の根拠としての因果性を究明する」[7]からである。だが、それゆえに、遊びの社会学も心理学も「なぜ遊ぶのか?」という問いにしか向き合えない。すなわち、遊びの科学的な研究は、「(…)『ひとは、なぜ遊ぶか』という原因を、また『ひとは、なんのために遊ぶか』という目的因を問う」[8]ことしかできない。しかし、そもそも私たちは「〈遊び〉とは何か?」がわからないのである[9]。だから、西村の言うように、むしろ「問わるべきは、『遊びとはなにか』である」[10]。これは、原因や目的にかかわる科学的な問いでなく、「本質にかかわる(…)哲学的な問い」[11]である。
哲学的な問いが本質を求めるのなら、遊びの哲学は、遊び以外の何かでなく、まさに遊び自体に目を向けなければならない。これを見事に体現しているのが、西村の『遊びの現象学』である。――もちろん、私たちもまた遊びの形而上学として後にそれを体現するつもりである。――
だが、――私たちの問いが、「〈遊び〉とは何か?」であるのに対して、――西村の問いは、「『当の遊び手にとって、遊びとはなにか』である」[12]。すると、西村の問いは実は私たちの問いと異なる。なぜなら、私たちが探求する〈遊び〉の遊び手は、もちろん〈子ども〉であるが、第十回の連載で書いたように、〈子ども〉とは、私たち大人から独立した、まったく異質な存在だからである。それゆえに、私たちは、「遊び手にとって、〈遊び〉とは何か?」と問うことはできない。(あるいは、問えるとしても、答えられない。)私たち大人には、〈子ども〉にとってということが一体どのようなことであるのか、見当もつかないからである。なるほど、〈子ども〉であれば、それがどのようなことであるのか、知っているのかもしれない。だが、〈子ども〉がそれを教えてくれるとは思えない。また、教えてくれたとしても、大人にそれがわかるとも思えない。
では、西村の考える遊び手とは、誰なのだろうか。――西村自身が〈子ども〉でないかぎり、――それはもちろん大人である。あるいは、いずれ大人になる、大人と同質の子どもである。彼は日常にある遊びを具体的に次のように描写している。
わたしはいま、目的地へとむけて、街路をあるいている。まちあわせ場所には、恋人の笑顔がまっていて、わたしをむかえてくれるはずである。土曜日の午後、天気は申し分なく、約束の時間には、まだ十分、間がある。ゆるやかな風は、柳の枝葉を気まぐれになびかせては、川面をかすめて、さざなみをざわめかせ、微細な波頭が、あかるい陽光の反射を、わたしの目にきらめかせる。かろやかな足どりが、全身につたえてよこす律動にさそわれて、わたしは、口笛をふき、あるいは、ポケットにさぐりあてた鍵束を、掌で玩ぶ。わたしが、鍵束をかるく投げあげては、ふたたび掌におさめるたびに、鍵どうしが打ちあって、軽快な音を、わたしの耳にひびかせる。ときにわたしは、掌をつよくにぎりしめたりゆるめたりして、その金属のつめたい感触をたのしむこともある。約束の時刻までに、わたしは目的地に到着しなければならない。これは、あらかじめ計画され企てられた、真剣な行為である。しかも、たしかにここには、遊びがある。[13]
これは西村が『遊びの現象学』第二章「遊びの祖型」の冒頭で挙げる遊びの具体例である。たしかに、この「わたし」が西村であるとはかぎらない。しかし、ポケットの鍵束で遊ぶのは、間違いなく大人でしかありえない。そもそも、〈子ども〉は、恋人と待ち合わせないし、約束の時間なんて考えもしない。柳の枝は振り回したくなるし、川面には石を投げたくなる。軽やかすぎる足どりで急に走りだしたり飛び跳ねたりもする。〈子ども〉にはきっとこんなに穏やかな土曜の午後は訪れない。
したがって、西村が考察する遊びとは、大人にも遊べる遊びである、と考えられる。もちろん、西村の挙げる遊びの事例には、(大人よりも)子どもがよく遊ぶ遊びもある。たとえば、第四章「かくれんぼの現象学」で考察される「鬼ごっこ」や「花いちもんめ」は、子どもが遊んでいる様子を連想させるし、第五章「玩具の存在論」に登場する「独楽」や「お面」も、たしかに子どもがよく遊ぶものである。しかし、それらは、〈子ども〉にしか遊べないものでなく、大人にも遊べるものである。実際に(大人である)西村はもうすぐ二歳になる次男と「お面」で遊んでいるし[14]、私も自分の子どもや姪っ子たちと「かくれんぼ」をすることがある。すると、――〈子ども〉にしか遊べない〈遊び〉があるとしても、――大人にも(子どもにも)遊べる遊びがあることになる。西村の『遊びの現象学』が探求する遊びはこれである。すなわち、第六回の連載の言い方をするなら、――私たちの形而上学的な遊び研究の対象は(自然)世界に存在する〈遊び〉であるが、――彼の現象学的な遊び研究の対象は(人間)社会に現象する遊びである。だから、西村は、「遊び手にとって、遊びは、いかなる現象(…)であるのか」[15]、と考えられるのである。そして、西村にとっての遊び手とは、もちろん人間である。それは、社会の一員である大人であり、いずれ大人になる子どもである。
[1] この問いは、物自体の物理学や過去自体の歴史学がいかにして可能であるのか、という問いと類比的であるだろう。
[2] Cf. ピアジェ・J.『遊びの心理学』大伴茂訳,黎明書房,1973年9月20日,56頁.
[3] カイヨワ・ロジェ『遊びと人間』多田道太郎・篠塚幹夫訳,講談社学術文庫,2022年11月1日,146-147頁.
[4] ピアジェ・J.『遊びの心理学』大伴茂訳,黎明書房,1973年9月20日,53-54頁.
[5] ここでは、遊び以外のものが遊びと因果的に結びつけられるので、「因果(関係)の信念」と書いたが、もちろん、因果(関係)の信念の代わりに、「自然の斉一性」の信念を考えてもよい。
[6] いわゆる帰納(的な一般化)の正当化の問題であるが、ここで詳細を論じることはできないので、興味のある方は、拙著『なせこれまでからこれからがわかるのか―デイヴィッド・ヒュームと哲学する』第5章「どうして自然の歩みは変わらないのか?―自然の斉一性と一般化の正当性」を読んでいただきたい。
[7] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,11頁.
[8] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,11頁.
[9] とはいえ、これはおそらくカイヨワとピアジェの問いではない。彼らはむしろ遊びから遊び以外のことを論じようとしている(ように見える)からである。
[10] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,17頁.
[11] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,17頁.
[12] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.
[13] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,20頁.
[14] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,166-168, 177頁.
[15] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,19頁.