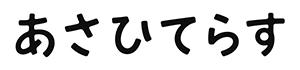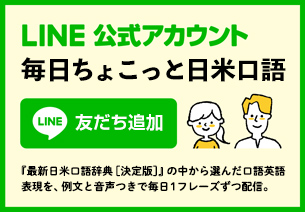第十三回 遊びの現象学(後半)――一人きりの一回だけの〈遊び〉(前半)
遊びの現象学(後半)――一人きりの一回だけの〈遊び〉(前半)
西村清和の名著『遊びの現象学』は私たち人間に現象する遊びの謎を解き明かしている。彼によれば、遊ぶということは、たとえば走ることや踊ることに並ぶような、種々の行為の一つでなく、むしろ、人間のどんな行為もとりうる、一つの独特な存在様態である。だから、私たちは、たとえば遊びで働くことも学ぶこともできるように、どんなことでも遊びですることができる。とはいえ、それは一体どのようにあることなのか。遊びでするとは、どのようにすることなのか。西村は、そこには遊び(の様態)を支える共通の構造がある、と考える。すなわち、何かが遊び(の様態)で為されるとき、そこには「遊隙」と「遊動」と「遊戯関係」と「役割交替」がある。彼によれば、これらが遊びの(様態を支える)共通構造の骨格である[40]。
だが、本当にあらゆる遊びがこれら四つの骨格を有するのだろうか。たとえば、「宙づりにされた期待の遊隙」と「同調される反復的な遊動」は「遊びの構造の、もっとも単純な骨組み」[41]と見なされるが、「遊隙」や「遊動」を欠いた遊びはありえないのだろうか。あるいは、「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」はどうだろうか。私は二歳の〈子ども〉と砂場で遊べていなかった。――あるいは、彼は砂と遊んでいたのかもしれないが。――だとしたら、「遊ぶものと遊ばれるものの役割交替」はどうなるのだろうか。大人である私には彼の〈遊び〉はまったくできそうにない。私は〈子ども〉のようには遊べない。――もしかしたら、砂にはそれができるのだろうか。砂は〈遊び〉でバケツに入ったのだろうか。――そもそも、どんなことでも〈遊び〉になるのなら、〈遊び〉に共通の構造なんてあるのだろうか。また、仮にあるとしても、大人にそれがわかるだろうか。〈子ども〉が遊ぶとき、大人に何ができるだろうか。ただ驚くことしかできないのではないか。
以上が西村の『遊びの現象学』に対する私の疑問である。なぜ以上のような問いが生まれたのかと言えば、それは、〈子ども〉は一人きりの一回だけの〈遊び〉を遊びうる、と思われるからである。そして、一人きりの一回だけの〈遊び〉には、西村の唱える遊びの構造が見いだせないからである。まず、一人きりの〈遊び〉が可能であるのなら、「宙づりにされた期待」は共有されない。なぜなら、そこには共有する相手がいないからである。すると、一人きりの〈遊び〉には「宙づりにされた期待の遊隙」がないことになる。また、「遊隙」がないのなら、「同調される反復的な遊動」もなくなってしまうだろう。というのも、そこには「遊動」が反復する余地がないからである。(したがって、反復しない「遊動」ならありうる。)以下では、一人きりの一回だけの〈遊び〉の姿を描き出し、西村の『遊びの現象学』への批判的な応答を試みよう。
まず、〈子ども〉が一人きりの〈遊び〉を遊ぶことができるとすると、真っ先に疑わしくなってしまうのが「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」である。たしかに、たとえば私が子どもとキャッチボールをするとき、そこには「遊び手と遊び相手とのあいだにおのずから生じる、主・客わかちがたい関係」[42]がある、と言える。なぜなら、私の「遊ぶという行動様態は(…)同時に遊ばれることでもある」[43]からである。つまり、そのとき私たちは互いに遊ばれながら遊んでいるのである。けれども、私は本当にいつでも彼と遊べているだろうか。たとえば、――第四回の連載に書いたように、――彼がノコノコを壁にぶつけたり崖に落としたりしているとき、私は本当に彼と「マリオカート」をしているのだろうか。もちろん、私たちは(同じ画面を共有し)同じレースに参加しているし、彼(のノコノコ)は私(のヨッシー)にもぶつかってくる。しかし、明らかに彼は私とは遊んでいない。彼は、自在にノコノコを操り、一人でケタケタ笑っている。私はそれに戸惑うばかりである。それでも私は他のNPC[44]とレースを楽しむことはできる。しかし、私は〈子ども〉と遊びたいのである。NPCに遊ばれたいのでなく、〈子ども〉に遊ばれたいのである。けれども、レースが始まっても動かない〈子ども〉と一体どのように遊べばいいのだろうか。ノコノコが急に逆走を始めたら、ヨッシーは何をすればよいのだろうか。
なるほど、私が〈子ども〉と遊ぼうとしても、彼はノコノコと遊んでいるのかもしれない。(すると、私はヨッシーと遊んでいることになるのだろうか。)だが、彼に遊ばれたいのは、ノコノコでなく、私である。(私はヨッシーと遊びたいのではない。)私が彼と遊びたいのである。
とはいえ、彼にとっては、ノコノコと遊ぶことも、私と遊ぶことも、同じ〈遊び〉であるのかもしれない。たとえば、私たちが掌で鍵束と遊ぶことについて、西村は次のように述べている。
わたしはけっして主体たる資格で、意図してポケットをまさぐり、鍵束に手をのばして、これをつかみとったわけではなかった。それは、まちあわせの場所への道すがら、ただほんのついでに掌にはいってきたのであり、気がついたときには、わたしの掌と鍵束とは、ふれあいの同調のただなかにともにあったのである。[45]
もちろん、鍵束は、人でなく、物である。しかし、西村は、掌と鍵束のふれあいにも、――「いない・いない・ばあ」で遊ぶ母と子と同じように、――「いずれが主・客ともわかちがたい力動的な遊びの様態が現象する」[46]、と考える。つまり、人(の一部である掌)は物(である鍵束)との「相互的な同調という関係」[47]にも巻き込まれる。彼の『遊びの現象学』によれば、人と物が遊ぶということは、そういうことなのだ。人が物で遊ぶとき[48]、人と物の間には、――「いない・いない・ばあ」をする母と子の間にあるのと同じ、――「『と・遊ぶ』ふれあいの遊戯関係」があるのである。
なるほど、もしかしたら、〈子ども〉にとっては、人と遊ぶことも、物と遊ぶことも、同じ〈遊び〉であるのかもしれない。というのも、自然(世界)の一部である〈子ども〉にとっては、おそらくすべてが自然(世界)の一部であるからである。つまり、〈子ども〉にとっては、人もまた物である。もちろん、〈子ども〉は、親とも遊ぶし、兄妹とも友達とも遊ぶ。しかし、〈子ども〉は、むしろ、石でも棒でも、砂でも水でも、何でも遊べる。――たしかに物でも遊べる大人もいるかもしれない。だが、大人は〈子ども〉のように何でも遊べるわけではないだろう。――というのも、〈子ども〉は(人間)社会の外で遊ぶからである。
だが、それゆえに、〈子ども〉が遊ぶのは、(人間)社会の遊びでなく、(自然)世界の〈遊び〉である。つまり、それは、大人にも遊べるものでなく、〈子ども〉にしか遊べないものである。そもそも〈子ども〉は(人間)社会のないところで遊ぶのである。だから、〈子どもの遊び〉では、誰であれ何であれ、すべてが(自然)世界の一部でしかないのである。けれども、西村の『遊びの現象学』が考究するのは、大人にも遊べる(人間)社会の遊びである。だから、そこでは特に子どもは大人と区別されない。いや、むしろ〈子ども〉はそこに登場しない。そこに出てくるのは、大人と同調して遊ぶ子どもである。そのような子どもは、西村の言うように、きっといずれ大人と役割を交替する。それはまさに大人になりゆく子どもである。
しかしながら、大人が遊べる(人間)社会の遊びにおいて、物との遊びは本当に人との遊びと同じなのだろうか。私たちは本当に、人と遊ぶように、物と遊べるのだろうか。おそらく、西村なら、然りと答えるだろう。だが、物が人のように期待を共有できるとは思えない。「いない・いない・ばあ」で遊ぶ母と子のように、鍵束が私(の掌)と期待を共有できるとは思えない。私が操作するヨッシーでさえ、私と同じ期待を共有できるとは思えない。なぜなら、物は人と違って期待しないからである。
西村は、がらがらで遊ぶ母と子の間の「宙づりにされた期待の遊隙」について、次のように書いている。
両者のあいだに期待がある、ということは、両者のあいだにいまだ充実されないひとつの不在がある、ということである。(…)それは、つぎの瞬間には確実に充実されるはずの、猶予としての不在であり、まだならぬがらがらへの、いわば「宙づり」にされた期待と、それから生じる、両者のあいだに架けられた天びんの動揺、「いまか・いまか」、「もうちょっと・もうちょっと」と気をもたせてははぐらかす、つかずはなれずの遊動をこそ生みだすための、仕組まれた不在である。(…)両者のあいだに仕組まれ、わらいのうちに留保されたこの遊隙のうちで、宙づりの期待が共有され、緊張と解消とからなるひとつの遊動が維持され、反復されるのである。[49]
もしかしたら、西村もまた、文字通りに、物が期待を共有する、とは思っていないのかもしれない。――とはいえ、彼は、たとえば、風になびく柳の枝、波頭に反射する陽光、魚の涼しげな回遊、ひばりの美しいさえずりなどを「(…)遊びと見ることは、たんなるメタファー以上の意味をもっている」[50]、とも書いている。――だが、彼によれば、「(…)それ自体は自然法則にのっとった諸現象も、すくなくとも、これを注視するわれわれの目には、気まぐれであてどない往還の遊動とうつり、遊びと見ることがある」[51]のである。だとすれば、たしかに物でさえ人のように遊べるように見えるのかもしれない。物でさえ私たちと「宙づりの期待」を共有できるように見えるのかもしれない。
しかしながら、母と子の「いない・いない・ばあ」は、遊びである。遊びに見えるのではなく、遊びなのである。彼女らの間では、「宙づりの期待」が、共有されるように見えるのはなく、共有されるのである。なぜなら、彼女らは人だからである。人は、物と違って、不在の充実を期待するからである。これが人と物の違いである。それゆえに、人と遊ぶことは物と遊ぶ(ように見える)ことと異なるのである[52]。
さて、「宙づりの期待」が共有されなければ、(少なくとも西村が論じる)遊びの構造の骨格が崩れてしまうことになる。だが、それで〈遊び〉が終わってしまうわけではない。なぜなら、〈子ども〉は一人で遊べるからである。たしかに私は二歳の〈子ども〉に砂場で遊んでもらえなかった。そこに「宙づりの期待」の共有はなく、それゆえに私たちは一緒に遊べなかった。しかし、彼は明らかに遊んでいた。砂場に座り込んで、穴を掘ったり、砂をばら撒いたり、私が汲んできたバケツの水に砂を(二度も!)入れたり、私が砂場に作った池に棒を突き刺したり、結局は池にも砂を入れ続け泥でぐちゃぐちゃにしてしまったり。これが〈遊び〉でなくて何であろうか。これはまさに〈遊び〉でしかないのではないか。
とはいえ、もちろんそれは砂との遊びでもない。砂は「宙づりの期待」を共有しないからである。たしかに、先述したように、自然(世界)の一部である〈子ども〉は、砂でも遊べるにちがいない。なぜなら、〈子ども〉が遊ぶところには、そもそも自然(世界)しかないからである。すなわち、〈子ども〉はそもそも自然(世界)で遊ぶ。だから、自然(世界)の一部である砂で遊べるのである。だが、その意味では私もまた〈子ども〉にとっては自然(世界)の一部である。すると、彼は私でも遊べるはずである。なるほど、もしかしたら、彼は私でも遊んでいたのかもしれない。(もちろん私よりも砂で遊んでいたのだが。)けれども、それはもちろん私との遊びではない。「宙づりの期待」を共有し、誰か「と・遊ぶ」のは、人間(社会)の遊びだからである。――むろん、西村によれば、何か「と・遊ぶ」こともできるのだが、私たちにとって物「と・遊ぶ」ことは人「と・遊ぶ」ことと本当に同じ(構造をもつ)だろうか。たとえば、一人で楽器を演奏するのと仲間と一緒に演奏するのは、やはりまったく違う遊びではないだろうか。――
では、〈子ども〉はいかにして遊ぶのか。おそらくそれは〈子ども〉からの一方的な〈遊び〉である。すなわち、私は〈子ども〉と遊べなかったが、〈子ども〉は私を遊んでいた。しかし、私は彼と「宙づりの期待」を共有できなかった。大人である私には〈子ども〉のように遊ぶことはできないからである。(あるいは、そもそも〈子ども〉には共有されるべき「宙づりの期待」がないのかもしれないが、これは次回の連載で詳しく論じるつもりである。)だから、〈子ども〉は一人で私を遊んでいた。そして、もちろん(私よりも面白いので)砂を遊んでいたのである。
ようするに、〈子ども〉はすべて「を・遊ぶ」、と言えるだろう。つまり、〈子ども〉は自然(世界)を遊ぶのである。もちろん、西村が指摘するように、私たちは、「鍵束を玩ぶ」とか「鬼ごっこをする」とは言うが、「鍵束を遊ぶ」とか「鬼ごっこを遊ぶ」とは言わないので[53]、〈子ども〉は自然(世界)と遊ぶ、と言ってもよい。しかし、「と・遊ぶ」という言い方からは、まさに西村の遊びの構造が呼び起こされてしまうのである。だから、私たちはここではあえて「を・遊ぶ」という表現を用いなければならない。〈子ども〉は砂とも私とも「宙づりの期待」を共有しないからである。〈子ども〉は一人で自然(世界)を遊べるのである。〈子ども〉は、誰とも何とも遊ばなくても、一人ですべてを遊べるのである。
[40] 西村が提案する遊びの(様態を支える)共通構造については、第十一回と第十二回の連載を参照のこと。
[41] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,38頁.
[42] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,32頁.
[43] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,33頁.
[44] Non Player Characterの略。直接プレイヤーが操作しないキャラクターのこと。
[45] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,30頁.
[46] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31頁.
[47] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31頁.
[48] 西村によれば、「(…)『鍵束と遊ぶ』、あるいは『鍵束で遊ぶ』とは、わたしの掌が、鍵束『と』の相互的な同調という関係にまきこまれており、その遊隙の場『で』、さまざまに生起する気分や状況『に・遊ぶ』ことを意味している」(西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,31頁)。
[49] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,38頁.
[50] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,25頁.
[51] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,25-26頁.
[52] もしかしたら、『遊びの現象学』では、人との遊びでさえ、遊びに見えるだけなのかもしれない。とはいえ、もし仮に一切がそのように見えるだけ――あるいは現れるだけ――であるのなら、わざわざ「である」でなく「見える」と言うことの眼目が失われてしまうだろう。
[53] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,30-31頁.