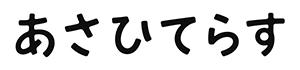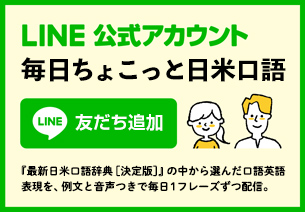第十六回 〈遊び〉の形而上学 ――〈遊び〉の質料因
〈遊び〉の質料因
いよいよ私たちは〈遊び〉の形而上学への一歩を踏み出さなければならない。これまで見てきた遊びの諸研究――すなわち、遊びの社会学、遊びの心理学、遊びの現象学――では、大人(になる子ども)にも遊べる遊びが総じて研究されていた。しかし、これから見ていくのは、大人にも遊べる遊びでなく、〈子ども〉にしか遊べない〈遊び〉である。それは、いかなる原因も目的もなく、それ自体のためにのみ為される〈遊び〉である。それは、特に決まった形もなく、たんに実現される〈遊び〉である。
とはいえ、どうしてたんなる実現の〈遊び〉が探求されなければならないのか。遊びの諸学はすでに遊びを研究し尽くしているのではないか。――実はたんなる実現の〈遊び〉も大人にも遊べるのではないか。――それを形而上学的に探究する余地など本当にあるのだろうか。
なぜ私たちは〈遊び〉を探求しなければならないのか。もちろんそれは私たちが〈遊び〉に驚くからである。それは〈子ども〉にしかできない〈遊び〉であり、それゆえに私たち大人にはそれがわからないからである。たしかに、どんな知の探究も驚きから始まるのなら、たとえば、カイヨワも変容する社会の遊びに驚いたのかもしれないし、ピアジェも発達する子どもの遊びに驚いたのかもしれない。だが、彼らが驚いた遊びに私たちはもはや驚けない。というのも、そうした遊びの原因や目的はすでに彼らに明らかにされ(私たちに知られ)ているからである。もちろん西村もまた日常的に見られる遊びに驚いている。『遊びの現象学』の冒頭で彼は子どもたちが遊ぶかくれんぼに惑わされている[1]。しかし、だからこそ彼は諸々の遊びに共通の構造を自ら探し求めたのではないか。もし遊びに驚いていなければ、そもそも遊びの本質は探究されなかったのではないだろうか。だが、ひとたび遊びに共通の構造がわかってしまうと、その構造をもつ遊びにはやはり驚けなくなる。なぜなら、そうした遊びはまさに型にはまっているからである。(もちろん、西村によれば、それらはまさに型にはまっているがゆえに遊びであるのだろうが。)
しかし、私たちにはなお驚く〈遊び〉があるのである。それが〈子ども〉にしか遊べない〈遊び〉である。まず、私たちは〈子ども〉が原因も目的もなく遊ぶことに驚く。〈子ども〉は、何の原因もなく、何の目的もなく、まさに遊ぶためだけに遊ぶことができる[2]。だから、それはたんなる実現の〈遊び〉なのである。だが、大人にはそれは至難の業である。ただ何かをすることなど大人には到底できない。なぜなら、およそ大人がすることには、原因か目的があるからである。私たち大人は因果的に生きざるをえないのである。また、私たちは〈子ども〉が型破りに遊ぶことに驚く。〈子ども〉は、遊ぶためなら、どんなことでもしてしまうのである。だから、〈子ども〉のたんなる実現の〈遊び〉には、何か共通の構造があるわけではない。むしろ共通の構造を逸脱して遊べるのが〈子ども〉である。〈子ども〉はどんなことでも〈遊び〉でしてしまうのである。だが、型にはまっていないからこそ私たちは驚くのである。私たちは見慣れた型通りの遊びには驚けない。しかし、〈子ども〉は型破りに遊ぶので、私たちは驚かされてしまうのである。そして驚きから探求が始まるのである。
とはいえ、どうして私たちの〈遊び〉の探求は形而上学であるのか。それはなぜ、科学でなく、哲学であるのか。そして、なぜ、現象学でなく、形而上学であるのか。まず、――すでにこれまでにも何度か西村の洞察を引用し指摘してきたように[3]、――科学(者)は研究対象の原因ないし目的を究明しようとする。つまり、遊びの諸科学が浮かび上がらせるのは、遊び(の本質)とは何かではなく、遊びと因果的に関係する何かである。たとえば、それは、社会の文明的な動向であるかもしれないし、あるいは、子どもの心理的な発達であるかもしれない。すると、遊びはたしかに遊び以外のことから因果的に説明されることになる。しかし、それが何であれ、遊びの原因や目的は、もちろん遊びそのもの(の本質)ではない。そうではなくて、それは、――たとえ遊びと因果的な関係があるとしても、――遊びではない何かなのである。だが、西村の『遊びの現象学』は、遊びの原因や目的でなく、むしろ遊びの本質を探し求める。だから、彼の遊び研究は、科学的なものでなく、哲学的なものなのである[4]。とはいえ、彼の研究は、もちろん、現象学であって、形而上学ではない。というのも、彼の研究はまさに遊びの形を見て取るものだからである。つまり、諸々の遊びに共通の型が見いだされるには、そもそも諸々の遊び(現象)が見えるのでなければならない。ここで私たちは特に「形而上学」という(訳)語にこだわっているわけではない[5]。だが、およそ私たちの目に映るものはすべて何らかの形がなければならない。そして、形があって見えるものは、形而上のものでなく、形而下のものなのである。
では、これに対して、私たちの〈遊び〉研究が形而上学的なものであるのはなぜなのか。私たちは本当に形を超えて〈遊び〉を探求できるのか。たしかに、たんなる実現の〈遊び〉には、何か特定の決まった型があるわけではない。というのは、どんなことであれ、〈子ども〉の手にかかれば、何でも〈遊び〉になってしまうからである。もちろん、たんなる実現の〈遊び〉も何かでなくてはならないだろう。さもなければ、それは、私たちに現れることができず、したがって私たちを驚かすこともできないからである。
すると、この意味ではどんな〈遊び〉にも何らかの型があることになる。しかし、〈子ども〉のたんなる実現の〈遊び〉には、一定の決まった型があるわけではない。だから、主に第十三回と第十四回の連載で論じたように、――西村の推察に反して、――遊隙も遊動もない〈遊び〉が〈子ども〉にはありうる。なぜなら、〈子ども〉は一人きりの一回だけの〈遊び〉を遊べるからである。たとえば、がらがらを手にした〈子ども〉は、ただちに降って音を鳴らすこともできるが、しかし、飽きたらすぐに手放してしまうこともできる。あるいは、〈子ども〉は、私を「マリオカート」に誘っておきながら、いきなりコースを逆走し始めるし、何度も壁にぶつかったり崖に落ちたりしているし、急に走るのを止め、ただコース上で私やNPCが通り過ぎるのを見送っている。こうした〈遊び〉はもちろん西村の考える遊びではない。――西村の遊びの構造に倣えば、私たちの順位が宙づりにされたゴールまでの遊隙の内で互いにアイテムを使ったり使われたりしながら抜きつ抜かれつの遊動を繰り返すことが「マリオカート」の遊び方であるだろう。――だが、何でも唐突にしてしまう〈子ども〉はやはり遊んでいるのである。私たちの洞察では、むしろ〈子ども〉は期待を宙づりにしておけない。何でもいきなり実現してしまうのが〈子ども〉なのである。
にもかかわらず、〈子ども〉が唐突にすることは、やはり〈遊び〉でしかない。というのは、まさにそれはたんなる実現にすぎないからである。すなわち、それは、何の原因もなく、何の目的もなく、ただそれ自体のためにのみ実現されるのである。〈子ども〉は何か特定の(遊隙や遊動のような)決まった形の実現を目指して遊んでいるわけではない。だから、〈子ども〉の実現の〈遊び〉には、共通する型なんてないのだ。〈子ども〉は、何であれ、ただ実現するためにのみ、実現することができる。これが〈遊び〉が自己目的的であるということの形而上学的な意味である。〈子ども〉は何でも〈遊び〉で実現できる。〈子ども〉はまさに遊ぶために遊ぶからである。
では、私たちの実現の〈遊び〉の探求は一体どのようなものになるのか。残念ながら、この問いに答えることは今はできない。というのも、それはまさに今から私たちが探し求めるものだからである。もちろん、今ここで大まかな見取り図が描けたら、これからの探求が少しは楽になるのかもしれない。けれども、私たちの〈遊び〉の探求には、全体を見渡せる地図はなく、それがどのようなものになるのかは、今はまだまったくわからない。(もしかしたら、どこへも進めなくなってしまうかもしれないし、同じところをさ迷い歩くことになるかもしれない。)にもかかわらず、〈子ども〉に驚かされてしまったからには、少しでも〈遊び〉の謎に切り込んでゆきたい。そのためには、まったくの手探りで一歩ずつ歩を進めなければならない。
とはいえ、私たちの探求の全貌は眺め取れなくても、それを他の研究と対比することで遊び研究の全体に組み込むことはできるかもしれない。というのも、私たちの〈遊び〉研究は、第一には、社会学でも心理学でもないのだから、科学ではなく、哲学なのであるが、第二には、現象学ではなく、形而上学であるからである。このことを改めて確かにしてくれるのは、アリストテレスの四原因である。すなわち、彼が区別する四つの原因(の意味)を通して遊びの諸学を透かし見れば、私たちの〈遊び〉研究は質料因的なものに位置づけられそうなのである。
さて、アリストテレスによれば、私たちは、原因を知っているからこそ、物事を知っている、と言えるのだが[6]、彼の主張する四つの原因は、科学的なものと哲学的なものに二分できる、と思われる[7]。たとえば、朝にはなかったリースが帰宅後の玄関ドアに飾ってあったら、私は「なんでリースがあるの?」と妻に尋ねるかもしれない。これに対し妻はどのように答えられるだろうか。まず、妻はその作用因(あるいは始動因)を私に知らせることができる。つまり、――もちろん私はそんなことを聞いているわけではないのだが、――たとえば「それは私が作って飾ったから」と彼女は答えられる。また、彼女はその目的因を答えとすることもできる。たとえば、「もうすぐクリスマスだから」と答えられたら、私はそれがクリスマスを祝うために飾られたのだと納得するかもしれない。すると、そのリースについては、それを作り飾る妻(の動き)とクリスマスを(華やかに)祝うことが、それぞれその作用因と目的因である、と言える。そして、これら二つの原因は科学的なものである、と言える。というのも、妻(の作業)と(華やかな)祝祭は明らかにリースそれ自体とは別のことだからである。すなわち、その作用因と目的因は、むろんリースと因果的に関係するが、リースそれ自体に見いだされることではない。この意味で作用因と目的因は科学的な原因なのである。
同じことはもちろん遊びの諸学についても言える。遊びとは別の(社会の動向や子ども発達のような)何かを持ち出して、遊びとの因果的な結び付きを発見するのは、遊びの科学なのである。たしかにそれ(ら)は遊びの作用因や目的因であるかもしれない。しかし、それ(ら)は、遊びとは別のことであり、遊びそのものではないのである。
では、遊びそのものに見いだされる原因とは何か。アリストテレスは、作用因と目的因の他に、さらに二つの原因を挙げている。形相因と質料因である。たとえば、私が「このリースはなんで(何で)あるのか?」と聞き、――たとえ私が望んでいる答えではないとしても、――妻が「それはこのような設計(図)で」と答えるなら、そのリースの形相因が知らされることになる。これはもちろんそのリース自体の内に見いだせることである。というのも、あることの形相因とは、まさにそれが何であるのかということ、すなわちそのことの本質に他ならないからである[8]。つまり、まさにそのような(特定の大きさの土台に固有に配置された特定の諸パーツから構成される)リースであることが、そのリースの形相因なのである。あるいは、私の「このリースはなんで(何で)あるのか?」という問いが、――もちろん本当にそれを聞きたければ「何で作られているのか?」と聞くべきだが、――妻の「モミの葉とかワイヤーとか松ぼっくりとかシナモンスティックとか」という答えを導くなら、そのリースの質料因が与えられることになる。ようするに、何かの質料因とはそれが作られているところの素材ないし材料である。そして、これもまたそのリース自体に内在する原因である。というのは、それが何でできているのかは、それ自体を見ればわかるからである。すると、アリストテレスの四原因のうち、――作用因と目的因は科学的なものであるが、――形相因と質料因は哲学的なものである、と言える。それらは、――研究対象と関係するが異なる何かでなく、――研究対象それ自体の内にあるからである。
では、同じことは遊びについても言えるだろうか。遊びについて形相因と質料因を探ることはできるだろうか。おそらく西村の『遊びの現象学』が遊びの形相因的な探求であることは明らかであるだろう。というのも、彼の現象学的な探求は、まさに諸々の遊び現象に共通の形を見いだすものだからである。西村によれば、あらゆる遊び(現象)には、それを遊びたらしめる、共通の(遊隙と遊動のような)型がある。それが彼が見つけた遊びの形相因である。それによって彼は「遊びとは何か」という本質を尋ねる問いに答えているのである。
しかしながら、従来の遊びの諸学には――私の知るかぎり――質料因的な探求はない。ここに私たちの〈遊び〉研究が入り込む余地がある。私たちはまずは〈遊び〉の質料因を探し求めたい。ここから私たちの〈遊び〉のメタフィジックスは始められる。
[1] 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,1頁.
[2] だから、〈子ども〉たちは、「今日、学校が終わったら、一緒に遊ばない?」と言って、ただ〈遊ぶ〉だけの約束をすることができる。しかし、大人たちは、「今日、仕事が終わったら、一緒に遊びませんか?」とは言えないので、代わりに「映画に行きませんか?」とか「飲みに行かない?」とか言ってしまうのである。
[3] たとえば、すでに第二回の連載では、「科学的精神は、観察された所与事実の根拠としての因果性を究明する。いまや、ひとはあらためて、遊び行動という、生物学的、心理・生理学的事実のかくされた根拠を、したがって、『ひとは、なぜ遊ぶか』という原因を、また『ひとは、なんのために遊ぶか』という目的因を問う」(西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,11頁)、と引用されている。また、第八回と第十一回の連載でも同じ個所が部分的に引用されている。
[4] もちろん西村自身このことに自覚的である(Cf. 西村清和『遊びの現象学』勁草書房,2023年3月15日,17頁)。
[5] 明治期に井上哲次郎が編纂した『哲学字彙』において英語の「metaphysics」の訳語として導入された「形而上学」という日本語は、古代中国の『易経』にある「形而上者謂之道、形而下者謂之器」(形より上のもの、之を道と謂い、形より下のもの、之を器と謂う)という一説に由来している(Cf. 小坂国継「アリストテレスの形而上学」『研究紀要,一般教育・外国語・保健体育』第79号,日本大学経済学部,2015年10月,5頁;秋葉剛史『形而上学とは何か』ちくま新書,2025年8月10日,34-35頁)。
[6] アリストテレス『形而上学(上)』出隆訳,岩波文庫,1998年5月6日,31頁.
[7] したがって、第八回の注76は、正確でなかったので、修正されなければならない。すなわち、もし何かを因果的に知ろうとすることに、作用因と目的因だけでなく、形相因と質料因も含まれるのなら、前の二つの探求はたしかに(自然)科学的であるが、後の二つの探求は哲学的である、と。
[8] Cf. アリストテレス『形而上学(上)』出隆訳,岩波文庫,1998年5月6日,31頁.