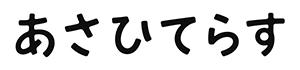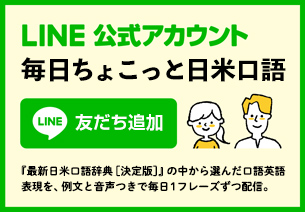第14回 数字と記号の題名
小説や演劇、映画、音楽、漫画や絵画など、あらゆる作品の「内容」はほとんど問題にせず、主に題名「だけ」をじっくりと考
第14回は、映画化、ノベライズまで決定したウォーキングシュミレーションゲームと、見た目や声のかわいさと、激しいパフォーマンスとのギャップで目が離せないアーティストの曲、小学生と中学生の狭間の空気感を描きヒットした少女漫画の題名です。
★今回で本連載は最終回となります! 現在、年内書籍化に向けて制作中です。これまで読んでくださったみなさま、ブルボン小林さん、ありがとうございました。(編集部)
日焼け止めを買ったことはないが、「SPF50PA++」とかいう表記は気になる。
なにをいってるんだろうといつも思っている(説明を受けたことはあるがうろ覚えで、でも聞くたびに気になる)。
アルファベットはともかく、そこに50という数字と、+という記号、なぜ二種類のものが必要なんだろう。(企業努力などで)効き目が強まっているのなら、数字が増えていくだけでよかったんじゃないか。+を複数重ねているのも面白い。プラ(ス)プラ(ス)、という響きの連なりにも良いリズムが生じている。なんか、玄人っぽいのだ。
日焼け止めに縁がないのに、そうまで気にさせる力が記号と数字にはあるわけだ。題名にももちろん、有効だ。今回は数字と記号の題名。
1.「8番出口」KOTAKE CREATEのゲームの題名
低予算で作られたゲームだそうだが大ヒットし、映画化しノベライズもされた(川村元気作)。その映画もヒット中だ。
最初は、それほどぐっとくる題名とも思えなかった(悪いものでもなく、ごく普通の題と受け止めていた)。しかしここまでのヒットを思うに、題名にも独特な力があったのではないか、と感じられるようになってきた。
筆者は遊んだことはないのだが、梗概は知っている。
どこにでもあるような駅の構内から出られなくなった主人公が謎を解いて脱出するゲームだ。題名の中に、目的(=脱出すること)が「出口」という言葉に端的に示されている。
無味乾燥な、装飾のまるでない題名で、そのことは「どこにでもあるような」気配を醸し出している。ゲーム本編で描かれる(のであろう)非日常の恐怖(駅から出られない)と対比するためにそうしたと思われる。
ここで題名に「出られない」「恐怖」などの語を入れてしまうと、都市伝説的なクールな怖さが減じてしまう。
もちろん「出口」だけでは題として説明が足りない。〇番出口ということで、おそらくは駅だろうと舞台が自然に示される(漢数字でない、算用数字であることも、公共の場の気配を伝えている)。
そこで選ばれた出口の数字、8が絶妙だ。
1番~3番出口くらいまでは割と小規模な駅でもありうるので、都心の迷宮のような広さの駅を連想してもらえなくなる。
4番~7番出口も、それが最大値なのか(つまり、そこが中規模の)駅なのか、もっと上の数の出口がある(大規模の)駅なのかを絞りにくい。
8番出口あたりから、(それが最大値でないのだとしても)けっこう大きな駅であろうと、作品規模の見当がつくようになる。
9番出口だと、ホラーゲームの場合「9=苦」を思わせてよさそうだ。
でも、10番出口以降になると梅田地下か新宿か銀座か、逆に駅のイメージが具体的に絞られてきてしまうのではないか。
そうすると、8か9が規模的に理想の駅を思ってもらえそうだ。
で、8が9に勝っているのは数字の形である。無限のループを描く8が、出られないというルールを絵面で示すことができている。
これは9=苦のストレートなミーニングよりも気付かれにくいものだが、気付かれなくても構わないわけで、後から「そういえば」と思えた人にだけ作用する。
なお、1~7を「不向き」と書いたが、それぞれの数字ごとに少しずつ、印象の差はある。1番出口なら利用者が多そうだし、2番は「メインの出口の反対側」という感じもする。6と7はなぜかマイナーな、利用者の少ない出口を筆者は思い浮かべる。作品の中身によってはそれぞれの数字の効き目を活かせるかもしれない。
とにかく、数字にも色がある、なんでもいいわけではないということを忘れずにいたい。
2.「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」anoの曲名
当連載第5回で語った「二物衝撃」の取り合わせの題名だが、すごい運動神経で並んだ二物だ。
「ゆうぐれダイアリー」のほうは、昭和にもありうる語彙で、「骨バキ」はもろに令和の語彙。
さっと検索しただけなので間違っているかもしれないが、別にネットミームやスラングとして「骨バキ」があるわけではないのらしい(その語で検索すると、最上位にはこの曲名が出てくる)。とにかく、昭和や平成のクリエイターはそんな語を思いつかないし、題にも採用できなかった(「骨」という単語も「バキバキ」というオノマトペもあったのにだ)。
肩や背中が凝っての「骨バキ」も思わせるが、「相手の肋骨に膝を入れた」とか「腕の骨を折る」といった、格闘技的な骨折の方を想起する人が多いだろう。
『臨死!! 江古田ちゃん』の「臨死」や、『這いよれ! ニャル子さん』の「這いよれ」といった、「これまではそうは使わなかった」語の使い方だ。それが繰り返されるうち(文化が)だんだん揉みほぐされて、「骨バキ」も題に銘打たれるし、こちらも説明される前から受容できる脳になっている。
ところで、「骨バキ」の手前に「臨死」「這いよれ!」を置いてみたのは、語の選択に新規性があったからだけではない、題においてその三つに共通項を感じたから連想したのだ。
「臨死」も「這」っていることも「骨がバキバキ」になっていることと遠くない。うっすらとダメージの気配がある(……臨死は「うっすら」どころじゃないか?)。
いずれも題名の切り出しにあっけらかんとダメージを匂わせていることで、自虐を用いての元気さを標榜しているのだと思う。

そのヤケになっている暴力的な気配とは相反するほど抒情的、過去回想的な「ゆうぐれダイアリー」のてらいのない青春性とが、ミスマッチのような、むしろ青春の色を濃くするような、深い衝突をもたらしている。
そして、ここからが今回の本題だが、間を取り持つ(?)「☆」の効きがいい。
この☆は、ひとまず「ゆうぐれダイアリー」に属するものだと思う。ダイアリーなどという前時代的な単語に、さらに「乙女チック」な「ファンシーさ」を付加してみせている。
でも、これは全体(つまり「骨バキ」の方)にもちゃんと作用している。肩こりなのか骨折なのか分からないが物騒で不穏な言葉の深刻さを、コミカルさでコーティングしている。
だが、そのコーティングで不穏さがまるで覆い切れていない。「わざと」そうしていることは明らかだ。不要な星があえて置かれたその恣意性から、「そうしている『人』」の存在がほの見える。それで題(の中の☆)から不遜さや稚気を含んだ「人格」が立ち昇ってくる。
記号の中でも(!や?と違い)星やハートは、文字ではない。文字の中にありながら絵として機能する。
だから『きまぐれオレンジ☆ロード』と同様にセンターではない、やや左(「きまぐれ~」は右)に添えているのも、どセンターだとエンブレムっぽくなってしまうからだろう。
題名をロゴにしたときのことまで含め、髪飾りのようなデザインとして考えられているのだ。
・『臨死!! 江古田ちゃん』瀧波ユカリの漫画(講談社)の題名
・『這いよれ! にゃるこさん』逢空万太の小説(GA文庫)の題名
・『きまぐれオレンジ☆ロード』まつもと泉の漫画(集英社)の題名
3.『12歳。』まいた菜穂の少女漫画の題名

数字には単位や年号が付随することが多い。それで「意味」がうっすら生じるようになっている(先の「出口」もだ)。
『海底二万マイル』『母を尋ねて三千里』などにおける数字は、ただのデータではない。すごく長い、途方もない距離という「意味」だ(なんなら、作中の実測値は三千里ではなかったりする)。
『アイコ16歳』は、主人公(アイコ)が思春期、多感な時期だと誰もが思う。
(先に取り上げた)『九十歳。何がめでたい』だと、長寿の内実を問う内容であることが具体的な数字に込められている。これをたとえば「ご長寿。何がめでたい」にするとより広いレンジに向けた題になるが、むしろ全員をとり逃すことになる。逆に「九十」という具体的数字は、九十一歳や八十九歳に興味を持たれないなんてことはない(このことは、後述する通り、すべての年齢の数字で有効というわけでもないのだが)。
思春期や中年や老人、卒業、退職などの節目になる、キャッチーな数字がいくつかある。
そんな中『12歳。』をみたときは驚いた。その年齢を「題にする」んだ! と。
創作において、何歳をテーマにしてもいいはずなのだが、12歳はテーマになりにくい、となぜか思っていたのだ。
それこそ、年齢「だけ」を題にした歌を、筆者はよく耳にしてきた。ザ・ハイロウズに『14才』、奥田民生に『30歳』、人間椅子にも『三十歳』、爆風スランプには『35才』がある。それぞれ「その年齢」らしさがテーマになっていることが分かるし、たとえ中身が私小説的な中身だとしても、「そういう年齢」を歌っているのだから、普遍的な共感を描いた内容であるはずだ。
つまり「どの人でもその年齢なら当てはまる」ことが歌になっているのだ、と思わせる。
で、(内容は問わず)年齢を作品の題名につけるという試みに絞った際、『12歳。』には特に感心したし、驚いた。
「14才」や「(アイコ)16歳」の年齢の数字はまさに思春期の真っ只中のものだから「なんらかの作品で語られるに足る」感じがした。自然な曲名であり映画名だ。
それに対し12歳はまだまだ子供で、その年齢に向けて「作品」を放つ意義があるのか? と感じたのだ。
たとえば『8歳』や『10歳』という「題名」のフィクションは広まるだろうか。そういうテーマのフィクションを作ることはできるが、そう題することの意義がどれだけあるだろう。当事者にまず、訴求しないだろう。俺たちの世代のことが書いてあるぞ、読んでみよう、とか思わない。
中年が在りし日のことを郷愁と共に思い返したくなる数字も「14才」あたりからではないか。8歳や10歳だったら『少年時代』(という題)でいい。
もちろん、少女漫画の読者には12歳の子が大勢いる。でも、多くの少女読者は背伸びをして、少し大人の少女のフィクションをみている(『セーラームーン』も、幼児に向けたアニメ『プリキュア』シリーズも、主人公は中学生だ)。
だから、盲点だった。
別に、12歳の(女子の)普遍的なことを描いてよかったのだし、題にしてもよかった。
ちょうど「12歳」は小学六年生と中学一年生のはざまだ。小学生と中学生にまたがる数字は「12」しかない。
スマホを買ってもらえる・もらえない、制服を着る・着ない。さまざまな激変の両方にまたがる唯一の年齢だ。背伸びをして恋愛漫画を読む当事者たちでもある。つまり、充分に語るに足るものがある。
そういった誰かを主人公に据えて、その子供の名前で題名をつけるのでも構わなかったろうが、それだと別の年齢の主人公の漫画とさして変わりがないことになる。
普遍的な広がりを感じさせる、すべてのその年齢の人に「自分のこと」とわかってもらえる、端的にして最適な題名として年齢が選ばれた。読者を捉える網がとても大きい、それゆえか本作はどこか風格のあるヒット漫画になった。
なお、内容まで踏み込んでみると、本作では主人公的なヒロインが三人入れ替わる。オムニバスにせず、三人に絞ったことで、オーソドックスな恋愛漫画としても楽しめるようになっている。
それでも三人も入れ替わること自体が斬新であり、題名がちゃんと機能しているともいえる。似た例ではちばあきおの『キャプテン』がある。これも題の通り、一人の主人公でない「キャプテン」がどんどん入れ替わっていく漫画で、題が作品の機能性を示している。
これらは作品の根幹から導き出された題であり、作品のテーマが強固だから題名に必然性があり、揺るがない気配が漂う。たとえ地味な言葉選びでも「言いえて妙!」と、長く読者の心を打つものだと筆者は思う。
・『海底二万マイル』ジュール・ヴェルヌの冒険小説の題名
・『母をたずねて三千里』1976年に放送された日本アニメーション制作のアニメの題名
・『アイコ16歳』1982年に放送されたTBS制作のテレビドラマの題名
・『少年時代』井上陽水の曲名
さて、この連載は今回で一応の最終回となります。年内単行本化を目指して鋭意作業中です(実は、ブルボン小林デビュー25周年記念作品でもあります)!
来月以降も、単行本化にあわせてのなんらかの更新があると思うのでお楽しみに。
ひとまず、長らくのご愛読ありがとうございました!
◎ 好評発売中! ◎

『増補版・ぐっとくる題名』 著・ブルボン小林(中公文庫)
題名つけに悩むすべての人に送る、ありそうでなかった画期的「題名」論をさらに増補。論だけど読みやすい! イラストは朝倉世界一氏による新規かきおろし!