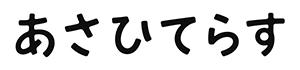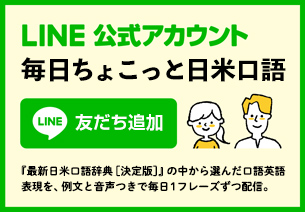ベビーキャリアとスタイのタグ
平日の午後の地下鉄はまだ空いていて、広い空席を選んで座ると、はす向かいに座っていた白いブラウスの女性が、赤子を抱いていることにはじめて気がついた。ぱちっぱちっという乾いた音がしたので顔を上げると、女性がベビーキャリアのバックルをなめらかに外し、片方の手のひらで厚手のパッドをささえていた。その上にぽやぽやとやわらかい茶色の毛の生えた、小さな頭頂部がのぞいているのが見え、パッドにはガーゼがかぶせられており、その白が女性の服と同化していたので、赤子の存在に気づかなかったことがわかった。赤子はおそらく目が覚めたばかりで、動きもなくぼんやりとしていたが、母親と思われる女性はそのまま頭を支えながら、ぐーっと赤子の身体を反らせてみたり、膝の上で赤子を持ち上げ、ぽーんぽーんとジャンプするような動作をさせてみたりしていた。
ターミナル駅に着くと車内はすこし混みはじめ、女性の横には大きな鞄を提げたべつの若い女性が座った。赤子がときどきその若い女性をじっと見つめるので、若い女性はスマートフォンを操作する指を止め、ときどき赤子のほうを見て笑いかけたり、首をかしげて手をふったりしていた。赤子を抱く女性はそのことに気がついていないように見え、中空を見ながら赤子の背中をとん、とん、と一定のリズムで、やさしくたたいていた。
やがて地下鉄は地上へ出て、抱かれた赤子の視線は窓の外の流れる景色へとうつった。赤子の見る車窓をわたしも見つめながら、窓のむこうのいまこの景色とは、あの子どもにとってどのように見えるのだろう、これらの景色が記憶に刻まれないのだとしたら、赤子が見ているこれらのものたちはどこへ行くのだろう、というようなことを茫洋と考えた。窓を見ている赤子の首もとには、スタイのタグが見えていた。白いタグは赤子の首に貼りつくようにして、この製品の扱いと安全についてを訴えていた。自分の子どもがあの赤子と同じくらいの月齢だったころ、タグがとても好きだったことを思い出した。めったに行くことのない外資系の量販店で何枚も買ったタオルの、手触りのがさがさとした大きめのタグがとくに好きで、布団にころがりながらよく齧っていた。
しばらくすると母親とおぼしき女性はベビーキャリアのバックルを、時間を巻き戻すように慣れた手つきで、ぱちんぱちんと取り付けなおして降りていった。赤子の白いふくらはぎと足裏が、女性の下腹あたりにむちむちとおさまっていた。隣に座っていた若い女性は、頭をうしろにもたせかけ、真剣な表情でスマートフォンを見つめていたが、やがて彼女も先に降りていった。車内はふたたびまばらになった。
自分の子どもが乳児だったころを、わたしはすでに忘れかけている。育児休暇中で仕事はなく、目の前の子どもとただ向き合うばかりの日々を、子どもが生後八か月になるまでわたしは日記に書いていた。書いたのはおそらく出産後に産科の病院でもらった、乳児用ミルクのメーカーが製作した育児日記で、授乳や睡眠、入浴や排泄など子どもの生活リズムを、見ひらきで一週間記録できるようになっている。宿題などで強制的に書かされたもの以外、自分で日記を書いたことはなく、おそらく今後もないだろう。わたしにとって書くことは記録でも備忘でもなく、見えている現実からすこし自分をずらすためのツールなので、起きたことを記しておく行為に興味をもったことはないが、出産四日後の退院の日から書かれた育児日記は、記録することで子どもの生活や成長を可視化するところから、育てるという未知の営為を手さぐりですすめようとした、自分の切迫感にあふれている。出来事は箇条書き程度の文章で記され、ほとんどは排泄の回数を示す正の字や、授乳量の大まかな数字など記号的な記述しかない。自宅に乳児用のスケールは用意していなかったので、授乳前後で子どもを抱いたまま体重計に乗り、その体重の推移を見てどれだけ飲めたかの目安にしたり、測定器のある駅ビルの授乳室まで、わざわざ測りに出かけたりしていたことも、自分の筆跡をたどりながら思い出した。生後五十三日目にはぬいぐるみのうさぎの耳をしゃぶり、翌日には顔にあらわれた湿疹について案じ、その翌日には日中にひとときも眠らず、夕方の沐浴で盛大に泣き出している。
生まれてから三歳までが水平線のように遠かった。一年もう一年と経つうちに、子どもはどんどん手を離れお母さんは楽になっていくよと、保育士の先生から言われたことを呪文のようにくりかえし、自分に言い聞かせていた。つい近ごろまで、風呂あがりの自分の髪にドライヤーをかけていると、きまって子どもの泣き声の幻聴が聞こえてきたが、子どもがひとりで入浴するようになってからは、その頻度もすくなくなり、最近はようやく聞こえなくなった。
午後の電車で赤子を抱く女性を見るまでわたしは、これらのことをひとつとして思い出さなかった。おぼえていることと同じように忘れることも、生きていることによってしか感受できないのだと、やはり茫洋と考えた。赤子は車窓のむこうに見たものをくりかえし忘れつづけることによって、世界をこれから劇的に把握していくのだろう。十一歳になったわたしの子どもも、目の前のいまを丸飲みするように生きているが、あるとき住んでいる団地の入口に、ひょろりと伸びた木を目にして、あんなところに木が生えていたっけ、と驚きながらつぶやくわたしに、前から生えていたよ、と即答されたことを思い出した。前は小さかったけど大きくなったんだよと、子どもがきっぱりとした口調で答えたとき、つないでいた手をふいにほどかれたような、とこしえのような時間をいま、空いた車内にも見たように思った。
『何を読んでも何かを思い出す』 大塚真祐子
言葉で何かを思い出すとき、目の前の日常は意識の裏に隠れるけれど、消えたわけではない。ただ、自分の身体がどの地点にあるのかわからなくなって、ふたたび言葉を手がかりにする。日々はそうしてめぐる。読むこと、書くこと、女性として生きるということなど、言葉をとおして見えた景色を綴ります。