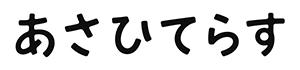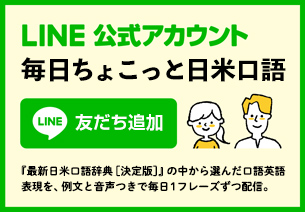「美しい祖父」と10篇の詩 (ナカタサトミ)
あさひてらすの詩のてらすでは、ご投稿いただいた作品の中から、世話人と編集部にて作品の選出を行い、良いと思われるものを掲載しています。今回、投稿作品の中で、一群として読まれることが望ましいと思われる作品がありました。その作品が、ここに掲載するナカタサトミ氏の11篇となります。世話人のコメントともに、ぜひご一読ください。
|
美しい祖父
七月のゆらぐ空 ネオンテトラの水槽 お菓子をつめた青い箱 雨ふる休日も イルカのキスも 君にはみんなやるから どうか帰らないでいておくれ そして 私のまどろみの中にある 早朝のお墓でかくれんぼをしよう |
|
家出のあと
私自身の若いくちびるを通して祖母が 旧い高慢さをスプリンクルしているのを 頭の後ろから見つめるようなとき 火のでるほど恥ずかしいと思う 私の身体は育った虚栄の帝国の 内部がダメになった果物でできていて 私はフケを落としていくのと同じに それらの腐敗汁を滴らせる そのくささが私の生命といっしょに はやく失われてしまえばいいと メンタルクリニックの待合室で けがれのない美しい魚たちを見るにつけ せんないことを考えてしまいます |
|
黒い蝶の少女
あの子はもう十六にもなるのに 黒い蝶が髪にとまれば死ぬという 陰惨なメルヘンを信じていた 他人を睨むように見るので そのことでいつも祖父にきらわれた きらわれているほうがむしろ 彼女にとっては安全だった 祖父とその妻と彼らの二番目の娘は 十六の少女に眠りを許さなかった つくりものの眠りと 無理に拡大された目覚めとが あの子の生命の見えているすべてだった 家族に隠れて非実在の恋人に逢うとき きまって囁きかけるのは 実在しない小説のどこにでもいる女として 私を見つめないでという言葉で しかし実際のところ少女は すべての国のすべての町に暮らす 少し壊れた子どものうち一人にすぎなかった あの洒落た封筒は大きな窓が必要だったのだ 隣のおじさんが誰に言うともなく呟いた |
|
父の標本
大破壊交響楽の雨がふる日 毛布を抱いていた女の子は 獰猛になにかを恋い慕いたいと思う 所在がわからない父親に似た 気団とおなじ 巨大なものを それでいてけっして醜悪ではない たとえば皇帝や 戦争や バクダン 奪い焼きはらうそんな強さでなく 女らしい父を恋人として夢見るのだ 彼は女の子を広く肉付きのよい膝に 彼女の赤いベビー毛布がそうであるように 大切に しかし必死に抱いてやる 父の乳房と心音に頭をすり寄せながら 娘は安心しきって眠るだろう 二人はマイナス千年生きられるだろう |
|
N夫妻と私
たとえば私がパパとママの子ではなく がらんどうを親として生まれた娘だったら どんなに幸せだっただろう 誰にも見つからない 傷から血の不在を流す無口なからだ すれ違うことも ぶつかることもない 注意ぶかく追究された不在は 存在を乗り越えるとシロクマが私に教えた 二〇〇七年の春を夢で見た夜だけ ひとりぼっちになれるのだった |
|
父親泥棒
むかしTという詩人が 母を盗めと若者に説いた しかし青年が母を盗むようには 娘たちは父を盗むことができない 女はその美醜にかかわらず 色さまざまの宝石でできているために かえって盗まれやすいのだ 臆病者の私は父の髪の匂いを 胸深く吸う明け方を夢見ながら 神戸の喫茶店の二階の奥のほうの席に 遊びつかれた犬みたいに座っている |
|
ファンタジー
なり損ないの天使が大粒の真珠で 静かに窒息していくように 彼女の膿んだかさぶたを誰かが 人魚の鱗に喩えたから声を失ったのだと 田舎の娘は翻訳ノートの端に書いた 震える手を美しいと思うとき あなたは一つ罪を犯している それに触れようとするとき また一つ自分をよごしている 逃すまいとしたときには 不可逆的に腐敗している 見つめていたものが娘の血と肉ではなく ヘリコンの山の泉であったことを 無数の老いた少年に知らせようと 女たちがしきりにメモをとっている 鉛筆と紙がこすれるその音の連なりが 甘やかな声をよみがえらせるまで |
|
いやなことヒューズ
少しかすれた声が 都会の娘の醜いところを触って 線路沿いの窓の向こう側へ 行って 行って はるかに行って 音のない音として 小さなネコの子の眠りを妨げるのを すこやかな戯れとするのなら 言えない出来事の果てない連なりで造られた 彼女の身体はどうやって赦されればよいのか わからないでいた 彼女の中の彼女以外が目を醒ますそういう 暗くみじめな交わりは あの人の無邪気がもたらした 遅効性の呪いであり 生活の日々にさしこむ光の針 どこへしまっておこうかと わからないまま今朝も指先を血に濡らして 生命をするということの耐えがたい重さを 感じないでいようとする 身体に棲みついた誰かが |
|
Oへの手紙
ときどき 私のこころは私のからだを離れて 不在ゆえ永遠に呼びかけることができる父や ホテルの廊下や モールの地下駐車場へと 当たり前のように帰っていく 命はみんな命の色をしているが 私はとりわけ隠れるのが下手なのだ そういうお話をあなただけにはしてもいい |
|
Kへの手紙
身体の骨が砕けるというほど 目の前の人に抱きしめられたかった けれど一刻も早く逃げ出したいと思った つながりを滅ぼす激烈さを愛と呼ぶなら 私は人間でなくなりたい どれだけ愛し敬っても かれは知恵のあるただの人だと 思える時間が必要なのに ふれあえばふれあうほど いばらの垣にへだてられる恋人たち 私がいばりくさって見えるのは ふたりぶん さびしさの息をふきこんだから 年下の女に母を見いだすことは あくまで醜悪な気持ちです あなたはそれをやめられない飢えた砂像だ |
|
恋
美しいものについて話す口ぶりで おまえは「いま、恋している」と言う しかし あの老学者やその娘が 幼いおまえを獲物として見る目を みずから身につけてしまって そのけがれた悪魔のまなざしで かれの背中をとらえているのではないか? 私がこのことを囁くと ようやく気づいたふりをしながら はたちすぎの健やかな皮膚を掻きむしって 獰猛にうなりだす 実際のところどこかの男を犯すのではないかと いつも不安でたまらないのだろう あるいは 貞淑な祖母が日頃言い聞かせていたように 望みや秘密やこころの動きは どんなときも他人に知られていると 恐れつづけているのではないか? 彼女はおまえがおまえ自身の祖父と 家の小さな図書室で犯した罪を 執念深く罰しようとしている おまえが夜 あの美しい友人の れんげ畑の香りの胸に やさしく抱きしめられる夢を見ているのも 私たちは知っている |
〈世話人より〉
これらナカタサトミ氏の作品は、投稿された作品群から世話人が選んだものであり、その選択や並べ方は、作者の望むものではないかもしれないが、世話人の考えとして了承していただいた上で、以下に、コメントしたい。
ナカタサトミ氏の作品は、それぞれの完成度が高く、自立しているが、しかも、相互に共鳴しあう。悲痛な叫びを上げる各々の詩作品が、時には直喩や名詞止めによって、時には企まれた散文調によって抑制されながら、担うべきそれぞれそれのパートを変奏してゆく。その主題がわれわれへ伝えたい託けは、なんなのだろうか。
冒頭の「美しい祖父」は、主題のイントロであり、また、作品群全体のイントロでもある。かの者を言葉巧みに誘う<かくれんぼう>(「美しい祖父」)こそが、偽りであり、騙しである。それは、圧倒的な力の差のもとで成立する罠であって、初めから結果を予測できる人間が、遊戯の名の下に、何も知らない人間を、精神的に、肉体的に弄ぶ。それがほんとうに<かくれんぼう>なのだろうか?
そもそも、かの者は、<隠れるのが下手>(「Oへの手紙」)なのである。かの者が引き受けざるを得なかった<私の生命>(「家出のあと」)、あるいは、<あの子の生命>(「黒い蝶の少女」)は、他者によって翻弄されるものとなる。全て、かの者の選択ではなかった。翻弄されることなぞ、誰が望もう。だが、まさしく、かの者こそが、全てを引き受けねばならない。かの者が、たとえ自己処罰を行おうと、<執念深く罰しようと>(「恋」)、かの者が<生命をする>(「いやなことヒューズ」)ことから逃れることはない。それが、定めなのである。
書き手は、では、かの者との距離をどう確保するのだろうか。途上で測りかねている様は、自己同一(「家出のあと」「N夫妻と私」)の状態や、三人称化された<あの子>(「黒い蝶の少女」)、<娘>(「父の標本」)を読めばわかる。「ファンタジー」では、<彼女>、<田舎の娘>、<あなた>と、かの者を呼び替える。
しかし、最後の作品「恋」において、書き手がおのれの自称を<私>から<私たち>へ変えながら、かの者を<幼いおまえ>から<おまえ>と対象化してゆくとき、ついに、救済が訪れるであろう。いや、訪れねばならない。最終行で<私たちは知っている>と語ること、それはありふれた言葉であるけれど、しかし、納得であり、安心であり、共感であり、罪穢れを含めて一切の受容でもあるのだろう。言葉が救済である。
作品それぞれが、非常に複雑で深い感情や内面的な葛藤、人間関係・血縁関係の孕む矛盾と危険性、しかもそれでも、どこかでその関係に依存せざるを得ない人間存在の弱さを、鮮やかに表現している。
(渡辺信二 記)