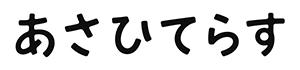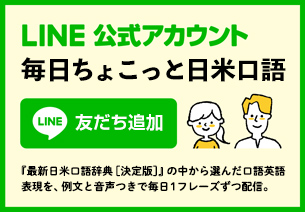Q.142「英語におけるクッション言葉とつなぎ言葉とは?」
英語で話すときに、頭の中で話すことやどのような使う単語や文法などを考えて、結構詰まってしまって、無言になってしまったり、笑ってごまかしたりすることがあり、悩んでいます。もうすこし英語が流暢に話せれば、悩んだりしないと思うのですが、先日英語が比較的得意な人から、クッション言葉を学べばいいと聞きました。英語のクッション言葉(表現?)には、どのようなものがありますか?よく使われるものをお教えいただきたいです。
また、流暢に話す練習として、自分一人でできる良い練習法があれば、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
(トシ、27歳、会社員)
沈黙を埋める表現を知り、より良いコミュニケーションを!
英語を流暢に話す人は、話しているときにあまり沈黙がありませんよね。会話しているときに沈黙があると少し気まずい空気が漂ったりしますし、ある研究によると、会話中に0.4秒以上の沈黙があると、その沈黙の後に、聞き手が聞きたくない内容が話されるケースがよくあるようです。つまり、会話の中で、聞き手が聞きたくないだろうと予測できる内容を話す前には、知らず知らずのうちにためらいがあり、そのためらいが0.4秒以上の沈黙を生み出しているということです。また、聞き手側も、話し相手が少し黙ると、これから聞く内容があまり聞きたい内容ではないことを察知できるようです。
しかし、これらの研究はあくまでもネイティブ同士の会話の話であって、英語を第二言語として使用している学習者が話している場合には、そこまで敏感に沈黙に反応することはないと考えられます。聞いている人がネイティブであってもそうでなくても、話し手がネイティブではないことを理解していれば、沈黙の理由が言いづらい内容のためのためらいというよりは、言いたい内容を伝えるための英語表現を探すのに時間がかかっているということを理解してくれているはずです。
「クッション言葉」と「つなぎ言葉」を学ぶ
それでも、やはり沈黙は避けるに越したことはありません。そこで、沈黙を埋めるための言葉、「クッション言葉」と「つなぎ言葉」を紹介させてください。この二つは、沈黙を埋めるという共通の目的がありますが、実は話す内容によって使用する場面が異なります。これから話す内容が、聞き手にとってあまり聞きたくない内容だと予測できる場合には「クッション言葉」を使い、英語でどのように言えばいいのか考えたり、伝えたい内容を整理するなど、聞き手にとって心地よい内容であっても話すのに時間を要する場合には、「つなぎ言葉」を使用します。
「クッション言葉」の重要表現
まず、「クッション言葉」にはどのような表現があるのでしょうか。一般的に使用されている「クッション言葉」をいくつかリストアップしてみました。「クッション言葉」はその後に続く内容が重要なので、それぞれの「クッション言葉」に例文も書いてみたので参考にしてみてください。
〇相手が聞きたくないと予測できる内容の場合
|
・I’m sorry but … (申し訳ないのですが…) I’m sorry but I don’t think I can join you today. (申し訳ないのですが、今日はご一緒出来なさそうです。) ・I hate to say this, but … (言いたくはないのですが…) I hate to say this, but your insurance does not seem to cover your damage. (言いたくはないのですが、あなたの保険はその損害をカバーしていないようです。) ・You may not want to hear this, but … (このようなことを聞きたくないとは思いますが…) You may not want to hear this, but it looks like your plan costs too much. (このようなことは聞きたくないと思いますが、あなたの計画はお金がかかり過ぎのようです。) |
〇相手が聞きたくない意見をいう場合
|
・It seems to me that … (私には…のように思われます。) It seems to me that you made a wrong choice. (私には、あなたが選択を間違ったように思われます。) ・In my humble opinion, … (私のつたない意見ですが…) In my humble opinion, you should have changed your job earlier. (私のつたない意見ですが、あなたはもっと早く転職するべきだったと思います。) ・With all due respect, … (失礼ながら申しますと…) With all due respect, you could have avoided this. (失礼ながら申しますと、あなたはこれを避けることができたはずです。) |
〇要望や要望や依頼を断る場合
|
・I wish I could, but … (できればそうしたいのですが…) I wish I could, but I can’t go to Hawaii with you this year. (できればそうしたいのですが、今年は一緒にハワイに行けなさそうです。) ・I’d love to, but … (是非そうしたいのですが…) I’d love to, but I’m allergic to dogs. (是非そうしたいのですが、犬アレルギーなんです。) ・I’m afraid that … (残念ながら…) I’m afraid that I have to go now. (残念ながらもう行かなければなりません。) |
「つなぎ言葉」の重要表現
これらのような聞き手がおそらく聞きたくないという内容でない場合にも、頭の中で次に話す内容を考えたり、整理したり、英語でどう表現するかを考えたりする際に便利なのがつなぎ言葉です。いくつかリストアップしたのでここでクッション言葉と一緒に学習しておくと、会話中の沈黙を埋めることができると思います。
〇話す内容や表現を考えている際
|
・Let’s see … (えー …) ・What should I call it … (なんと呼べばいいんでしょうか…) ・How should I put it … (どう表現すればいいんでしょうか…) ・I’m not sure how to say it in English … (英語でどう言えばいいのかわからないのですが…) |
〇言い間違えたときの訂正をする際あるいは詳細を思い出す際
|
・What I’m saying is that … (つまり私が言おうとしていることは…) ・What I mean is that … (つまり私が言おうとしていることは…) ・I mean, … (えー、つまり…) |
〇考えを整理してまとめている際
|
・How can I explain this? (どうやって説明すればいいんでしょうか。) ・Where should I start? (どこから始めればいいんでしょうか。) ・How should I put this? (どう説明すればいいんでしょうか。) |
このような表現は、会話中の沈黙を埋める用途にも使えますし、伝えたい内容次第では、話す前に相手にそれを聞く準備をさせるのにも便利なので、積極的に使ってみてください。これらの表現を使えば、聞き手もその前後に多少の沈黙があることを察知するはずなので、会話の雰囲気を崩さずに済みます。とはいえ、やはりスピーキングの流暢さを磨くのも重要です。そこで、流暢さを磨く練習方法をご紹介させてください。
スピーキング練習で押さえておく3つのポイント!
流暢さを磨くためには、当然ですが、スピーキングの練習が必要になります。それは聞き手がいた方が行いやすいかもしれませんが、一人でも十分できる練習があります。その一人で行うスピーキング練習では、次の3点を念頭におくことが非常に重要です。
|
・簡単な内容と表現を使って練習する ・少なくとも3回は反復する ・時間を計測して早く話すことを意識する |
まず、簡単な内容・表現を使って練習するというのは、現在の自分自身のレベルで言い表せないような、難しい内容や英語表現を使用する必要はありません。ゆっくりでもいいので、あくまでも辞書などの力を借りず、自身の英語力のみで表現できる内容について話をするということです。
多くの学習者は、日本語をそのまま英語に訳そうとしますが、頭に浮かんだ日本語が比較的難しい表現で、その対訳を探すのに戸惑ってしまいます。その難しい表現を上手く英語に訳すのが目的ではなく、言いたいアイデアを言葉にすることが目的です。そのため、難しい日本語表現が頭に浮かんできてしまった際には、小学生にわかるような日本語に置き換えてから英訳すると、自分の力で表現できる物事の幅が広がります。
この練習で話す内容は、少なくとも3分間くらいは話し続けられるような内容が望ましいです。たとえば、「先週起こった出来事で、良くも悪くも一番印象に残った事について」や「小学校時代に仲良かった友人について」など、ストーリーにして話すことができる内容がおすすめです。それぞれのエピソードを詳しく話すこともできますし、実体験がベースなので、それほど難しい表現を必要としないので、流暢さを鍛えるトレーニングに向いているトピックだと考えられます。
反復練習が上達の鍵!
次に反復練習です。流暢に話せるようになる学習者の多くは、反復練習を怠りませんし、反復練習なしに流暢さが向上することもありません。ネイティブももちろんですが、上級者が流暢に話せるのは、同じ内容を以前に何度も話しているからです。私自身もこれまで話したことのない内容を話す際には、必然的に話すスピードが遅くなりますが、それはどのように表現すればいいのか考えながら話しているからです。十分な反復練習が行われると、どう表現すればいいのかを考えるというプロセスがなくなり、自然に口から出てくるようになります。例えば、初級者であってもHow old are you? やWhere are you from?などの表現は比較的スラスラ言えます。その理由は、Wh-疑問文だからHowやWhereを文頭に持ってきて、Be動詞の疑問文だからyou areの語順を入れ替えてare youにして…というように、それぞれの単語を疑問文の構造に当てはめるプロセスを経る必要がないくらい十分な反復が行われてきたからだと考えられます。十分な反復を行うと、文構造や語彙を考えずに表現できるレパートリーが増していくので、それに伴って流暢さが磨かれていきます。反復回数は多いに越したことはないのですが、練習は継続することがとても重要です。そのため、研究で効果があることが分かっている3回を最低回数とすることをおすすめします。同じ内容を必ず3回繰り返し話すようにしましょう。
そして、流暢さを磨くのに重要なのは時間の負荷です。3回以上反復するようにと提案しましたが、毎回時間を測ることが重要です。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目の方が早く話せるようになるように目標を設定します。これは、1回目に要した時間が例えば3分間だったとして、全く同じ内容を2回目では2分間で話すことを、3回目では1分間で話すことを目標にするというように、早く話すための負荷をかけていきます。あるいは、最初から、3分間、2分間、1分間という時間設定をしてスピーキング練習をすると決め、あるトピックについて、1回目は3分間ノンストップで話し続ける、2回目は2分間で1回目に話した内容をすべて話しきる、3回目は1分間ですべての内容を話しきるということを目指すトレーニングも有効的です。この時間のプレッシャーが流暢さを磨くのに不可欠です。
この3つの要素を含む流暢さを磨くトレーニングの効果は、話すスピードにも表れますが、それ以外にも、3回目ではより複雑な文法を使用する傾向が見られたり、1回目や2回目では文法的に誤っていた部分を修正できていたり、反復を重ねるごとに語彙表現が適切になっていたりと、様々な形で表れます。すなわち、総合的なスピーキング力の向上を促す優れた練習方法だということです。
さらに、より高い学習効果を求めるため、録音をすることをおススメします。スマートフォンの録音機能を使用して、ご自身の話した内容を録音して、是非聞いてみてください。聞き手にどのように聞こえているのかを知ることはとても重要ですし、何しろご自身で修正できる箇所が複数あるはずです。話している際には気づかない点でも、聞き手になると気づく点が多々あります。おそらくご自身で想像するよりも多くの気づきがあると思います。録音を聞いて修正箇所をみつけたら、2回目、3回目ではそこを修正することを心掛けると、文法や英語表現が磨かれていきますから、録音しない時より高い学習効果が期待できます。
今回は、会話中の沈黙がテーマでした。「クッション言葉」と「つなぎ言葉」を上手く使いながら、さらには流暢に話せるように3つのポイントを押さえてスピーキング練習をしていきましょう。会話中の沈黙が少しでもなくなるように、日々の練習を重ねることが大切です。頑張っていきましょう!
★編集部より★
英語学習に質問やお悩みのある方は、ぜひ横本先生にご質問をお寄せください。一人で考えて答えが出る悩みもあれば、悩み続けて時間が経ってしまうことも多いと思います。ご質問はこちらから。ぜひお気軽にお聞かせください!